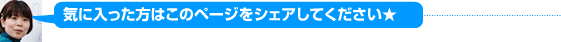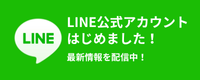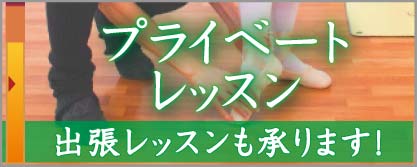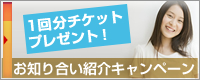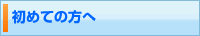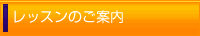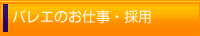バレエKnow
-
7.222025
バレエをもっと楽しく!バレエ整体って?どんな効果があるの?


みなさんはバレエ整体をご存知でしょうか?
成長期の子どもの体は、柔軟性や姿勢を求められるバレエに挑戦する中で、大きな負担がかかることもあります。
そこで注目されるのが、バレエ整体です。
この記事では、バレエ整体が姿勢改善やケガ予防にどう役立つのかご紹介します!
バレエを楽しく安全に続けるためのヒントが見つかりますように。バレエ整体って?

バレエをしている人であれば、「バレエ整体」という言葉を耳にしたことがあるという人も多いのではないでしょうか。
ではバレエ整体では一体どのような施術が受けられるかご存知ですか?
ここではまずバレエ整体についてご紹介します。普通の整体と何が違うの?
バレエ整体が普通の整体と異なるのは、名前の通り「バレエに特化している」という点です。
普通の整体では、一般的な体の不調や歪みを整える施術を受けることができます。
対してバレエ整体は、バレエ特有の動きや体の使い方を考慮した専門的な整体で、バレエに必要な柔軟性や姿勢を重視した施術が行われます。
バレエ経験者やバレエの知識が豊富な整体師が施術し、バレエに特化したサポートが受けられるのが特徴です。なぜ整体がバレエを習う子どもに必要なの?
成長期の子どもは骨や筋肉が発達途上にあり、バレエの練習による負担が大きくなることがあります。
例えば、長時間のレッスンや無理な柔軟性の追求が原因で、姿勢が歪んだり、痛みが生じたりすることがあります。
バレエ整体を取り入れることで、体のバランスを整え、怪我を未然に防ぐことができます。
特に初めてトゥシューズを履くタイミングでは、体への負担が急激に増すため、バレエ整体でのサポートが役立ちます。バレエ整体はどこで受けられる?
「お住まいの地域+バレエ整体」で検索するとお近くのバレエ整体が見つかるでしょう。
最近では、バレエ整体を専門に行う整体院が増えてきました。
「バレエ整体」と看板に掲げている整体院だけでなく、ダンス整体やスポーツ整体としてバレエに対応している院もあります。
インターネットで口コミや評判を確認するのがおすすめです。
InstagramなどのSNSで施術の様子やビフォーアフターなどを載せている院もありますよ。
また、通っているバレエ教室の先生に整体院を紹介してもらうもの良いでしょう。バレエ整体の効果とは?

バレエ整体は普通の整体とは違い、バレエに特化した施術を受けることができます。
ではバレエ整体の施術を受けることで、どのような効果が得られるのでしょうか?
主な効果を3つご紹介します。姿勢改善
バレエでは背筋をまっすぐに保つ美しい姿勢が求められます。
しかし、日常生活や練習の疲労で猫背や骨盤の歪みが生じることもあります。
バレエ整体では、骨盤や背骨の位置を整え、正しい姿勢を身につけるサポートが得られます。
姿勢が整うことで、踊りの美しさが増すだけでなく、パフォーマンスも向上します。ケガ予防
無理な動きや体の使い方が原因で、成長期の子供は捻挫や筋肉痛、疲労骨折などのリスクがあります。
バレエ整体では、体の歪みや負担を軽減することで、怪我を未然に防ぐことができます。
特に、足首や膝、股関節といったバレエで酷使する部位をケアする施術が行われます。柔軟性アップ
柔軟性はバレエの基盤ともいえる要素ですが、無理にストレッチをすると逆に筋肉を痛めることもあります。
バレエ整体では、適切な方法で筋肉や関節を柔らかくし、自然な形で柔軟性を高めることができます。
「バレエ整体に行ったら足がよく上がるようになった!」「甲が出るようになった!」という声をよく聞きます。
バレエ整体で柔軟性を高めることで、無理なく可動域が広がり、表現の幅も広がります。バレエ整体Q&A

バレエをしている人や、バレエを習うお子様をお持ちの保護者の方など、バレエ整体に興味を持っている人は多いと思います。
バレエ整体に行ってみたいと思っている方々に向けて、バレエ整体に関するよくある質問に回答していきます!子どもに合った整体院の選び方は?
子どもに適した整体院を選ぶには、まずバレエに特化した知識があるかを確認しましょう。
口コミサイトやSNSで「バレエ」「整体」と検索すると、実績のある整体院が見つかります。
また、教室の先生や周りの保護者に聞いてみるのもいいかもしれません。
成長途中の子どもの体には、正しい知識を持って施術してくれる整体院を見つけることがとても大切です。どんな人がバレエ整体に通っている?
バレエ整体に通うのは、小学生から高校生のバレエダンサー、コンクールを目指す上級者まで様々です。
特に、姿勢や体の使い方に課題を感じている子どもや、ケガのリスクを減らしたいと考える保護者に支持されています。
通っている年齢も様々ですが、整体院によっては年齢制限を設けている場合があるので、事前にHPなどで確認することをおすすめします。
また、バレエをやっている人だけでなく、ジャズダンスやチアダンス、新体操などのバレエの要素を含むダンスやスポーツをやっている人もバレエ整体を利用しています。バレエ整体はいくらかかる?
施術費は整体院によって異なりますが、大体8000円前後の整体院が多いようです。
施術時間は45分前後の整体院が多く、時間内で骨格調整やトレーニングなどを行います。
整体は原則として保険が適用されないため、接骨院などに比べて費用が高くなります。
また、症状によっても施術費が異なるため、詳しくはHPなどで確認してみてください。
費用はかかりますが、バレエに特化したケアを受けることでパフォーマンスの向上につながるので、一度は行ってみたいですよね。まとめ

いかがでしたか?
今回はバレエ整体についてお話ししました。
バレエ整体は、成長期の子どもが安全にバレエを楽しみながら技術を磨くための大切なサポートツールです。
姿勢改善やケガ予防、柔軟性アップなど、多くのメリットが期待できます。
バレエをもっと楽しめるように、バレエ整体を取り入れてみてはいかがでしょうか? -
7.222025
気軽にバレエを始めよう!美しい身体を手に入れるためのバレエエクササイズ


リモートワークが増えてきた現代。
運動不足や姿勢の崩れが気になっていませんか?
そんな方におすすめなのが「バレエエクササイズ」です。
優雅なバレエの動きを取り入れたこのエクササイズは、初心者でも簡単に始められる上、美しいスタイルや柔軟性を手に入れられると話題です。
この記事では、バレエエクササイズの魅力や具体的なやり方や習える教室をご紹介します。バレエエクササイズとは?

バレエとフィットネスを組み合わせた「バレエエクササイズ」。
バレエエクササイズとは一体どのようなものなのかご紹介します!バレエの動きを取り入れた新感覚エクササイズ
バレエエクササイズは、バレエの動きを取り入れたトレーニング方法です。
バレエのバーを使いながら、プリエなどのバレエの基本的な動きを取り入れ、体を動かしながら優雅な動作を楽しめます。
本格的なバレエの経験がなくても、誰でも手軽に始められる点が魅力です。美容と健康を同時に叶える優雅なトレーニング
バレエエクササイズでは、見た目の美しさと体の健康の両方に効果があります。
バレエでは身体の内側で骨や筋肉を支え正しい姿勢を維持するインナーマッスルが重要になります。
バレエエクササイズではこのインナーマッスルを鍛えることができ、姿勢改善やボディラインの引き締めに効果があります。
また、バレエエクササイズによって運動不足を解消することができ、健康維持にもつながります。運動が苦手でも始めやすい理由
バレエエクササイズは、基本的にハードな動きは少なく、ゆっくりとした動作が中心なので、運動に慣れていない人でも気軽に始めやすいんです。
また、自宅でも簡単にできるエクササイズも多いので、ジムなどに通わなくても手軽に続けられます。
動きを覚えながらリズムに乗るだけで、運動初心者でも楽しく続けられますよ!バレエエクササイズのメリット

初心者でも運動が苦手な人でも始めやすいバレエエクササイズ。
ではバレエエクササイズをやることで一体どのような効果があるのでしょうか?
バレエエクササイズをやるメリットをご紹介します!姿勢改善: バレリーナのような美しい姿勢を手に入れる
バレエエクササイズでは、身体の内側で骨や筋肉を支え正しい姿勢を維持するインナーマッスルを鍛えることができます。
これにより、普段の生活での猫背や前傾姿勢を改善し、スッと伸びた美しい立ち姿が身につきます。
バレエをやっている人は姿勢がいいというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか?
バレエエクササイズもバレエの要素を取り入れているため、姿勢改善が期待できます。
さらに、正しい姿勢を維持することで、肩こりや腰痛の緩和にもつながるんです!柔軟性アップ: ケガ予防にもつながる体のしなやかさ
バレエをやっている人は体が柔らかいイメージがありますよね。
バレエエクササイズでも柔軟性アップが期待できます!
エクササイズに取り入れられる動きには、柔軟性を高めるストレッチが豊富です。
これにより、日常生活での動作がスムーズになり、ケガを防ぐ効果も期待できます。
また、柔らかい体は見た目にも美しく、女性らしさを引き立ててくれます。体幹強化: お腹周りを引き締めてスタイルアップ
バレエエクササイズでインナーマッスルを鍛えることにより、姿勢改善だけでなくスタイルアップにもつながります!
バレエエクササイズでは、体幹を使う動きが多く含まれるため、自然とお腹や腰回りの筋肉が鍛えられるんです。
これにより、ウエストの引き締めや体の安定感が向上し、スタイルアップ効果が期待できます。
引き締まった体は見た目だけでなく、体力の向上にもつながりますよ。ストレス解消: 優雅な動きで心もリフレッシュ
美しい動きを意識しながら体を動かすことで、気持ちがリラックスします。
クラシック音楽やバレエ特有の静かな動きにより、心が落ち着き、日々のストレスを解消する効果も得られます。
特に忙しい日常を送る方にとっては、心と体を整える貴重な時間になるでしょう。自宅でできる簡単なバレエエクササイズ3選

バレエエクササイズは自宅で簡単にできる手軽さが魅力です!
ここでは初心者にもおすすめの簡単なエクササイズを3つご紹介します。足を伸ばして体を支える基本動作
バレエの基本「プリエ」を取り入れた動作です。
脚を肩幅に開き、膝をゆっくりと曲げ伸ばしすることで、脚の筋力と柔軟性を同時に鍛えられます。
お腹の引き上げも同時に意識できると、全身の引き締めが期待できます。
広いスペースを必要としない動きなので、手軽に取り組めます。椅子や壁を使ったサポート付き動作
椅子や壁をバーの代わりに使って行うエクササイズです。
アラベスクのような片足を伸ばす動作や、背伸びをするような動きでバランス感覚を養いながら体幹を鍛えます。
道具を使うことで、初心者でも安心して練習できます。
椅子や壁に体重をかけすぎず、自分の力で立つことを意識できるとさらに効果的ですよ!フローリングストレッチ: 床を活用した初心者向けストレッチ
床に座って行うストレッチは、全身の柔軟性を高めるのに最適です。
足を伸ばして前屈をしたり、体をひねる動きを取り入れることで、固まった筋肉をほぐしやすくなります。
簡単な動きから始めることで、無理なく柔軟性を向上させられます。
慣れてきたら、ストレッチバンドなどを用いて負荷をかけてみるのもおすすめです。続けやすくするコツ

自宅で手軽に取り組めるバレエエクササイズですが、手軽にできる分続けるのは大変ですよね…。
しかしバレエエクササイズにおいて継続はとても大切です!
そこで楽しく続けるためのコツをご紹介します!音楽をかけてリラックス
バレエエクササイズを行うときは、お気に入りの曲を流してテンションを上げましょう!
好きなクラシック音楽や穏やかなピアノ曲を流しながら行うと、モチベーションが上がりますし、気分もリラックスしやすくなります。
音楽のリズムに合わせることで、動きが自然とスムーズになり、エクササイズの時間が楽しめますよ。朝や夜の5分間で習慣化
忙しい人でも、朝起きた後や寝る前の5分間を利用するだけで続けやすくなります。
短時間でも、継続することで体の変化を感じられるようになります。
特に、時間帯を固定することで習慣化しやすくなりますよ!
朝起きてすぐや、お風呂上り・寝る前など、時間を決めて取り組んでみましょう。SNSやアプリで進捗を共有
エクササイズの成果や日々の取り組みをSNSでシェアすることで、モチベーションが維持しやすくなります。
SNSに抵抗がある人は、自身の日記などに記録するのもおすすめです。
また、バレエエクササイズに限らず、運動を継続したいときはフィットネス専用のアプリを活用するのがおすすめです!
アプリに進捗を記録することで、自分の進歩を可視化でき、やる気が持続します。バレエエクササイズを習える教室3選

バレエエクササイズは自宅でも簡単に取り組めますが、レッスンを開講しているスクールもあります。
いきなり一人で始めるのは不安…という方は、スクールに通って仲間とともに取り組むのはいかがでしょうか?
ここではバレエエクササイズのレッスンを開講しているスクールを3つご紹介します!CARDIO BARRE(カーディオバー)
CARDIO BARREは、国内でトップクラスのバレエエクササイズスタジオです。
L.A.発祥のカーディオ・バープログラムを日本人により効果的な内容へとブラッシュアップし、バレエをベースに様々な動きを組み合わせ、音楽と融合させたユニークなプログラムを体感できます。
レベルにあったさまざまなクラスを提供しているので、初めての方でも通いやすいスタジオです。スケジュール お問い合わせください 対象年齢 18歳〜 料金 月謝:
自由が丘店・広尾店:
フルタイム会員 18,700円
平日会員 14,300円
マスターフルタイム会員 24,200円横浜店:
フルタイム会員 16,500円
マンスリー4 13,200円アクセス 自由が丘店:東京都目黒区自由が丘2-10-4
ミルシェ自由が丘5階
東急大井町線・東急東横線「自由が丘駅」正面口より徒歩1分
広尾店:東京都渋谷区広尾5丁目4-12 1階
広尾駅天現寺橋方面改札2番出口より徒歩すぐ
横浜店:神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1
ららぽーと横浜2階
JR横浜線「鴨居」駅より徒歩7分バレエフィットネス
バレエフィットネスは、日本とフランスを拠点に、バレエ筋肉を鍛えるバレエフィットネスを発信しているスタジオです。
目白駅から徒歩3分とアクセスもよく、通いやすさが特徴です。
なりたい身体やその日の体調など、ご自身の目的に合わせて好きなレッスンを選べる、バレリーナ筋肉をつくり上げる“セミオーダー”のレッスンを提供しています。スケジュール お問い合わせください 対象年齢 大人 料金 入会金:11,000円
登録料:3,000円
月謝:
デイプラン(平日17時迄):15,000円
通い放題:18,000円
通い放題+バレエ放題:20,000円
月/2レッスン:7,000円
月/4レッスン:12,000円
1チケット:4,000円アクセス 東京都豊島区目白3-17-24 目白I-Nビル3階
「目白」駅より徒歩3分NOAバレエスクール
NOAバレエスクールは、 さまざまなレベルのバレエが自由に受けられるオープンクラスのバレエ教室です。
東京都内に10のスタジオを構え、どのスタジオも駅から徒歩数分とアクセスが良いです。
女性専用のスタジオもあるので、安心して通うことができます。スケジュール スタジオ毎に異なります。
詳しくはHP(https://www.noaballet.jp/schedule/)をご確認ください。対象年齢 3歳〜 料金 入会金:11,000円
月謝:
月2回コース 5,390円
月4回コース 8,250円
月6回コース 12,100円
月8回コース 15,950円
月12回コース 19,800円
月16回コース 21,450円
月20回コース 26,400円
月24回コース 31,350円
月28回コース 36,300円
月32回コース 41,250円
月36回コース 46,250円アクセス 店舗により異なります。
詳しくはHP(https://www.noaballet.jp/store/)をご確認ください。まとめ

バレエエクササイズは、自宅で簡単に始められる運動方法として人気です。
美しい姿勢や柔軟性を手に入れるだけでなく、心のリフレッシュにもつながります。
まずは気軽にトライして、あなたの日常に優雅なひとときをプラスしてみてください! -
7.222025
バレエと音楽の魅力とは?名曲が生み出す感動の世界


バレエに欠かせないもの、それは音楽です。
バレエは子どもに人気の習い事のひとつですが、子どもたちがバレエを学ぶ中で、音楽は大きな役割を果たします。
音楽に合わせて体を動かすことで、リズム感や表現力を自然に養うことができます。
この記事では、バレエと音楽の関係性や、バレエで使用される名曲をご紹介します!バレエにおける音楽の役割とは?

普段、バレエと音楽の関係性について意識しながら、バレエを踊ったり見たりしている人は少ないでしょう。
しかしバレエと音楽は切っても切れない関係にあります。
ここではまずバレエにおける音楽の役割についてご紹介します。音楽でストーリーを伝えている
バレエの魅力のひとつは、ダンサーがセリフを使わずに物語を伝えることです。
その背後で物語を支えるのが音楽です。
例えば、物語の悲しみや喜びを伝えるシーンでは、音楽がその感情を際立たせます。
音楽が奏でるメロディーによって、観客はダンサーの動きだけでは感じ取れない物語の奥深さに引き込まれます。音楽でキャラクターや舞台の雰囲気を表現している
バレエ作品では、キャラクターごとに異なるテーマ曲が使われることがよくあります。
例えば、『白鳥の湖』では白鳥オデットの優美さを表現する穏やかな音楽が流れる一方で、黒鳥オディールのシーンでは力強い曲が選ばれています。
また、舞台が森や宮殿など異なる場所に変わると、それを音楽で表現して観客に世界観を伝えています。バレエの動きと音楽の調和
音楽とバレエの動きが一体となることで、美しい舞台が完成します。
音楽のテンポやリズムと一体した踊りで観客にストーリーを伝えます。
緩やかなワルツの音楽には優雅な動きが、速いテンポの音楽にはエネルギッシュな動きが組み合わされるなど、音楽とダンスは常に互いを引き立て合っています。
また、足を上げるタイミングやジャンプをするタイミングで楽器の音が鳴ったり、踊りが激しくなるにつれて音楽が盛り上がったりなど、踊りと音楽の調和はとても大切です。バレエでよく使われるクラシック音楽の名曲

バレエで使われる音楽は、バレエを知らない人には馴染みがないと思いがちです。
しかし、バレエ音楽は実はバレエの公演だけでなくいろいろなところで使われており、実は耳にしたことがある人が多いんです!
そこで、ここでは有名なバレエ音楽をご紹介します。『白鳥の湖』
チャイコフスキーの代表作『白鳥の湖』は、バレエ音楽の中でも特に有名です。
美しい湖畔の情景を描いた「情景」のメロディーは、一度聴くと忘れられない魅力があります。
『白鳥の湖』の中で特に有名なのが「情景」です。
第2幕の冒頭で演奏される「情景」は、暗い曲調で、『白鳥の湖』のその後のストーリー展開を表しているかのような曲です。
「小さな白鳥たちの踊り(4羽の白鳥の踊り)」も聞いたことがある人が多いのではないでしょうか。
軽快なリズムに合わせて4人のダンサーが休みなく動き続けるこの場面はとても印象的です。『くるみ割り人形』
クリスマスシーズンに人気の『くるみ割り人形』は、子どもたちが楽しめる明るい曲が多いのが特徴です。
『白鳥の湖』と同じくチャイコフスキーが作曲しています。
「花のワルツ」や「金平糖の精の踊り」などは、耳馴染みのある名曲ばかりです。
日本で特に有名なのは「葦笛の踊り」ではないでしょうか?
白い犬の携帯会社のCMでおなじみのあの曲です^^『眠れる森の美女』
同じくチャイコフスキーの名作『眠れる森の美女』は、優雅で壮大な音楽が特徴です。
特に「ワルツ」はバレエの象徴とも言える美しい曲です。
ディズニー作品にもなっている『眠れる森の美女』は、バレエで使われている曲がディズニー映画の中でも使われているので、耳なじみのある曲も多くあります。
例えば「ワルツ」はディズニー作品としては「いつか夢で(原題:Once Upon a Dream)」という曲名で広く知られています。音楽とダンスの相互作用

バレエに限らず、ダンスには音楽が欠かせません。
音楽があることによってダンスの表現が広がります。
では音楽とダンスにはどんな相互作用があるのでしょうか?バレエの振付と音楽にはどんな関係がある?
バレエの振付は音楽と密接に結びついています。
作曲家はダンサーの動きを意識して曲を作り、振付家はその音楽に合った動きを考えます。
また、バレエにはセリフがないため、踊りと音楽によって観客にストーリーを伝えなければなりません。
そのため、ストーリーに合った踊り・音楽を作る必要があります。音楽に合わせて表現力を高めよう!
バレエを学ぶ子どもたちにとって、音楽に耳を傾けて感情を込めて踊ることは、表現力を高めるための良い練習になります。
曲の雰囲気を感じ取り、自分なりの物語を想像しながら踊ると、より深い表現が可能になります。
バリエーションを踊るときだけでなく、バーレッスンのときから音楽に合わせて踊ることを意識できると、自然と表現力がアップします。音楽から踊りのヒントを得よう!
音楽には踊りのインスピレーションが詰まっています。
曲の流れやアクセントに注目すると、自然と新しい動きやアイデアが生まれることがあります。
バリエーションを踊るときなどは、繰り返し曲を聴くと表現のヒントを得られるかもしれません。
音楽を深く理解することで、ダンスもより魅力的なものになるでしょう。まとめ

いかがでしたか?
今回はバレエと音楽の関係についてお話ししました。
バレエにおいて音楽は、ただの背景ではなく、ストーリーや感情を伝える大切な要素です。
音楽に耳を傾け、その魅力を感じながら踊ることで、バレエはさらに楽しくなります。
これを機に、ぜひバレエ音楽にも注目してみてください! -
7.222025
バレエを通じて楽しく英語!小さいお子様にピッタリなバレエ英語レッスンの魅力とは?


お子様に英語を楽しく学ばせたい、でも座って勉強するのはまだ難しい…。
そんな親御さんにピッタリなのが、バレエを通じて英語を学ぶレッスンです!
踊りながら自然と英語を身につけることで、運動習慣も同時に得られます。
バレエ英語レッスンは、体を動かしながら感性や表現力を育み、英語力まで高める一石三鳥の習い事です。
今回は、そんな魅力的なレッスンのポイントを詳しくご紹介します。幼児・小学生に人気の習い事って?

ある調査では、小学生の7割以上が習い事をしているそうです。
また、習い事をしている小学生の半数以上が複数の習い事をしているそうなんです。
ではどんな習い事が人気なのでしょうか?スポーツ系や学習系が人気!
下記はベネッセが調査した小学生がしている習い事ランキングです。(https://benesse.jp/kosodate/202403/20240329-1.html)
- 1位 水泳
- 2位 英会話などの語学
- 3位 学校の予習・復習
- 4位 ピアノ・電子オルガン
- 5位 習字
- 6位 サッカー・フットサル
- 7位 計算・漢字
- 7位 受験のための学習
- 7位 ダンス
- 10位 体操・リトミック
TOP10 の中にスポーツ系の習い事は4つもランクインしていますね!
また英会話をはじめとする学習系の習い事も多くランクインしています。
昨今はスポーツ系の習い事や学習系の習い事が人気なことがわかります。英語でスポーツを習えるって本当?
近年は、体力づくりや協調性を育てることができるスポーツ、そして将来のために役立つ英語を早期から身につけたいと考える親御さんが多いようです。
特に幼少期からの英語学習に関心を持つ方が増えており、遊びながら学べる「英語×スポーツ」の組み合わせが注目されています。
「英語でスポーツ」は最近の習い事として徐々に増えてきた新しいジャンルです。
バレエやサッカー、ダンスなどを通して、英語に自然と触れながら体を動かすことで、より深く英語を身につけることが可能です。
言葉を学ぶだけでなく、スポーツの指示や基本動作も理解する必要があるため、自然に英語力が育まれるのが魅力です。英語×スポーツの習い事の特徴
「英語×スポーツ」の習い事では、指導者が英語を使って指示や説明を行います。
お子様は英語のフレーズを通じて体の動きを覚えるため、単語や表現を体感しながら学習できます。
さらに、楽しみながら学べるので、お子様にとっても抵抗なく英語と触れ合う環境が整っています。バレエ英語レッスンって?

最近注目を集めている「英語×スポーツ」の習い事ですが、実はバレエも英語で習うことができるんです!
ここではバレエ英語レッスンがどのようなものかご紹介します。英語とバレエの融合
バレエ英語レッスンは、バレエの基礎動作を学びながら、英語も自然に取り入れていくプログラムです。
指導者が英語を使ってポーズやステップを教えるため、バレエの動きと一緒に英語の基本表現も学べます。
例えば、ストレッチやターンなどの動作を「ストレッチ」「ターン」と英語で言われることで、無理なく英単語に親しめるのです。教室によって教え方が違う?
バレエ英語レッスンといっても、教室によって内容はさまざまです。
ある教室ではネイティブ講師が英語で指導する場合もあれば、日本人講師が英語と日本語を併用してレッスンを行う場合もあります。
お子様にとっての英語習得の目的や、英語力のレベルに合わせて、無理なく学べる教室を選ぶことが大切です。小さい子供でも安心!年齢に合わせたプログラム
バレエ英語レッスンは、お子様の年齢に応じてプログラムを調整する教室がほとんどです。
幼児向けのクラスでは、優しく楽しい雰囲気でレッスンが進められ、年齢が上がると少しずつ難しい表現や動きが加わります。
これにより、初めてのバレエや英語でも安心して始めることができ、無理なくレベルアップが可能です。英語でバレエを習うメリット3選

バレエのレッスンを英語で受けることでどんなメリットがあるのでしょうか?
ここでは3つ厳選してご紹介します!英語力アップと運動習慣を同時に獲得
バレエ英語レッスンの最大のメリットは、英語力と運動習慣を同時に得られることです。
特に幼少期に体を動かしながら学ぶことで、語学とスポーツの基礎を効率よく吸収できます。
バレエを通じて自然に英語のフレーズやリズムが身につくため、勉強とは違った形での「実用的な英語」が学べます。集中力と自己表現力の向上
バレエは身体の柔軟性だけでなく、音楽や動きを通じた自己表現力も鍛えられる習い事です。
英語を使って踊ることで、自分の気持ちや意思を言葉と体で表現する力が養われます。
また、英語でレッスンが行われることによりレッスン中の指示に集中する習慣がつくため、集中力も自然と身についていくのが魅力です。グローバルな感覚を育てる
バレエ英語レッスンは、お子様にグローバルな感覚を育てる良い機会でもあります。
幼少期から英語に触れることで、外国語への抵抗が減り、異文化にも関心を持ちやすくなります。
将来、さまざまな国の方々とコミュニケーションを取ることができる土台を築くことができるでしょう。
また、バレエを長く続けると、バレエ留学を考えるお子さまもいるので、そんなときにはレッスンで身についた語学力やグローバルな感覚がきっと役に立つと思いますよ。英語ができなくても習える?バレエ英語レッスンに関するお悩みを解消!

語学とバレエを同時に習えるのはとても魅力的ですよね!
しかし英語もバレエも習ったことがないと、子どもも保護者も不安ですよね。
ここではバレエ英語レッスンに関するお悩みを一緒に解消していきましょう!英語がわからなくても大丈夫?
バレエ英語レッスンでは、英語が初めてのお子様でも安心して参加できるように、講師が丁寧にサポートしてくれます。
多くの教室では、日本語も交えながら少しずつ英語の指示に慣れていけるよう工夫されています。
ネイティブ講師がすべて英語でレッスンをする教室でも、ジェスチャーや周りの子どもの様子で子どもは自然とわかるようになってくるものですよ。
全ての動きが一度で理解できなくても、繰り返しレッスンを受けることで徐々に慣れていくことが可能です。何歳から習える?
対象年齢は教室によって異なりますが、3歳から習える教室が多いようです。
教室のHPなどで確認してみましょう。
バレエ英語レッスンは、幼児から小学生まで幅広い年齢層のお子様が対象となっています。
特に幼児向けのレッスンでは、簡単な英語の指示を中心に、楽しみながらリズムや表現を学べる内容になっています。
お子様の年齢や性格に応じたプログラムが提供されているため、安心して始めることができます。レッスンについていけるか不安
レッスンについていけるかどうか不安な場合は、まず体験レッスンに参加するのがおすすめです。
体験レッスンでは、お子様が英語やバレエにどの程度興味を持つか、また教室の雰囲気が合っているかを確認できます。
また、レッスンの内容やレベルがお子さまに合っているかどうかも確認しましょう。
一度体験してみることで、保護者もお子さまも安心して本格的に始められるでしょう。まとめ

バレエ英語レッスンは、英語力の向上や運動習慣の確立、さらには自己表現力や集中力も育むことができる、非常に魅力的な習い事です。
幼少期から英語と触れ合うことで、将来の国際的なコミュニケーション能力も磨かれます。
まずは体験レッスンを通じて、お子様に合ったバレエ英語教室を探してみてはいかがでしょうか?
きっとお子様にとって、新しい学びと楽しさを発見できる機会となるでしょう! -
7.182025
リノリウムってなに!?お稽古場や舞台の床について知ろう!!


突然ですが、バレエのお稽古場の床がどんな素材で出来ているか知っていますか?
床の種類には2種類あり、それぞれのメリット・デメリットがあります。
またバレエをしていると耳にすることが多い「リノリウム」ですが、一体どのようなものを指すのでしょうか。
今回はバレエのお稽古場の床の種類やリノリウムについて詳しく紹介していきます。
バレエ教室の床やバレエ舞台の床について気になる方は参考にしてみてくださいね!
お稽古場の床はどんな素材でできている?リノリウム床の場合

お稽古場の床がどんな素材か気にしたことはありますか?
床の種類は2種類あり、そのうちの1つがリノリウム床です。
「リノリウム」は普段あまり聞かない言葉ですが、どのような床なのでしょうか。
リノリウム床についてや、メリット・デメリットについても紹介します。
リノリウム床とは
リノリウムは、1860年代にイギリス人のフレデリック・ウォルトン (Frederick Walton) によって発明され、100年以上の歴史をもつ素材です。
見た目がビニールのようで、名称もカタカナであることから、化学物質で作られたものに思われやすいですが、実は原料のほとんどが天然素材。
亜麻と呼ばれる植物の種から取れる亜麻仁油、松ヤニ(ロジン)などの樹脂類、コルク粉、顔料などを混ぜて、シート状やタイル状にしたものを指します。
リノリウムは適度な弾力性があり滑りにくい素材として、バレエでも使われるようになりました。
リノリウム床のメリット
リノリウム床のメリットはなんといっても「滑りにくい」ことと適度な「弾力性」があること。
リノリウムがバレエの床として使用される前は、※松ヤニを床に散りばめて滑りにくくしていました。
松ヤニは滑り止めの効果が高いですが、同時にバレエシューズが汚れてしまうという点も。
リノリウム床の場合は、松ヤニを使用しなくても滑ることなく安全に踊ることのできる床素材です。
※松ヤニ・・・バレエでは、松ヤニを滑り止めとしてトゥシューズのつま先やソールに吹きかけたり、砕いてシューズの裏に付けたりして使用します。
松ヤニは粉状になるとグリップ力が高く、床上の滑りを軽減して踊りやすくしてくれる役割があります。
リノリウム床のデメリット
「滑りにくい」ことが最大の利点であるリノリウムですが、ワックスや松ヤニといったものが付着すると逆に滑りやすくなってしまうという特性も。
また、紫外線に当たると変色の可能性もあります。
主原料が亜麻仁油であるため特有のニオイが気になるという場合もあります。
施工直後は亜麻仁油特有のニオイが出てしまいますが、時間が経つにつれて薄れてきます。
リノリウム床に適したバレエシューズ
リノリウム素材の床は滑りにくいので、バレエシューズは滑りやすい材質がおすすめです。
具体的にはレザー生地を使用していない、キャンバス地のバレエシューズがリノリウム床との相性が良いのでおすすめです。
お稽古場の床はどんな素材でできている?木材床の場合

バレエのお稽古場の床の種類は2種類あり、1つは前述のリノリウム床で、もう1つは木材床です。
木材床の特徴や、メリット・デメリットについて紹介します。
木材床とは
木材床に適しているさ材は桜材です。
桜材は傷がつきにくいという特徴があり、リノリウム床にはひんやり感がありますが、木材床は暖かみも感じることが出来ます。
その暖かみが好きで桜材を起用しているお教室も多くいらっしゃいます。
木材床のメリット
木材床のメリットは暖かさの他にも、湿度調整できること。
また、ダンサーにとって重要なメリットは衝撃を吸収するため足への負担が少ないということです。
衝撃を吸収するので床を木材にしているお教室もあるでしょう。
木材床のデメリット
木材のデメリットはリノリウムに比べて、かなり滑りやすいところです。
そのため、松ヤニを付けて滑りにくくするものの、スタジオによっては松ヤニの使用を禁止しているところも・・。
松ヤニが使えない場合は、濡れ雑巾で対応するのですが、濡れ雑巾はバレエシューズには使用できますが、トゥシューズとの相性がよくありません。
トゥシューズは糊をたくさん使用し作られているので、水分に弱いという特徴があります。
バレエショップなどでは松ヤニ以外にも、滑りにくくするグッズが売られていますで木材床で滑るという方はチェックしてみましょう!!
木材床に適したバレエシューズ
木材床は前述の通り、滑りやすいのでリノリウム床とは逆にシューズは滑りにくい材質を選ぶ必要があります。
キャンバス地を使用しないオールレザー地が滑りにくくおすすめです。
舞台の床にも使用されているリノリウムについて詳しく知ろう

実はリノリウムはバレエの舞台でも使用されていることが多いんです!
中には、お教室や舞台でリノリウムを毎回、自分たちでひいているというところもあります。
バレエの舞台でリノリウムが使用されている理由や、リノリウムをお手伝いがあるかもしれないので、ひきかたを紹介していきます。
バレエの舞台でリノリウムが使用されている理由
実はバレエの舞台ではリノリウムが床材として使用されていることが多いです。
その理由は下記の通りです。
- ・滑りにくい
リノリウムのメリットでもある滑るにくさがやはり、バレエの舞台で使用される一番の理由です。
松ヤニは何回も使用すると層になって滑りやすくなることもあります。
そのため、松ヤニなしで滑りにくいというのはバレエに適していると言えますね。 - ・摩擦や衝撃に耐えられる
リノリウムは踊りの際に生じる衝撃や摩擦に強く耐えることができます。 - ・メンテナンスがしやすい
リノリウムは汚れが拭き取りやすいことから、日常的なメンテナンスも簡単です。
上記の理由からバレエをはじめとする、イベントやダンスステージでもリノリウムを使用している舞台が多いようです。
リノリウムの敷き方
お稽古場や舞台では、元々の床の上にリノリウムを敷く場合があります。
舞台の場合はリノリウムを敷くのは業者さんがやってくれる場合も多いですが、お稽古場の場合は先生や生徒、保護者で敷く場合もあります。
もしかしたらバレエをやっているとリノリウムを敷く機会があるかもしれないので敷きかたを紹介します。
リノリウムの敷きかた①
リノリウムは数個に分けて筒状に丸めて収納されていることが多いです。
筒状のリノリウムを運んで、並べていきます。リノリウムの敷きかた②
大体の場所が決まったら、筒状のリノリウムを転がして広げていきます。リノリウムの敷きかた③
リノリウムとリノリウムの隙間を埋めます。
この際、重なり合わないように注意します。
また、弛んでいる部分がないかチェックしましょう。※重なった部分があると、つまずきの原因となってしまいます。
リノリウムの敷きかた④
リノリウム同士の隙間が埋まったら、養生テープでとめていきます。
この際に2人1組で作業すると、やりやすいです。
(1人がテープを抑える、もう1人がテープを伸ばす)まとめ

リノリウムは「リノ」とも呼ばれバレエをしている人の中では親しまれています。
木材とリノリウムのどちらもメリット・デメリットがありますし、好みも分かれるところです。
ただ、バレエの舞台でリノリウムが使用されていることも多いので、リノリウム床だと本番に近い状態で踊れることも大きな利点かもしれませんね。
一度、お稽古場の床について考えてみてくださいね。
- ・滑りにくい
-
7.182025
国内トップレベル!?国際バレエコンクール【ジャパングランプリ】を徹底解説!!


年々レベルが上がってきていると注目されている、バレエのコンクールの1つであるジャパングランプリ。
小学3年生から出場できることもあり、バレエを習っていると興味があるという方も多いでしょう。
今回はジャパングランプリについて部門や参加規定など詳しく解説していきます。
コンクールでヴァリエーションを踊ってみたいという方はチェックしてみてくださいね!!
レベルが高い!?ジャパングランプリってどんなコンクール?

「毎年レベルが上がっている」と注目度の高いジャパングランプリ。
まずはジャパングランプリについて、参加規定や審査方法などを紹介します!
ジャパングランプリとは
ジャパングランプリの正式名称は『国際バレエコンクール・ジャパングランプリ』です。
日本の若きバレエダンサー達によりよい教育の機会とチャンスを与え、優れた才能の発掘をめざし、指導者、生徒の交流の場となる事を目的に開催されてます。
ジャパングランプリは海外の一流バレエ団・スクールから審査員を招いて行われる国内では唯一のコンクールで、毎年多くの受賞者がカンパニー・アパレンティス資格やスカラシップ等を得て世界に羽ばたいています。
ジャパングランプリ参加規定について
ジャパングランプリに参加するためには、参加規定を満たしている必要があります。
下記に、ジャパングランプリの参加規定について紹介します。
参加の際の参考にしてみてくださいね!
※ジャパングランプリ公式HP、下記URLより参照
資格
過去及び現在において、アマチュアに限る。
プロ活動に従事する者の参加は認められない。ただし、シニア部門はプロも認める。
課題曲児童
以下のVaを除く、クラシックバレエからのヴァリエーション
バランシン作品からのVa /黒鳥のVa
グランパクラシックVa/エスメラルダ(タンバリン)のVa
ジュニアB/ジュニアA/シニア
バランシン作品からのVaを除く、クラシックバレエからのヴァリエーション
内容クラシック部門の児童及びジュニアB部門は1曲。
ジュニアA・シニア部門 は予選1曲、決選1曲の異なる2曲を用意する。
制限時間
クラシック:3分以内
コンテンポラリー:2分30秒以内(無音も含め踊り出しから)
※共に、超過の場合は減点の対象となります。
音楽音楽はCDに出場番号・参加者氏名・曲名を記入し、参加者1名/1曲につき 1枚用意する。
音出し等の合図は、指導者の方が音響オペレーターの脇にて行ってください。
上記の出場規定に違反があった場合は失格となってしまいますので、十分に注意しましょう。
ジャパングランプリ審査方法
コンクールの審査方法が気になる方も多いでしょう。
ジャパングランプリの審査では下記の3つの重要なカテゴリーにより採点し順位を決定しているようです。
・技術
・音楽性
・将来性バレエはスポーツのように、それぞれの技に得点が決まっているわけではありません。
そのため、テクニックだけでなくヴァリエーションをどのように表現しているかも重要となります。
上記のことと、それらを意識して踊るようにしましょう。
※順位審査は舞台審査にて行われ、スカラシップ賞等はオンライン審査でも行われます。
どんな部門がある?ジャパングランプリについて詳しく知ろう

ジャパングランプリはクラシック部門とコンテンポラリー部門に分かれており、それぞれの部門はさらに細かく部門分けされています。
それぞれの部門についてみていきましょう!
クラシック部門について
ジャパングランプリのクラシック部門では女性と男性に分かれており、それぞれ対象年齢も異なります。
クラシック部門について詳しくみていきましょう!!
女性部門
クラシック部門の女性部門は下記のように分類分けされています。
・児童Ⅰ:小学3年生~4年生
・児童Ⅱ:小学5年生~6年生
・ジュニアBⅠ:中学1年生~2年生
・ジュニアBⅡ:中学3年生
・ジュニアA:高校生
・シニア:高校卒業〜23歳児童Ⅰ部門ではバレエシューズ、児童Ⅱ部門はバレエシューズでの出場が可能となっています。
つまり小学校3年生からバレエシューズでヴァリエーションを踊り、コンクールに出場できるということですね。
男性部門
クラシック部門の男性部門は下記のように分類分けされています。
・ジュニア:10~14歳
・ジュニア:15歳~高校生
・シニア:高校卒業〜23歳日本で10歳といえば小学校4年生5年生ですね。
女性部門よりも少し遅いですが最速では10歳からジュニアの部で出場可能です。
コンテンポラリー部門について
ジャパングランプリのコンテンポラリー部門は児童Ⅱやジュニアといった分類分けをされています。
それぞれの部門を詳しくみていきましょう!!
児童Ⅱ
コンテンポラリー部門の児童Ⅱでは小学5年生〜6年生の男性と女性が対象となっています。
ジュニアB / ジュニアA &シニア
コンテンポラリー部門のジュニアBは中学生の男女、ジュニアA&シニアでは高校生から23歳までの男女が対象となっています。
どんなヴァリエーションが踊られている!?2024年の審査結果をチェック

ジャパングランプリではどのようなヴァリエーションが踊られ、上位に入賞したのかが気になるという方も多いでしょう。
2024年のクラシック女性部門の児童Ⅰ(小学3年生~4年生)と児童Ⅱ(小学5年生~6年生)の審査結果を紹介します。
また、ジャパングランプリで得られるスカラシップや2025年の開催情報についても紹介していきます!!
2024年審査結果/児童Ⅰ部門(小学3年生~4年生)
ジャパングランプリのクラシック部門、児童Ⅰの審査結果と踊られたヴァリエーションは下記の通りです。
順位
1 田中 真結さん(BALLET・LE・COEUR) パキータ 第5
2-1 草信 杏莉さん(Ballet Sutudio Miyu) ライモンダ 1幕 夢の場
2-2 小野 茜さん(松浦かがりバレエアカデミー) コッペリア 1幕 スワニルダのVa
3-1 篠原 心海さん(キッズバレエプチリーナ) アレルキナーダ
3-2 大谷 海夏さん(AristoBALLETSTUDIO) パリの炎 女性ヴァリエーション
3-2 関本 千遥さん(Ballet Studio Prime) アレルキナーダ児童Ⅰの部門では『パキータ』や『アルキナーダ』が人気のヴァリエーションのようです!!
2024年審査結果/児童Ⅱ部門(小学5年生~6年生)
ジャパングランプリのクラシック部門、児童Ⅱの審査結果と踊られたヴァリエーションは下記の通りです。
順位
1 河合 摩乃さん(バレエスタジオ RISE) 眠れる森の美女 2幕 オーロラのVa
2-1 中口 心綸さん(Ito Tomoko Ballet Studio) ラ・フィーユ・マル・ガルデ 1幕 リーズ
2-2 小水石 雪葉さん(HAGAバレエアカデミー) ヴェニスのカーニバル
3-1 佐野 桃音さん(MOMOバレエスタジオ) タリスマン
3-2 二俣 アンノさん(AGRÂCE BALLET SCHOOL) パキータ 第5
3-2 五十嵐 伯逢さん(BALLET・LE・COEUR) ライモンダ ピチカートジャパングランプリのクラシック部門、児童Ⅱの部門では『タリスマン』や『 ヴェニスのカーニバル』といった珍しいヴァリエーションもたくさん踊られています。
また、上位には入っていませんが『パキータ』は児童Ⅰ部門と同様に人気の高いヴァリエーションのようです。
※その他の審査結果については下記のURLよりご確認ください。
https://www.jjgp.jp/result/2024/
スカラシップについて
ジャパングランプリのスカラシップはアメリカのバレエ学校が充実していることでも知られています。
英語圏以外ではベルギーやドイツといったヨーロッパのバレエ学校も。
海外でレッスンを受けてみたいという方はチェックしてみてくださいね!!
ジャパングランプリのスカラシップ先は下記の通りです。
エイリー・スクール(アメリカ)/ボストン・バレエ・スクール/ベルギー王立アントワープ・バレエ・スクール(ベルギー)
ベルリン国立バレエ学校(ドイツ)/カナダ・ナショナル・バレエ・スクール(カナダ)/カナダ・ロイヤル・ウィニペグ・バレエ(カナダ)
ドルトムント・バレエ(ドイツ)/ハリッド・コンサルバトリー(アメリカ)/ハンブルグ・バレエ(ドイツ)
ジョン・クランコ・バレエ・スクール(ドイツ)/国立バレエ・アカデミー・ミュンヘン(ドイツ)/オランダ国立バレエ・アカデミー(オランダ)
ニュージーランド・スクール・オブ・ダンス(ニュージーランド)/ノジャ-ネビュラ・ステージ・エデュケーション(オーストリア)
ピッツバーグ・バレエ・シアター・スクール(アメリカ)/ラドフォード大学バレエ・ユース(アメリカ)/サンフランシスコ・バレエ・スクール(アメリカ)
スカラ座(イタリア)/シンガポール・ダンス・シアター(シンガポール) 等
2025年の開催について
2025年のジャパングランプリは下記の通り、開催が予定されています。
開催日:2025年8月4日(月)〜8日(金)
会場 :彩の国さいたま芸術劇場
2025年も例年通り8月に開催が予定されているようです。
出場してみたい方は、上記の日程を参考に準備してみてくださいね!!
まとめ

クラシック部門では女の子は小学校3年生から出場することができるジャパングランプリ。
バレエシューズでヴァリエーションを踊ることもできるので、「ヴァリエーションを踊ってみたい」、「コンクールを目標にしている」とういう方にぴったりのコンクールです。
目標に向けて頑張ることは、とても良いことですね!!
ジャパングランプリに興味がある方は出場を検討してみてくださいね!
-
7.182025
バレエのティアラは作れる!?バレエティアラを作ってみよう!!


つけると上品に華やかな印象になるティアラ。
バレエの役柄でも多く着用されており、ティアラにこだわりがある方も多いです。
実はバレエのティアラは手作りすることができ、ティアラ作り教室といったプロに作り方を学ぶこともできるんです。
今回はバレエティアラについて、材料や作り方動画、ティアラ作り教室について紹介します!
バレエティアラを作ってみたいという方は参考にしてみてくださいね!!
まずはバレエティアラを知ろう!バレエティアラについて

付けると一気に華やかな印象になるバレエティアラ。
ティアラを付けるとテンションがアップするという方も多いでしょう。
まずは、バレエティアラの種類やティアラをつけて踊る役柄を紹介します!
バレエティアラの種類
バレエで使用するティアラには様々な形があります!
ティアラの形や種類について紹介します。
プリンセス型のティアラ
プリンセスタイプのティアラは、宝石(イミテーション含む)をたっぷり使ったものが多いです。
豪華な衣装にもシンプルな衣装にもマッチするスタンダードなティアラといえます。
そのため、どんな役柄にも着用できるスタンダードな形と言えるでしょう。
柄の部分は伸び縮みしないので、頭の大きさに合ったティアラを選ぶと良いでしょう。
一連or二連カチューシャ型のティアラ
カチューシャのように着けられるティアラはおでこの部分に前飾りがあるものとないものがあります。
おでこの部分に前飾りがあるものは、『海賊』や『くるみ割り人形』のアラビアの踊りといったオリエンタルな雰囲気を持つ役柄で着用されることが多いです。
カチューシャの形をしているので着用しやすいという特徴もあります。
クラウン型のティアラ
白鳥、黒鳥や妖精の女王などの役柄で使用されることが多いのがクラウン型です。
女王の役などになると大型のクラウンで飾りが普通のものより豪華なこともあります。
シニヨンに合わせてつけるティアラ
シニヨンに沿って、シニヨンの上部や下部に着けるタイプのティアラです。
着ける位置をシニヨンの高さによって変えることができます。
ティアラをつける役柄
バレエ作品に登場する役柄でティアラを付けるのはプリンセスや妖精といったものが多いです。
バレエティアラを付けて踊る役柄について紹介します。
プリンセス
バレエティアラを付ける役柄で代表的なのがプリンセスの役柄です。
バレエ作品に登場する主なプリンセスは下記のようなものがあります。
『眠れる森の美女』・・・オーロラ姫
『白鳥の湖』・・・オデット(白鳥)、オディール(黒鳥)
『ドン・キホーテ』・・・ドルシネア姫
『シンデレラ』・・・シンデレラ
妖精
プリンセスの他にバレエティアラを着用する役柄の多くは妖精です。
妖精が登場するバレエ作品は下記の通りです。
『くるみ割り人形』・・・※金平糖の精
『眠れる森の美女』・・・・リラの精、やさしさの精、元気の精、第1幕:鷹揚(おうよう)の精、勇気の精、のんきの精、宝石の精
『ドン・キホーテ』・・・森の女王(森の妖精たちの頂点に立つ強い存在)
『シンデレラ』・・・春夏秋冬の精
※金平糖の精・・・『くるみ割り人形』はバレエ団や上演される国によって演出が異なる演目です。
プリンシパルが金平糖の精を踊りますが、クララと金平糖の精は同一人物であるというパターンもあります。
バレエティアラに必要なものと作り方の参考動画

バレエティアラ作りに必要なものや、作り方の参考動画を紹介します!
バレエティアラをて作りしようと思っている方は参考にしてみてくださいね!
バレエティアラ作りに必要なもの
バレエティアラを作る際には、まず道具や材料を揃える必要があります。
バレエティアラに必要なものは下記の通りです。
必要な道具・・・ラジオペンチ(先細)、ニッパー、丸ペンチ
材料・・・役柄にあったカラーのビーズ、大小様々な大きさのビーズ
これらの道具や材料は、アクセサリーパーツやチェーン、金具を取り扱っている貴和製作所で購入が可能です。
また、ティアラを販売しているショップやオンラインショップなどではティアラ作りのキットを取り扱っている場合もあります。
キットは材料やレシピが揃っているので、すぐに作り始められます。
初心者向けバレエティアラ作り方参考動画
まず初めにティアラ作りにチャレンジする際はどの形から始めれば良いのでしょうか?
初心者向けバレエティアラ作り方の参考動画を紹介しますので参考にしてみてくださいね!
初心者におすすめカチューシャ型
シンプルな形で着用もしやすいカチューシャ型は、ティアラ作りを始める際の初めの一つにおすすめの形といえるでしょう。
参考動画
初心者におすすめクラウン型
見た目がクラウン(王冠)であることから仕上がりが想像しやすく、初心者にも作りやすいのがクラン型のティアラです。
参考動画
中上級者向けバレエティアラ作り方参考動画
ティアラ作りに慣れてきたら、少し作りが複雑な中上級レベルのティアラにも挑戦してみましょう!!
中上級者向けのバレエティアラ作りの参考動画を紹介しますので参考にしてみてくださいね!
中上級者におすすめのプリンセス型①
プリンセス型のティアラはスタンダードな形なので色んな役柄に着用できます。
初級より難しくなっていますが、その分仕上がれば出番も多くなるでしょう。
参考動画
中上級者におすすめのプリンセス型②
プリンセス型はスタンダードな形ですがデザインも多様です。
ビーズやラインストーンといった材料のカラーを変えることで演じる役柄にあったものを作れます。
参考動画
プロに習う!おすすめのバレエティアラ作り方教室

初めてバレエティアラを作る際はわからないことも多いですよね。
そこで、初めはプロに習うということもおすすめです。
バレエティアラの作り方を教えている教室を紹介します!
表参道ティアラ&グルーデコ教室『Vivienne blanc …Vivienne blanc
ヴィヴィエンヌブランはハンドメイドのバレエティアラ、ウェディングティアラの作り方を教えている教室です。
道具や材料を揃えてくれているので、すぐにティアラ作りを始められます。
また、バレエティアラディプロマコースという資格取得を目指したレッスンも開催されています。
体験レッスンがあるので興味がある方は参加してみてくださいね!
場所:表参道(東京)
時間:平日 11:00〜16:00土曜日 13:00〜17:00
※入室は10:55〜
所要時間:ティアラのレッスンは約3〜5時間が目安です。※制作する作品により異なります。
公式HP: https://www.vivienne-blanc.com/
ティアラlino
ティアラlinoは「バレエを頑張っている娘を応援したい」、「ママだからこそできる『お守りになるティアラ』を作って渡したい」という気持ちからできたバレエティアラ作り教室です。
場所:下総中山(千葉)
時間:月 定休日/火 11:00 – 16:00/水 11:00 – 16:00木 11:00 – 16:00/金 定休日
土・日 11:00 – 16:00
所要時間:HPに記載がないため、直接教室にお問い合わせください。
公式HP:https://fuwamoko74.amebaownd.com/まとめ

バレエティアラを手作りするのは一見難しそうですが、材料やレシピが公開されているものも多く初心者の方も挑戦できそうですね!
手作りのものを身につけて舞台に立てるとお子さまも心強いでしょう。
バレエティアラ作りに興味があり方は、ぜひ挑戦してみてくださいね!!
-
7.182025
バレエの衣装はサイズ調整できる!?ムシの作り方を徹底解説!!


バレエの衣装はバレエの舞台の必須アイテムですよね!
衣装を着て舞台に立つことに憧れている方も多いでしょう。
バレエの衣装はサイズを測り自分のサイズに合ったものを着るものですが、時にはサイズを測った時より大きかったり小さかったりすることもあります。
そういった時には〝ムシ〟を作ることでサイズ調整が可能なんです。
今回は、〝ムシ〟について、〝ムシ〟で調整できる衣装についてや実際の作り方について紹介します。
衣装のサイズ調整が必要な方は参考にしてみてくださいね!
バレエ衣装はサイズ調整が可能!〝ムシ〟ってなに?

衣装を正しい状態で着てみた際に大きかったり、小さかったりすることはよくあります。
バレエの衣装は一見、サイズの調整ができなさそうですが実は〝ムシ〟を作ることで調整が可能なんです!
バレエ衣装のサイズ調整に必須の〝ムシ〟について紹介します!!
〝ムシ〟とは
バレエの衣装はボディス部分の背中にホックとループという糸を縫いとめたものがついています。
このループ部分を〝ムシ〟と呼びます。
貸衣装の場合はもともと衣装についていることも多いですが、自分のサイズに合わないことも・・。
そういった時はムシの位置を縫い直す必要があります。
自分のサイズに合わせてムシの位置を調整することで、体のラインがキレイに見え、踊りやすくなります。
一度、サイズを調整しても本番直前に直しが必要になることもあるので、衣装を扱う場合はムシの作り方を知っておく必要があるでしょう。
〝ムシ〟でサイズ調整できる衣装
上記で紹介した〝ムシ〟はホックがあるものであれば、基本的にどの衣装でも取り付けることができます。
具体的にはチュチュや男性衣装の背中部分やパンツのウエストといったホックがある衣装には取り付けが可能です。
実際に〝ムシ〟を作ってみよう!〝ムシ〟の作り方について

実際に〝ムシ〟を作る際に必要なものや作り方を紹介します!
衣装のサイズ調整が必要な方は参考にしてみてくださいね。
〝ムシ〟作りに必要なもの
〝ムシ〟を作る際に必要なものを用意していきましょう!
ムシ作りに必要なものは下記の通りです。
- ・針
太めの糸が通りやすいものが使いやすいです。
- ・糸
決まった専用の糸はありませんが、細いよりは太い糸の方が作業がしやすいです。
また、ムシが目立たないよう衣装に似た色を使用します。
〝ムシ〟作りに適した針や衣装の色に合った糸など、すぐに手に入らない場合もあるので時間に余裕を持っての準備がおすすめです。
〝ムシ〟の作り方
材料が揃ったら実際に〝ムシ〟を作ってみましょう!!
〝ムシ〟の作り方は下記の通りです。
- 本取りした針で、生地の裏側から通して上下に針を差し込み土台を2本作ります。
- 土台になった糸の隙間に針を通したあと、残っている糸の輪に針を通し2本の土台に巻き付くように作ります。
- その作業を上まで繰り返します。
- 上まできたら、針を生地の裏側に通して玉留めします。
バレエを習っていて舞台に立つ機会が多くなると衣装のサイズ調整のため〝ムシ〟を作る機会も多くなります。
機会が多いと、ムシ作りにもすぐに慣れていきそうですね。
よりわかりやすい!〝ムシ〟作り参考動画

〝ムシ〟の作り方の参考動画はたくさんあります。
動画で見た方がわかりやすいという方は参考にしてみてくださいね!!
〝ムシ〟作り参考動画①
バレエの衣装レンタルを行なっているアトリエヨシノがわかりやすい〝ムシ〟の作り方の参考動画をあげてくれています!
〝ムシ〟作り参考動画②
バレエスタジオの「Angel R」が解説する〝ムシ〟の作り方の参考動画。
よりわかりやすく簡単に〝ムシ〟を作る方法を解説しています。
〝ムシ〟作り参考動画③
バレエ衣装作家の藤平由紀さんが解説する〝ムシ〟の作り方の参考動画です。
〝ムシ〟についてだけでなく糸通しのコツや玉結びの仕方なども詳しく解説してくれています。
素早く作れる!〝ムシ〟作りのお助けグッズ!

慣れれば簡単な〝ムシ〟作りですが、急いでいる場合や慣れていない時は作るのに時間がかかってしまうことも・・。
そういった場合に、〝ムシ〟作りが簡単にできるお助けグッズも。
〝ムシ〟作りが簡単にできるお助けグッズについて紹介します!!
〝ムシ〟作りに役立つグッズ
〝ムシ〟は基本的に針と糸があれば作ることができますが、最近は〝ムシ〟を作るためのお助けグッズもあります。
お助けグッズを使用して〝ムシ〟を作ることでより、簡単に強度の高い〝ムシ〟を作ることができますよ。
「ムシ作り革命」について
「ムシ作り革命」は〝ムシ〟サイズの小さいプラスチックのプレートです。
このプレートを衣装に置いて糸を縫い留めることで〝ムシ〟のサイズを一定の大きさで早く作ることができます。
また、早く作ることができるだけでなく「ムシ作り革命」を使用しない〝ムシ〟に比べて約1.5倍の強度があり激しい動きにも耐えられる造りとなっています。
カラー展開:透明タイプと濃い衣装用のダークグレータイプ
お値段:12個入り750円 90個入り4,800円 180個入7,900円
Amazon.co.jp: (12個入り, 透明クリア) ルーポン ムシ作り革命 Loopon バレエ 衣裳 衣装 のムシ/ループ 衣類用 雌ホック 前カン マエカン 鍵ホック カギホック
まとめ

バレエ衣装のサイズ調整は頻繁に起こります。
本番当日にも〝ムシ〟を作って調整することもあり得ますので、〝ムシ〟作りに必要な針や衣装の色に合った糸は常備しておくと良いでしょう。
初めは、時間がかかったり難しい〝ムシ〟ですが、慣れてくると素早く簡単にできるようになります。
お助けグッズもかなり役に立ちますので、〝ムシ〟が難しい場合は使ってみてくださいね。
ぴったりサイズの合った衣装で舞台で輝きましょう!!
-
7.182025
お家でもバーレッスン!?自主練用のバーはどんなものがいいのか徹底検証!!


バレエを習っている方の中には毎日お稽古したい!!という方も多いでしょう。
バーレッスンはバレエの基礎が詰まっているので毎日できるに越したことはないですよね。
しかし、バーレッスンは自宅でできるのでしょうか?
今回は自宅で練習する際に適したバーのおすすめや、その他に必要なものなどを紹介します。
自宅でバーレッスンをしたいと考えている方は参考にしてみてくださいね!!
バレエのレッスンに必須!バーレッスンのバーとは

バレエのお教室には必ずといっていいほどバーが備わっています。
それはバーを使用して行う、バーレッスンがバレエにとって重要だからです。
まずは、バーレッスンについてと、自宅にバーがあるメリットについて解説していきます!
バーレッスンとは
バレエのレッスンで必ず行われるレッスン方法がバーレッスンです。
バーレッスンはバレエの基本的なポジションや動きを身につけるために行われ、バレエを踊るために必要な体つくりや、踊る際に必要な筋肉などを維持するための要素が含まれます。
バーを離れた際に動けるようになるには、バーに頼りすぎないことが大切。
バーレッスンの時点で正しいポジションやフォームを確認することで、踊りにも大きく反映します。
プロノバレーリーナは毎日バーレッスンを行なっていたり、本番前にも必ず行なっているはずです。
中には、バーレッスンを行うことで、その日の調子をうかがっている方も多いでしょう。
それほど、バレエを踊る際に必須なのがバーレッスンなのです。
自宅にバーがあるメリット
上記で紹介したバーレッスンは毎日行うと、基礎がしっかりし踊りの向上に役立ちます。
そのため自宅にバーがあった場合、お稽古場に行かなくても自分の好きなタイミングや好きな時間で好きなだけバーレッスンを行えます。
レッスンに行かない日や、レッスンの予習や復習もできるので、とにかく自分の好きなように練習できるのが最大のメリットでしょう。
バーレッスンは、自宅にバーがなくても椅子や壁などでも代用は可能ですが、バレエのバーとは感覚が異なるので、力の入り具合が変わってしまうことも・・。
そのため、せっかく自宅でバーレッスンをするなら、バレエ用のバーがあった方が良いでしょう。
自宅でバーレッスンは可能!?自宅用のバーを選ぶ際のポイント

自宅でバーレッスンを行う際は、どのようなバーを選ぶと良いのでしょうか?
自宅用バーを選ぶ際のポイントを紹介しますので、バー選びの参考になさってくださいね。
高さ調節ができる
バーは自分の高さが合っていることが大切です。
自分の身長に合っていないものは、ストレッチやバーレッスンの際使いづらいのでバーの高さを調節できるタイプがおすすめ。
また、身長が伸びた際やきょうだいで使用する際にも高さを調整できると便利です。
高い位置と低い位置のそれぞれの高さにバーを備えているバーも用途によって使い分けやすいのでおすすめです。
バー長さや太さ
自宅にバーを置く場合は、どのくらいの長さのバーを置けるか事前に確認が必要です。
自宅用のバーはお稽古場のバーと違い、コンパクトなものが多いです。
可能であれば長めのバーの方が、できる動きが増えるので良いでしょう。
また、バーには太めのものや細めのものがあります。
太さについては好みもあるので、自分の握りやすい好きな太さにしましょう。
バーの素材
自宅用のバーの素材は木製やプラスチック、アルミ製といった種類があります。
お稽古場で使用されているバーの多くは木製が多いです。
普段のレッスンと同じ感覚が良いという方は木製を選ぶといいかもしれません。
プラスチックやアルミ製の利点は軽くて持ち運びがしやすいことです。
用途や好みに合わせて素材もチェックしてみましょう!
バーの重さ
バーはバーレッスンの際に支えとして捕まるものなので、ある程度の重さがある方が安定します。
持ち運べるからと軽さにこだわりすぎてしまうと、レッスン中にぐらついてしまう場合も・・。
逆に持ち運ぶ頻度が高いと重いバーは、持ち運びが大変なので重すぎるのも注意が必要です。
ずっと同じ場所に置いて置く場合は多少重くても良く、持ち運びが多い場合は軽めの(軽すぎはNG)ものが良いでしょう。
バーの土台部分
バーを支えている土台部分ですが、重さがありふらつかないものがベスト。
しかし、土台部分がしっかりしすぎているものや幅が広いものはバーレッスンの際に足がぶつかるデメリットもあります。
そのため、安定感がありつつスリムなものがベストでしょう。
自宅でバーレッスンにおすすめのバー3選

自宅用バーを選ぶ際のポイントを紹介しましたが、実際におすすめのバーも紹介します。
どのバーを購入していいか分からないという方は参考にしてみてくださいね!!
バレエスタンド/ZENRO
ゼンロのバレエスタンドは5段階(85cm 90cm 95cm 100cm 105cm)の高さ調整が可能です。
そのため、成長に合わせて高さを調整できるのでおすすめ。
また、木の質感も活かされた直径5cmのバーはつかまりやすくレッスンがしやすいです。
ブランド・・・ZENRO
カラー・・・ナチュラル
サイズ・・・119×27×7.50cm
重量・・・約9kg
材質・・・ウッド+ステンレススチールポータブルバレエスタンド/チャコット
カラー展開の少ないバーが多い中で、チャコットのポータブルバレエスタンドはオフホワイトに加え、ロイヤルピンクやライラックと可愛いお色がありレッスンのテンションも上がりそう!
持ち運び用のバッグも付いているので、発表会やコンクールの会場などバーがない場所でもバーレッスンを行えます。
ブランド・・・チャコット
カラー・・・オフホワイト・ロイヤルピンク・ライラック
サイズ・・・高さ1mX幅1.1mX奥行55cm バー:直径40mm
重量・・・約9kg
材質・・・鉄(メラ焼き仕上げ)バレエスタンド バレエレッスンバー/RiZKiZ
一般的にバレエ教室で使用されているバーの直径5cmと差が出ないよう直径4,8cmで作られており、普段のレッスンのように練習ができます。
別売りのバーとスタンドを買い足せば幅を2倍に広々使うこともできます。
ブランド・・・リズキズ(RiZKiZ)
カラー・・・ホワイト・ベージュ
サイズ・・・(約)幅110cm×奥行65cm×高さ85cm・100cm
※高さ2段階調整可能
重量・・・約7.5kg
材質・・・スタンド:スチール・PP樹脂・PVC
バー:スチール
耐荷重・・・(約)200kgまとめ

バレエが大好きで練習がたくさんしたいお子さまにとって、自宅にバーがあるのは夢のようですね!
自宅に置けるバーにも種類が豊富にあります。
お子さまに合ったバーを選んで、ぜひ自宅でもバレエのレッスンを楽しんでくださいね!!
-
7.162025
エレガントさがアップする!?自分にぴったりのティアラをみつけよう!!


バレエの衣装といえばチュチュですが、頭飾りであるティアラもエレガントさをアップさせるのに重要なアイテムです。
キラキラのエレガントなティアラに憧れているという方も多いでしょう。
今回はバレエでティアラを付ける役柄や、ティアラの入手方法、ティアラの選び方などについて紹介します!!
ティアラに憧れている方は参考にしてみてくださいね!
バレエでティアラをつけるのはどんな時!?ティアラ着用の意味と役柄について

ティアラはどのような時に付けるものなのでしょうか?
バレエ作品におけるティアラを付ける役柄や、その付け方について紹介します。
ティアラを付ける意味や理由
ティアラには「星空の神々からの祝福と繁栄の授かり」、「永遠の愛を誓う」、「誓いや清め、祝福の象徴」といった意味が込められています。
古来より星空は神聖なものとされており、重大な決断や誓いの際は星空の下で行われていました。
そのため、戴冠式や結婚式で着用されるティアラのデザインにはキラキラと光り輝く装飾がつけられ、星空がイメージされています。
王族が戴冠式でティアラを頭上におく理由は「神々からの贈り物」の象徴であるとされているためです。
ティアラの由来や、付ける意味を知ると付ける時の気持ちも神聖なものになりそうですね
ティアラの種類
バレエで使用するティアラには様々な形があります!
上記で紹介した役柄に合ったティアラの形を選ぶことが重要です。
ティアラの形や種類について解説していきます。
プリンセス型のティアラ
プリンセスタイプのティアラは、宝石(イミテーション含む)をたっぷり使ったものが多いです。
豪華な衣装にもシンプルな衣装にもマッチするスタンダードなティアラといえます。
柄の部分は伸び縮みしないので、頭の大きさに合ったティアラを選ぶと良いでしょう。
一連or二連カチューシャ型のティアラ
カチューシャのように着けられるティアラはおでこの部分に前飾りがあるものとないものがあります。
カチューシャの形をしているので着用しやすいという特徴もあります。
クラウン型のティアラ
白鳥、黒鳥や妖精の女王などの役柄で使用されることが多いのがクラウン型です。
女王の役などになると大型のクラウンで飾りが普通のものより豪華なこともあります。
シニヨンに合わせてつけるティアラ
シニヨンに沿って、シニヨンの上部や下部に着けるタイプのティアラです。
着ける位置をシニヨンの高さによって変えることができます。
頭飾りにティアラをつける役柄
前述の通りティアラは星空がイメージされており、神聖なものとして扱われています。
そのため、バレエ作品に登場する役柄でティアラを付けるのはプリンセスや妖精といったものが多いです。
3大バレエ作品で頭飾りにティアラを付ける役柄の例を紹介します。
『眠れる森の美女』
3大バレエ作品の一つである『眠れる森の美女』でティアラを付けるのは下記の役柄です。
・オーロラ姫
・リラの精
・やさしさの精、元気の精、第1幕:鷹揚(おうよう)の精、勇気の精、のんきの精
・フロリナ王女
・宝石の精プリンセスや妖精が多く登場する『眠れる森の美女』ではティアラをした役柄の登場回数も多いですね!!
『白鳥の湖』
3大バレエ作品の一つである『白鳥の湖』でティアラを付けるのは下記の役柄です。
・オデット姫(白鳥)
・オディール(黒鳥)
・王子の花嫁候補(各国の王女)踊りの技術が高いのは当然ですが、衣装やティアラといった見た目も圧倒的な主役感のあるオデット姫。
オデット姫のティアラには白い羽があしらわれており、羽のついたティアラに憧れている方も多いでしょう。
『くるみ割り人形』
3大バレエ作品の一つである『くるみ割り人形』でティアラを付けるのは下記の役柄です。
・金平糖の精
・マリー姫『くるみ割り人形』はバレエ団や上演される国によって演出が異なる演目です。
※プリンシパルが金平糖の精を踊りますが、マリー姫と金平糖の精は同一人物であるというパターンもあります。
※プリンシパル・・・バレエの最高位の名前
きれいなティアラの付け方
お団子ヘアにしてからの手順を紹介します。
- ティアラの真ん中を鼻筋の延長線と合わせ中心を決める
- 中心部分が決まったら、Uピンを横にさします。
- さしたUピンをアメリカピンで固定します。
- 両サイドにも同じ要領でUピンとアメリカピンで固定していきます。
- さらに固定したい場合が中央とサイドの間にUピンとアメリカピンで固定します。
最後に、動いてもティアラが取れないか確認してみましょう!!
ぴったりのティアラを身につけよう!!ティアラの選び方の3つポイント

ティアラは普段身に付けることが少ないので「選び方がわからない」という方も多いかもしれません。
しかし、これから紹介するポイントを抑えていれば自身にぴったりのものが見つかる可能性が高いです!
ティアラ選びの参考にしてみてくださいね!!
作品のイメージに合っているか
バレエの場合、ティアラは好みのものを着ければいいという訳ではありません。
ティアラはバレエ作品の一部といっても過言ではないんです。
そのため、バレエ作品の世界観を知り、理解する必要があります。
作品や役柄に合ったティアラを思い浮かべることで、「どんなティアラが必要なのか」がわかってきます。
衣装とコーディネートできているか
ティアラを着用する際には衣装と合っているかも重要です。
特に色や雰囲気、形といったことがコーディネートのポイントとなります。
衣装に使用されている糸や装飾の色にティアラを合わせると雰囲気がまとまりやすくなります。
踊り手に合っているか
ティアラのサイズ感も、ティアラを選ぶ際に重要なポイントとなります。
お顔の大きさや、肌の色といったことを考慮し選びましょう。
お顔の形・大きさ
お顔の形が丸い場合はプリンセス型が、面長な場合は高さが出ないカチューシャ型がオススメです。
また、お顔の大きさもティアラ選びの重要なポイントです。
小さなお子様のお顔にボリュームのあるティアラを着けてしまうとバランスが悪くなってしまいます。
一方、お顔が大きい方に華奢なティアラを着けてしまうと大柄が強調されてしまう場合も・・。
そのため大きめでボリュームのあるものを選んでみましょう!!
肌の色に似合う色
最近ではパーソナルカラーという言葉もよく聞きますね。
バレエのティアラ選びにもパーソナルカラーは役立ちます。
イエローベースかブルーベースかを知っていれば色を選ぶ際に迷いません。
例えば、「白」といっても青よりの白や黄色味がかった白があります。
肌の色に合った「白」を選ぶことで、全体の統一感も変わってきます。
好きな色より似合う色を探すことが重要ですが、好きな色が似合う色の場合も多いのも事実です。
ティアラはどこで手に入る!?ティアラの入手方法

ティアラは、バレエスタジオの先生が衣装とともに用意してくださることが多いです。
しかし、自身で気に入る物を用意したい、用意を任された際には、下記のような入手方法があります。
購入する場合
ティアラが購入できるのはバレエショップ、もしくは最近ではオンラインショップで購入が可能です。
ティアラを販売しているバレエショップとオンラインショップを紹介します。
バレエショップ
都市部の大きいショップには常時、ティアラが用意されている場合もありますが、取り寄せとなってしまうこともあるので気になるものがあれば、問い合わせをしてから来店するのがオススメです。
チャコット
お値段 11,000〜19,800円
シンプルながら上品なティアラが見つかります。
また、シンプルな分、様々な演目に対応できそうです。
オンラインでも購入可能です。シルビア
値段 2,300円
ティアラにはコームがついているので、自分自身でもつけやすそうなデザインです。
オンラインショップもあります。エトワール
値段 1650〜24,200円
小ぶりでプチプラなティアラから、ラインストーンがたくさんあしらわれた豪華なものまで揃っています。
オンラインショップもあります。バレエショップで直接、購入する利点は実際に商品を見られること。
また、スタッフの方に相談ですこともできますね。
オンラインショップ
上記のバレエショップもオンラインでの購入が可能ですが、オンラインでのみ販売を行なっているティアラの専門店もあります。
ティアラを販売しているオンラインショップを紹介します。
値段 19,800〜20,350円
カラーや役柄がカテゴライズされていますので、自身の探しているティアラを見つけやすいのも◎
お値段は少し張りますが、ハンドメイドの豪華なティアラを購入することができます。
値段 12,000〜25,000円
商品名に役柄が書かれているので選びやすいです。
また、付け加える必要がないほど豪華なので、そのまま使用できるでしょう。
バレエティアラ Tiaras balletatticprop
値段 14,500円〜
品切れとなっているものが多いものの、セミオーダー(リクエスト)できるようなので気になるものがあれば問い合わせてみましょう。
レンタルする場合
一度しか踊らない役柄のために購入するのはちょっと勇気がいるという場合にはレンタルがオススメです。
衣装もレンタルする場合はティアラを含む頭飾りがついてくるところも。
下記にティアラのみをレンタルできるショップを紹介します。
衣装とティアラのレンタル
衣装のレンタルを行なっているお店では頭飾り(ティアラを含む)も衣装と一緒に貸し出しを行なっている場合もあります。
例えば下記のお店ですと、衣装と頭飾り両方のレンタルを行なっています。
アトリエヨシノ https://www.atelier-yoshino.com/
ティアラのみレンタル可能
衣装はすでに決まっている、持っているという場合はティアラのみのレンタルがオススメ。
ティアラのレンタルを行なっているお店は下記の通りです。
値段3,850〜4,950円
役柄の特徴をとらえた様々なティアラが購入するよりもお安くレンタル可能です。
手作りする場合
時間がある場合は手作りするというのもティアラの入手方法の1つです。
購入やレンタルの場合には他の人とかぶってしまう場合もありますが、手作りの場合は完全オリジナルなので人とかぶることはないでしょう。
初心者にはなかなか手作りはハードルが高いですが、最近ではティアラ作りの教室もあるようなので、時間がある場合は参加してみてもいいかもしれませんね。
下記はティアラ教室を開催しているお店です。
・Vivienne blanc https://www.vivienne-blanc.com/tiara-lesson/
・パッショネクト https://itosachi.com/
・ティアラlino https://fuwamoko74.amebaownd.com/
まとめ

ティアラを着けるとテンションがアップするという人も少ないはず!
ティアラには不思議な力がありそうですね。
バレエ作品を表現する際にも重要なアイテムとなります。
自分に合ったお気に入りのティアラをぜひ、みつけてみてくださいね!
-
7.162025
【初心者向け】これからバレエを始める方必見!バレリーナの足を知ろう!バレエレッスンのための基礎知識


バレリーナの美しい足に憧れている人も多いのではないでしょうか?
今回はバレエ向きの足についてや、バレエレッスンの基礎である足のポジションなどについて紹介します。
バレエを習うか検討されている方、バレエを習いたての方は参考にしてみてくださいね。
バレエ向きの足とは

ピーンと伸びた足が美しいバレリーナ。
どのようにして綺麗な足になるのでしょう。
もともと足の形がバレエに向いている人もいますが、もしそうでない場合でもバレエをすることは可能です。
正しいレッスンをすることでバレリーナのような足になれる可能性が、誰でもあります。
バレエに向いている足の形
一般的にバレエ向きの足は、まっすぐか少しX脚気味が良いとされています。
しかし、自分の足がこれに当てはまらないからといってバレエを諦める必要はありません。
バレエのレッスンを通して、正しく身体を使えばバレリーナのような美しい足に近づくことは可能です。
バレリーナの足が美しい理由

バレリーナの足は美しいですが、誰でも始めから美しい訳ではありません。
正しいレッスンや食事管理などを通して美しい足は仕上がります。
以下にバレリーナの足が美しい理由を説明します。
正しいレッスンを行なっている
バレエのレッスンで間違った筋肉を使ったり、力のかけ方を間違うと逆に足が太くなってしまう場合もあります。
バレエは足の内側の筋肉を使うことが多く、内側の筋肉が付いている方が美しく見えます。
逆に外側の筋肉が発達してしまうと足が太く見えることも・・。
そのため、闇雲にたくさんレッスンするのではなく正しいレッスンを行うことが重要です。
食事管理をしている
正しいレッスンを行なっていても、お菓子やジャンクフードを食べてばかりしていては効果が台無しに。
バレリーナは食事管理もしっかり行うことで美しい足をキープしています。
しかし、極度に食事を減らすのではなく、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
特に成長期のお子さんは、しっかり食事で栄養を摂る必要があります。
脂質や糖質が多い食べ物は脂肪に変わりやすいので控えめにするなど少しだけでも意識してみましょう。
バレエレッスンの基礎 足のポジションを覚えよう!

バレエのレッスンで一番初めに習うことが多いのが、足のポジションです。
バレエでは1〜5番までのポジションがあります。
1つずつ紹介していきますので、お家でも練習してみてください。
1番ポジション
- まっすぐに立ち、両方の膝とつま先を正面に向けます。
- つま先を左右外向きに45度ずつ開きます。
- つま先を無理のないところまで開いてみましょう。
2番ポジション
- まず1番のポジションに立ちます。
- そこから、自分の足の1つから1つ半くらいの幅に足を広げます。
3番ポジション
- まず1番のポジションに立ちます。
- 片方の足のかかとを、もう片方の足の土踏まずのあたりに置きます。
4番ポジション
- 3番ポジションから前に置いてある方の足を1歩前に出します。
- 重心が足と足の真ん中になるよう調整しましょう。
5番ポジション
- 4番の状態から、前に置いている足を後ろの足に重ねます。
- つま先とかかと同士がくっついた状態が理想です。
ポジション注意点
・小さいお子さんの場合は5番ポジションが難しい場合があります。
そういった場合には、まずは5番ポジションに近い3番ポジションから練習してみましょう。・練習をする際は手は腰でも良いです。
・1番から5番まで終わったら、足を入れ替えて反対の足も練習してみましょう。
まとめ

バレリーナのような美しい足を目指すには、正しいレッスンと食事管理が重要です。
ただ小さいうちは「バレエが好き」という気持ちも大切。
その気持ちが今後の成長に大きく役立つためです。
また、バレエレッスンの基礎である足のポジションは一見、簡単そうに見えますがとっさにポジションを取るのは難しい場合もあります。
足のポジションは美しい踊りの第一歩となります、ぜひお家でも練習してみてください。
-
7.162025
バレエをやっていたら一度は読みたい!?人気バレエ漫画TOP 5


バレエ漫画には魅力的な主人公が登場し、難易度の高い技や役に挑戦したり、人間関係やバレエとの向き合い方に悩む姿がみられます。
読んでいるうちに共感したり、勇気をもらうことも。
今回はそんなバレエをやっていたら1度は読んでみたくなるバレエ漫画TOP5を紹介します!
バレエ漫画を読んでみたい、興味がある方は参考にしてみてくださいね。
第5位『トウ・シューズ』

バレリーナになりたい女の子の日常と成長を描いた『トウ・シューズ』
バレエの試練だけでなく甘酸っぱく可愛いラブストーリーにも注目です。
作品概要
完結 全5巻
作者 水沢めぐみ
出版 集英社あらすじ
森野くるみは小学校5年生の時に友達の桃子に誘われ発表会で上演されている「くるみ割り人形」を観に行きました。
そこで見たバレリーナの白河はづきの踊りに感動したくるみはバレリーナを夢見るようになります。
しかし、バレエの実力以外の重要な要素の1つ「身長」に小柄なくるみは悩むことに。
同じように幼馴染の同級生であるサッカー少年 智也も身長が低いことをコンプレックスに感じていました。
2人は犬猿の仲でしたが、同じ悩みを抱えた2人は次第に共に支え合うようになっていきます。
みどころ
智也は密かにくるみに好意を抱くものの、くるみには憧れのダンサーがいて智也の気持ちになかなか気づくことができません。
バレエのストーリー以外にも、もどかしい恋愛模様といった甘酸っぱく可愛らしいストーリーにも注目です!
第4位『Do Da Dancin’!』

挑戦することに遅すぎることはないと励まされるバレエ漫画。
主人公のバレエに対するひたむきさに心動かされるはずです。
作品概要
完結 全9巻
作者 槇村さとる
出版 集英社あらすじ
主人公の桜庭鯛子は母の死をきっかけにプリマへの道を諦めてしまいます。
しかし、22歳で再びプリマへの道に挑みます。
プロを目指すには遅すぎる年齢という現実にめげそうになる鯛子ですが、友人や家族から励まされ奮闘します。
みどころ
鯛子がバレエで成功するためには「全日本クラシックグランプリ」で優勝し、クラシックバレエの最高峰「ヴェネチア国際コンクール」で入賞することが必須条件です。
鯛子は自分とバレエを見つめ直しコンクールで入賞することができるのでしょうか!?
続編の『Do Da Dancin’! ヴェネチア国際編』では鯛子がプロになるための戦いが描かれています。
進化し続ける鯛子と彼女のバレエから、最後まで目が離せません。
第3位『絢爛たるグランドセーヌ』

主人公のバレエに対するピュアな気持ちに心打たれるバレエ漫画です。
2025年現在も連載が続いており続きが気になる人が続出中です!
作品概要
1〜25巻(連載継続中)
作者 Cuvie
出版 秋田書店あらすじ
主人公の有谷 奏(ありや かなで)はごく普通の女の子。
隣町に住んでいる梨沙のバレエ発表会を観たことを機にバレエに魅せられ両親に頼み込み近所のバレエスタジオに通い始めます。
バレエを始めて発表会で舞台に立つ楽しさを実感した奏はプロのダンサーを目指し奮闘します。
みどころ
本作は舞踊史・舞踊評論家として知られている村山久美子さんが監修の本格作品です。
主人公の奏は体格や柔軟性、音感は平凡ですが、素直な性格で観察眼や吸収力は抜群。
そのため自分が「いいな」と思った演技者の良いところを見つけ自分に取り込もうと努力します。
自分の踊りを客観視でき、人の優れた部分を素直に認めることができる奏ではどんどん上達していきます。
奏での他にも小さい頃から英才教育を受けてきたエリートの栗栖さくらや、才能があるゆえに努力を嫌うクールな藤田絵麻、そして奏と同じスクールに通う1つ年上で努力家の伊藤翔子といった個性豊かなライバルたちも目を引きます。
また、バレエを続ける上での金銭的な壁や進路の悩み、才能に対する葛藤なども描かれています。
バレエに打ち込む少女たちの、ひたむきな姿に心打たれること間違いありません。
第2位『ダンス・ダンス・ダンスール』

『溺れるナイフ』や『ピースオブケイク』のジョージ朝倉先生が描く、バレエ男子が主人公の珍しいバレエ漫画。
タイトルの「ダンスール」とは男性バレエダンサーを意味する言葉なんです。
作品概要
1〜28巻(連載継続中)
作者 ジョージ朝倉
出版 小学館あらすじ
主人公は中学2年生の村尾潤平。
幼い頃からバレエに興味があったが、バレエは女性的な面が多いという気持ちが強く本気で取り組むことに迷いを感じていました。
しかし、美少女の転校生 五代都(ごだい みやこ)から誘われたのを機にバレエへの情熱が目覚めます。
みどころ
「男らしく、カッコよくいたい」という気持ちは思春期の男の子なら誰にでもあるものです。
主人公の潤平もその1人でバレエをやっていることを友達に言えずに隠れて練習をしていました。
しかし、ライバルの少年 流鶯(るおう)の出現によりバレエに本気で取り組む決意をします。
流鶯は天性の才能がある美少年、一方の潤平は抜群のセンスと粘り強さがあり2人のライバル関係は巻を追うごとに目が離せなくなります。
潤平と流鶯のライバル関係、潤平が憧れている都との恋愛模様と今後の展開がどんどん楽しみになる作品です。
第1位『昴』

代表作『め組の大吾』で有名な曽正人 が実在のバレエダンサーであるシルヴィ・ギエムから着想を得たという本格的なバレエストーリーです。
主人公 すばるがストイックな姿勢でバレエに取り組む姿が感動を呼ぶ人気作品です。
作品概要
完結 全11巻
作者 曽田正人
出版 小学館あらすじ
主人公のすばるは悪性の脳腫瘍に侵された双子の弟 和馬を勇気づけるため毎日のように病室に通って踊りを見せます。
しかし、すばるの想いも虚しく和馬は帰らぬ人に・・。
そんな悲劇から、すばるのバレエは生きるためになくてはならない存在になっていきます。
すばるの命を削るような演技にただただ圧倒されること間違いありません。
みどころ
『昴』は主人公 すばるのバレエへの熱量が伝わってくる作品です。
新人バレリーナの登竜門となっているローザンヌ国際バレエコンクールへの参加や渡米など着実に才能を磨きステップアップし孤高のバレリーナとなっていくすばる。渡米後のすばるは続編『MOON -昴 Solitude standing-』で描かれており、新たなライバル、長年にわたる母親との不和や生涯のパートナーとの出会いなど自身の人生との向き合い方にも胸を打たれます。
限界を超えさらなる高みを目指す、すばるのプリマドンナとしての生き様は必見です。
まとめ

どの作品の主人公たちも熱い気持ちを持ってバレエをしているのがわかりますね。
落ち込んだ時や、やる気がおきない時にバレエ漫画を読むと主人公たちがきっと励ましてくれるはずです。
漫画といえどもバレエの勉強やモチベーションとなりますので、ぜひ読んでみることをオススメします!
-
7.162025
【高校生以上編】新国立劇場バレエ団の団員になるには?オーディションを徹底解説!


日本で唯一、公演のための専用劇場を持つバレエ団である新国立劇場バレエ団。
日本を代表するバレエ団であり、どうしたら団員になれるのか気になる方も多いでしょう。
今回は新国立劇場バレエ団の歴史やオーディションについて紹介します。
新国立劇場バレエ団について

新国立劇場を専属劇場とするバレエ団です。
日本の文化政策の一環として活動している日本を代表するバレエ団で、日本全国から優秀なダンサーが揃っています。
2020年からは長年、英国でプリンシパルダンサーとして活躍した吉田都さんを芸術監督に迎え、さらなる飛躍が期待されています。
古典バレエのみならず「アラジン」や「不思議の国のアリス」といった他のバレエ団では見ることができない演目を上演するなど、人気の高いバレエ団の1つです。
公式HP 新国立劇場バレエ団
新国立劇場バレエ団の団員や演目について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください↓
日本で唯一!国立の劇場所属 新国立劇場バレエ団について知ろう
新国立劇場バレエ団の階級制度
バレエ団では階級制度があり、階級によって配役が決まっていることも多いです。
新国立劇場バレエ団の場合は下記のような階級制度となっています。
プリンシパル(主役を踊る最高位のダンサー)
ファースト・ソリスト(準主役級のダンサー)
ソリスト(ソロパートを踊るダンサー)
ファースト・アーティスト(コール・ド・バレエ(群舞)の中でも中心的な役割を担うダンサー)
アーティスト(コール・ド・バレエ(群舞)の一員)
特に主役を踊ることが多い最高位のプリンシパルはバレエ団の看板ダンサーともいえますね。
新国立劇場バレエ団のプリンシパルとして活躍している方々をチェックしましょう。
新国立劇場バレエ団プリンシパル女性バレエダンサー
現在、新国立劇場バレエ団では4人の女性バレエダンサーがプリンシパルとして活躍されています。
新国立劇場バレエ団プリンシパル女性バレエダンサー
・小野絢子さん
・木村優里さん
・柴山紗帆さん
・米沢 唯さん
新国立劇場バレエ団プリンシパル男性バレエダンサー
現在、新国立劇場バレエ団では5人の男性バレエダンサーがプリンシパルとして活躍されています。
新国立劇場バレエ団プリンシパル男性バレエダンサー
・井澤 駿さん
・奥村康祐さん
・速水渉悟さん
・福岡雄大さん
・渡邊峻郁さん
新国立劇場バレエ団の主なレパートリー
新国立劇場バレエ団では年間を通して古典バレエからオリジナル作品まで上演されており、数多くのレパートリーがあります。
主なレパートリーを紹介しますので、観劇の参考にしてみてくださいね。
古典バレエ作品
新国立劇場バレエ団が上演する古典作品の主なレパートリーには下記のようなものがあります。
・くるみ割り人形
・白鳥の湖
・眠れる森の美女
・シンデレラ
・ジゼル
・ドン・キホーテ
・ライモンダ
オリジナル作品
新国立劇場バレエ団が上演する古典作品のレパートリーには下記のようなものがあります。
・アラジン
・不思議の国のアリス
・人魚姫
新国立劇場バレエ団の団員になるには

新国立劇場バレエ団の団員になるためにはオーディションを受ける必要があります。
オーディションの詳しい内容は下記の通りです。
※下記は2024年度のものです。
オーディションの概要
募集条件
① 契約開始時点で、満18歳以上の方。
② 原則として、女性は身長163cm以上、男性は身長173cm以上の方。
①と②の条件を満たしている方。
- 報酬&待遇
・シーズンを通じての固定報酬に加え、実績に応じた出演料が支払われます。
・ポワント、シューズ支給(財団規定による)
・稽古及び舞台期間中のステージトレーナーによる施術 その他サポート体制有り
・全国公演の日当、宿泊費、交通費支給契約期間
2024年9月1日~2025年7月31日
オーディションの概要
▼第一次審査
日程:2024年2月4日(日)
会場:新国立劇場リハーサル室
内容:クラスレッスン
▼第二次審査
日程:2024年2月5日(月)
会場:新国立劇場リハーサル室
内容:カンパニークラス
応募方法
申し込みフォームに必要事項を入力の上、応募します。
提出するポーズ写真及び映像は、以下の条件を満たす必要があります。写真・・・稽古着着用。第一アラベスク、真横から撮影。女性はトゥシューズ着用、オンポワント。
映像・・・クラシック作品に限る。過去半年以内に撮影されたもの。舞台、稽古場いずれも可。
申し込み〆切:2024年1月5日(金)厳守2024年度のオーディションは2月上旬に2日間に渡り開催されました。
募集の締め切りは1月上旬なので、それまでにしっかり準備をしておく必要があります。
※オーディション毎に内容が変わる場合があります。
まとめ

日本で唯一、専用の劇場を保有するバレエ団。
日本中から優秀なバレエダンサーが集まっています。
演目も3大バレエや古典作品に限らずオリジナル作品にも力を入れ、子ども向けの作品も上演しているなど身近に観劇しやすいバレエ団です。
また、オーディションの概要にもあるように報酬や待遇がしっかりしており、団員になった際にはしっかりバレエに集中できそうです。
入団するバレエ団を迷っている方は参考にしてみてくださいね。
良いバレエ団が見つかるよう願っています。
-
7.162025
バレエグッズを手軽に買おう!バレエ用品専門通販サイト4選!


みなさんは普段どこでバレエ用品を購入しますか?
バレエ用品専門店は店舗数が少なく、特に地方に住んでいる方は直接お店でバレエ用品を買うことは難しいですよね。
そこで便利なのが通販!
最近ではバレエ用品を扱う通販サイトが増え、バレエ用品を専門で扱っている通販サイトもたくさんあります。
そこで今回はバレエ用品の通販サイトをご紹介します!バレエ用品専門店ミニヨン

バレエ用品専門店ミニヨンは、実店舗を持たないオンライン専門のバレエ用品店です。
幅広い商品ラインナップで人気の高い通販サイトです。おすすめポイント①幅広い品ぞろえ
ミニヨンには、トウシューズ、レオタード、バレエタイツ、スカート、アクセサリーなど、バレエに必要なアイテムが充実しています。
取り扱いブランドは50以上あり、ミニヨンオリジナルブランドもあるんです!
トゥシューズもグリシコやブロック、カペジオなどの有名ブランドをはじめとする12ブランドの取り扱いがあるため、きっと自分に合ったトゥシューズが手に入るでしょう。
また、姉妹店として楽天市場やAmazonなどの大手ECサイトでも取り扱いがあるため、自分に合った方法で購入できるのも魅力です。おすすめポイント②発送が早い
ミニヨンの魅力は充実した配送サービスです。
平日14時までの注文は当日発送ができるので、急ぎの買い物にも便利です。
また、送料も良心的で、税込11,000円以上の注文で送料が無料となります。
さらに毎月24日は「ミニヨンの日」で4,400円以上の注文で送料無料となるので、お得にお買い物ができます。おすすめポイント③学割・団員割がある
ミニヨンの特徴として、学割・団員割があります。
高校生以上の学生は、ミニヨンでのお買い物が10%オフになるんです!
学生の間は何度でも利用できるので、バレエをやっている高校生以上の学生は是非利用してほしいサービスです♪
また、学生だけでなく、バレエ団に所属しているダンサーのための「団員割」もあるんです!
学割と同じく、団員も10%オフでお買い物ができます。
バレエを頑張る人にとてもうれしいサービスですね。イーバレリーナ

イーバレリーナはオンライン専門のバレエ用品店です。
幅広い品揃えでバレエダンサーのあらゆるニーズに応えるオンラインショップとして、多くの利用者に支持されています。おすすめポイント①手ごろな価格でバレエグッズが買える
イーバレリーナは低価格で高品質な商品を提供しています。
タイツやバレエシューズはなんと約1,000円から購入できます!
買い替えの機会が多い消耗品を安価な値段で手に入れることができるのはとても嬉しいですね。
また、イーバレリーナではさまざまな「お買い得セット」があり、レオタードやタイツ、バレエシューズなどのバレエ用品のまとめ買いで割引になるサービスがあります。おすすめポイント②購入後のサポートが手厚い
イーバレリーナは、色やサイズの交換が無料でできます。
通販での購入は試着ができずサイズが合うか不安ですよね。
しかしイーバレリーナではサイズが合わなくても交換ができるので安心して購入することができます。
それだけでなく、30日間の使用保障もついているんです。
30日以内に商品に不具合が生じた場合、無料で返品や交換に対応してくれるそうです。
低価格の商品を多く提供しているため品質に不安がある方もいらっしゃるかもしれませんが、このような保障サービスがあるので安心して利用することができますね。おすすめポイント③発送が早い
イーバレリーナは、平日13時までの注文は当日出荷しています。
バレエショップが近くにないけど急いで注文したい!という方にはとても嬉しいサービスですね。
また、送料は全国一律250円と良心的なうえ、6,500円以上の注文で送料無料となるのも嬉しいポイントです。シルビア

シルビアはバレエやダンス用品を専門に取り扱う通販サイトです。
全国に実店舗も構えている人気のバレエショップです。おすすめポイント①取り扱いブランドが幅広い
シルビアは国内外の幅広い商品を揃えていることが特徴です。
海外の有名バレエ用品ブランドの商品を豊富に揃えているほか、シルビア独自のオリジナル商品も販売しています。
デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムが多い印象です。
また、バレエ用品のみならず、モダンダンスやジャズダンス用の衣装やフィットネスウェアなど、幅広い商品を取り扱っています。おすすめポイント②店舗で試着できる
シルビアは全国に5つの実店舗を構えています。
そのため、シューズやレオタードなどを店舗で実際に試着してから購入することができます。
フィッティングが必要な商品は店舗で購入し、それ以外の商品はネットで購入するなど、店舗と通販を場面に応じて使い分けられるのも便利です。おすすめポイント③セールでお得にゲット!
シルビアでは定期的にセールを開催しています。
例年夏にサマーセールを、冬にはウィンターセールを開催しており、セール時期にはお得にバレエ用品をゲットすることができます。
セール時期は商品の価格が安くなるだけでなく、送料無料になる購入金額が下がる場合もあり、さらにお得にお買い物をすることができるので要チェックです!チャコット

チャコットは言わずと知れた老舗バレエ用品メーカー。
店舗のみならず通販でも購入することができます。おすすめポイント①安心して利用できる
チャコットはバレエを習ったことがない人でも耳にしたことがあるくらい有名なバレエ用品メーカーです。
1950年創業の老舗バレエ用品メーカーで、国内の各種バレエ公演でスポンサー活動を行うなどとても信頼できるメーカーです。
そんなチャコットが運営する通販なので安心して利用することができますね。おすすめポイント②店舗で実物を見て購入できる
チャコットは全国に26店舗と他のバレエ用品店と比べて圧倒的に多い実店舗を構えています。
店舗で実際に試着してみたり、実際に手に取って商品を見てみることが可能です。
また、オンラインショップで購入したものを店舗で受け取ることができるサービスもあります。
店舗受け取りの場合送料無料になるので、お得にお買い物ができますね。おすすめポイント③メイク用品が充実している
チャコットはレオタードやタイツなどのバレエ用品だけでなく、舞台メイク用品も有名ですね。
最近では、チャコットのメイク用品は舞台メイクに限らず、デイリーメイクとしても人気があります。
オンラインショップにも数多くの舞台メイク用品の取り扱いがあり、発表会やコンクールで舞台メイク用品を揃えたい場合、チャコットのオンラインショップが便利です。通販でバレエ用品を買うメリット・デメリット・注意点

店舗に行かずにバレエ用品を手に入れることができる通販はとても便利ですよね。
しかしメリットだけでなく、デメリットや注意点もあります。
ここではバレエ用品通販のメリットとデメリットをお話しします。メリット①店舗が近くになくても手軽に購入できる
バレエ用品専門店はどこにでもあるわけではありません。
特に地方に住んでいる人にとって、店舗で実物を見て買うことは簡単ではありません。
しかし、通販なら近くに店舗がなくても気軽に購入することができます。
最近では無料でサイズ交換ができるサービスを提供しているECサイトも多くあるため、試着ができないネットショッピングでも安心して購入することができますね。メリット②安価に手に入れやすい
オンライン専門のバレエ用品店は、実店舗のバレエ用品店に比べて低価格な商品が多くあります。
実店舗を持たない分、店舗の運営費がかからないため安価に良質な商品を提供できるのでしょう。
タイツやバレエシューズなどは消耗品ですから、安く買えると嬉しいですよね。
また成長の早い子どものレオタードなども通販だとお得に買えるかもしれません。デメリット①サイズが合うかわからない
通販における最大のデメリットのひとつは、実物を見て買うことができない点です。
届いて試着してみたらサイズが合わなかった…なんて経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかし、最近ではサイズ交換が可能なECサイトも多くあるので、実物を見て買えないことに不安がある人でも利用しやすくなっています。デメリット②届くまでに時間がかかる場合がある
店舗で購入する場合にはすぐに商品を手に入れることができますが、通販の場合、注文から実際に商品を手にするまでに少なくとも2、3日かかります。
利用するサイトによっては届くまで1週間前後かかる場合もあり、早く商品が欲しいときには通販は向きません。
急ぎのお買い物は店舗で、そうでないときは通販を使うなどして上手にお買い物しましょう^^注意点:買う前に教室に確認する
バレエ教室によっては、レッスン中に身につけるレオタードやタイツ、シューズに指定がある場合があります。
また、初めてトゥシューズを履く場合などは教室でフィッティングし、まとめて購入することもあります。
通販で買う前に、指定のものがあるかどうかや教室でフィッティングをしてもらえるかなど、事前に確認してみましょう。まとめ

いかがでしたか?
今回はバレエ用品のオンラインショップをご紹介しました!
気になるサイトは見つかりましたか?
バレエ用品を手軽に買いたいみなさんの参考になれば嬉しいです。
是非自分に合ったサイトでお買い物を楽しんでくださいね♪ -
7.152025
どんなものが最適?もらって嬉しいバレエ発表会のプレゼント


初めてバレエの発表会に招待された際には「プレゼントは用意すべきか」悩む方も多いでしょう。
花束は用意すべきか、何を用意したら喜ばれるのかなどプレゼントを選ぶ際のポイントや渡す時のコツなどについて紹介します!!
初めてバレエの発表会を観に行く方は参考にしてみてくださいね!!
バレエ発表会にプレゼントは必須?喜ばれるプレゼントとは

初めてバレエの発表会に招待された時は、プレゼントを用意する必要があるのかと悩む方も多いですよね。
まずは、バレエの発表会でプレゼントを渡す理由や、喜ばれるプレゼントについてチェックしていきましょう!!
バレエの発表会にプレゼントを渡す理由
そもそもバレエの発表会でプレゼントを渡すべきなのかを悩む方も多いでしょう。
プレゼントを渡す一番の理由は「相手に喜んでもらえる」という点です。
また、発表会当日は出演者はとても忙しいので直接会えないことも多いです。
そういった場合に招待してくれた方に、「ちゃんと観にきた」ということを伝える手段でもあります。
直接プレゼントを渡せなくても、後々プレゼントを見れば誰が来てくれたのかが分かりますね!
喜ばれるプレゼント3選
バレエ発表会の定番のプレゼントといえば花束ではないでしょうか。
花束のプレゼントは喜ばれる方も多いですが、かさばるので持ち帰りにくいといったデメリットもあるようです。
最近では花束以外にもプレゼントを用意される方が増えています。
どんなプレゼントが実際に渡され、喜ばれているのかチェックしていきましょう!!
バルーン
特に小学生へのプレゼントで人気なのはバルーンです。
バルーンは花束よりも持ち運びやすく、長持ちで飾りやすいという特徴があります。
特に夏の暑い時期は花束が傷みやすいのでお花の代わりとしてバルーンが好まれます。
バレエグッズ
バレエをモチーフにしたバレエグッズは人気の高いプレゼントです。
中でもペンケースやポーチ、ミラーなど実用性があるものだと喜ばれます。
ぬいぐるみ
可愛らしいものが好きな方にはぬいぐるみがおすすめ!
バレリーナをモチーフにしたぬいぐるみもあり、もらうとテンションアップするという方が多いです。
何が最適?バレエ発表会プレゼント選びのポイント

定番の花束以外にもバレエ発表会で渡されるプレゼントはたくさんあります!!
バレエ発表会のプレゼントを選ぶ際のポイントを紹介します!!
ポイント①年齢・性別
バレエ発表会のプレゼント選びのポイントの一つ目は、プレゼントを渡す相手の年齢と性別を考慮することです。
年齢や性別に合ったものを選ぶことで喜んでもらえる可能性が大きくなります!
ポイント②サイズ・重さ
次に大事なのはプレゼントのサイズや大きさです。
バレエ発表会の当日の出演者は荷物が多いため、プレゼントが大きかったり重いと持って帰るのが困難になってしまいます。
そのため軽く、コンパクトなプレゼントは持ち帰りやすく喜ばれます。
ポイント③予算
気になるバレエ発表会のプレゼントの予算ですが、相場は大体1,500円〜3,000円となっています。
あまり高額なプレゼントはかえって相手に「何かお返しをしないと」と気を使わせてしまう場合も・・。
チケット代を負担してくれている場合はチケットのお値段を考慮してプレゼントを選ぶと良いでしょう。
ポイント④相手との関係性
プレゼントの予算について紹介しましたが、予算はプレゼントを渡す相手との関係性によっても変わってきます。
例えば、小学生の友達の場合は1500円程度までのぬいぐるみや筆記用具等、中高生の友達の場合は1500〜2500円程度のメイクポーチやレッグウォーマーといったバレエ用品等、先生には3000円〜5000円程度までのタオルや入浴剤などです。
プレゼントを渡す相手との関係性も考慮してみてくださいね!!
いつが正解?バレエの発表会プレゼントを渡す時のコツ

前述の通りバレエ発表会の当日の出演者は忙しく直接会えないことも多いです。
そういった時はどのようにプレゼントを渡せばいいのでしょうか?
バレエ発表会のプレゼントを渡す時のコツについて紹介します!!
プレゼントの渡し方
バレエ発表会のプレゼントを渡す機会は4つのパターンあります。
下記に詳しく解説していきますね!
出演者の保護者に渡す
出演者の保護者にプレゼントを渡す方法が一番確実に出演者本人にプレゼントが渡る方法です。
発表会当日は保護者もスタッフとして忙しくしている場合があるので事前に連絡をしておくとスムーズでしょう。
終演後に直接渡す
バレエの発表会では終演後に出演者がロビーなどに出て来ることがあります。
そういった場合には直接、プレゼントを手渡しすることができますね。
また、他にも「楽屋を尋ねる」、「会場の外で会う」方法があります。
しかし、「出演者が終演後にロビーに出てこない」、「楽屋へ訪れることは禁止」といった場合も多いので、直接手渡しするためには事前に確認が必要となります。
受付に預ける
直接会って手渡しできなさそうな時は受付やプレゼント専用の場所に預けます。
集まったプレゼントは、後ほどスタッフによって本人に手渡されます。
直接、会えない場合はこの方法が安心ですね。
自宅に送る
上記で紹介した2つのパターンが叶わない場合は、自宅に郵送することもできます。
送料はかかってしまいますが確実に渡すことができますね。
また、この場合は少し大きめのプレゼントも送れますし、「送る側」も「もらう側」も楽なパターンとなりそうです。
メッセージカードを添えて
バレエの発表会でプレゼントを渡す際には必ずメッセージカードを添えましょう。
バレエの発表会ではたくさんのプレゼントをいただくことがあります。
そういった場合にメッセージカードがないと誰からいただいたか分からないということも・・。
名前を書いたメッセージカードを添えることで誰からのプレゼントかすぐに認識できますね。
まとめ

どんなプレゼントも嬉しいものですが、個人の好みなどを考慮したプレゼントは特にもらって嬉しいものですよね。
また、コンパクトで軽いといった大きさや重さに配慮したプレゼントには思いやりも感じられます。
バレエの発表会へ招待された際にはプレゼントを用意して観にいってみてくださいね!
-
7.152025
【中級者向け】バレリーナのような足を目指そう!美しい筋肉の付け方を徹底解説!


バレリーナの足は細くて長くて本当に美しいですよね。
「一体、どのようなレッスンをすれば、バレリーナのような綺麗な足になれるのか」という疑問を抱いている人も多いでしょう。
バレエのレッスンを正しく行うことで綺麗な足になることは可能です。
今回はバレリーナの足が美しい秘密について解説します。
バレエ向きの足とは

ピーンと伸びた足が美しいバレリーナ。
どのようにして綺麗な足になるのでしょう。
もともと足の形がバレエに向いている人もいますが、もしそうでない場合でもバレエをすることは可能です。
正しいレッスンをすることでバレリーナのような足になれる可能性が、誰でもあります。
バレエに向いている足の形
一般的にバレエ向きの足は、まっすぐか少しX脚気味が良いとされています。
X脚すぎると膝を伸ばした際に膝に負担がかかってしまうので、X 脚ではない人より身体を上に引き上げる意識が必要です。
また、股関節から外側に開いている方がバレエはやりやすいでしょう。
しかし、これはバレエ学校が定めるバレエ向きの足です。
そのため、この条件が揃っていないからといってバレエを諦める必要はありません。
レッスンや足りない部分を補うトレーニング次第で、バレエをやる上で美しい足になることができます。
ただし、闇雲にレッスンをたくさんしても足は綺麗にはなりません。あくまでも正しいレッスンを行うことが重要です。
バレリーナの足が細い理由
バレリーナの足は適度に筋肉が付いていて、細く美しいですよね。
間違ったトレーニングは筋肉を外側につけてしまうなど足が太くなってしまう原因にもなりかねません。
まずは、バレリーナの足が細い理由を知っていきましょう。
筋肉を正しく使っている
普段の立ち方やレッスン中の姿勢で、「正しい筋肉を使う」、「力のかけ方を意識する」ことが重要です。
例えば、外側の筋肉に力をかけるといった、筋肉の使い方を間違うと足が太くなる原因となってしまいます。
レッスン後にきちんとケアしている
正しい力のかけ方で筋肉を使っていても、筋肉は使い続けると凝り固まります。
そうなると足が太く見えてしまう場合も。
バレリーナはレッスン後にストレッチやマッサージをすることで、むくみやこりを解消し足をケアしています。
レッスンのあとは足をほぐしてケアしましょう。
食事管理をしている
バレリーナは日々のレッスンに加えて食事管理も行なっています。
何も食べないというような極端なダイエットでは長続きせず、身体を壊してしまいますのでバランスの良い食事を摂ることがバレエを長く続ける秘訣です。
糖質や脂質が多い食べ物は脂肪になりやすいので、良質なタンパク質やビタミン(野菜や果物等)といった栄養素が取れる食事がベストです。
※糖質、脂質は重要な栄養素でもあります。炭水化物を抜くなど極端な食事制限はやめましょう。
バレエの基本アンディオールとは

バレエをする上で欠かすことができないのがアンディオールです。
バレエをしている間は常にアンディオールを意識する必要があります。
上手くできていない場合は足が太くなったり、踊りが美しく見えなかったりするので、正しく理解しておきましょう。
アンディオールの基本
下肢(股関節・膝関節・足関節の三大関節)が可能可動域範囲内で外旋している状態です。
外旋とは骨を外側にねじるような運動です。
また、つま先が外側を向くように回す動きを指します。
バレエではつま先だけでなく足の付け根である股関節、膝、足首を動く範囲で外側に回して足を使います。
この3つの関節が同じ方向を向いていないと、ねじれが生じ怪我につながってしまうので自分の外に向けられる範囲(可能可動域範囲内)で動かします。
アンディオールのための3つのポイント
アンディオールを正しく行うためにはコツがあります。
下記に正しくアンディオールするための3つのポイントを紹介します。
アンディオールの仕方がイマイチわからないという人は参考にしてみてください。
足裏の力を意識する
身体を支えているのは、ふくらはぎや太ももといった大きい筋肉だけではなく足裏の筋肉も大きな役割を持っています。
足裏から内もも、内ももからお尻のラインが1つになっていることでバレエの美しい足が実現されます。
足裏でしっかり床を感じ、足首、膝、股関節を外旋します。
内転筋の力を意識する
内転筋は股関節の付け根から太ももの内側、膝の内側にかけて走行する筋肉です。
前述の足裏の筋肉をしっかり意識することで、内転筋に伝わり足を綺麗に開く(アンディオール)することができます。
この時、むやみにふくらはぎや太ももに力を入れなくて大丈夫です。
足裏の力を螺旋状に足首、膝、股関節に伝えていくようなイメージをしてみましょう。
身体を引き上げるための腹筋力
上記で説明した動きをどんな時も意識するためには、身体を常に上に引き上げる必要があります。
身体を引き上げるために必要なのが腹筋です。
「足裏、内転筋、腹筋」の3つを意識することで正しくアンディオールをすることができます。
しかし、意識しすぎて力んでしまっては余計な力が筋肉にかかってしまい足が太くなる原因に・・。
アンディオールは「外側に開放する」とも説明されることがあります。
足にギュッと力を入れて力むのではなく力を外側に逃すことで足を開きつつリラックスした状態がベストです。
アンディオールのためのストレッチ
正しくアンディオールするためには股関節の柔軟性が必要です。
股関節が硬いと足の付け根から十分に開く意識ができません。
もし、今自分が股関節が硬く十分にアンディオールができていないと感じる場合は股関節のストレッチをしてみてください。
- 「股関節のストレッチ方法」
- 座った状態で膝を曲げて足裏を合わせます。
- お尻をしっかり床につけます。
- 両膝を床に近づけ、ゆっくりと押します
※最終的に両膝が床につくのを目標にしてみましょう。
※どこか痛い部分がある場合は様子を見ながらストレッチを行なってください。
正しい足のポジションを保つポイント

正しい足のポジションができると、美しい踊りに繋がります。
基本のポジションについて紹介しましたが、今度は正しいポジションを保つためのポイントについて紹介します。
体の重心
アンディオールの説明でも足裏の力が重要であるといいましたが、レッスン、踊りと全体を通して足裏で床を意識することは重要です。
足裏には3箇所意識すると良い箇所があります。
- 親指の付け根
- 小指の付け根
- かかと
この3箇所が床にしっかりと付いているか意識をしながらポジションをとってみましょう。
例えば、親指側に重心が乗っていると小指側が浮いてしまいますし、逆もしかりです。
足裏がしっかり感じられる位置を探してみましょう。
上半身
上半身は一見、足のポジションやアンディオールとは関係のないように思えますが上半身を引き上げることがレッスンや踊る上でとても大切です。
上半身を引き上げることで、足が動かしやすくなり、足への負担が軽減されます。
身体の中心に1本の糸が通っているイメージで、その糸が上から引っ張られていると想像してみてください。
その糸がたゆまないよう意識すると身体が上に引き上がりやすくなります。
身体を引き上げる際は、肩が上がりやすくなるので耳と肩を離して首を長く保つよう意識してみましょう。
まとめ

バレリーナの足についてのお話でしたが、身体は足の先から頭まで繋がっていますので足を動かす際も上半身にも意識が必要です。
バレエは様々な決まりごとが多いようにも思えますが、1つ1つ理解し意識することで美しい踊りにも繋がります。
また、バレリーナの中にはもともと恵まれた容姿の人もいますが、そういった人でさえレッスンやトレーニングをして美しい足を保っています。
もし、自分の容姿が恵まれていないと感じる場合でも正しい知識を持ち理解することでバレエを踊ることができます。
身体を引き上げたり、アンディオールはなかなか初めは意識するのが難しいかもしれませんが、無意識でもできるよう頑張ってみてください。
きっと美しい足、踊りに繋がりますよ。
-
7.152025
花のワルツってどんな曲?バレエの有名な曲について知ろう!!


バレエを習っていなくても、題名を知らなくても一度は聞いたことがありそうな曲『花のワルツ』
『花のワルツ』はバレエ演目である『くるみ割り人形』や『眠れる森の美女』に登場するワルツ曲として有名です。
今回は2曲の『花のワルツ』と他のバレエの有名曲も併せて紹介していきます。
発表会で踊ることになった、バレエの公演をみに行くことになった方など参考にしてみてくださいね!!
バレエのワルツと言えばこの曲!『くるみ割り人形』の花のワルツとは

バレエのワルツとして有名な『花のワルツ』はバレエ演目『くるみ割り人形』に登場します。
『くるみ割り人形』についてや、『花のワルツ』はどんなシーンで登場し、どんな衣装なのかについて紹介します。
『くるみ割り人形』とは
クラシックバレエの有名な演目の一つである『くるみ割り人形』
登場する曲や踊りは、どれも有名ですが『花のワルツ』もその一つです。
そんな、『くるみ割り人形』について詳しくみていきましょう!!
『くるみ割り人形』概要
『くるみ割り人形』はピョートル・チャイコフスキーが作曲したバレエ音楽で、その楽曲を用いた、全2幕のバレエ作品です。
チャイコフスキーが手掛けた最後のバレエ音楽で、バレエの公演は1892年にサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で初演されました。
『くるみ割り人形』の原作はドイツのE.T.A.ホフマンによる童話『くるみ割り人形とねずみの王様』を、アレクサンドル・デュマ・ペールがフランス語に翻案した『はしばみ割り物語』です。
クリスマスにちなんだ作品なので、毎年クリスマス・シーズンには世界中で上演されています。
クラシック・バレエを代表する作品の1つで、同じくチャイコフスキーが作曲した『白鳥の湖』『眠れる森の美女』と共に「3大バレエ」となっています。
『くるみ割り人形』あらすじ
クリスマスイヴに不思議な魅力のあるくるみ割り人形をプレゼントされたクララ。
その晩に現れた悪いネズミ王様をくるみ割り人形と共に戦い倒します。
そのお礼にと、くるみ割り人形はクララをお菓子の国へと連れ出します。
お菓子の国で歓迎されたクララは、様々な国のお菓子たちに歓迎され夢のような踊りを見せてもらいます。
金平糖の精と王子による華やかなグラン・パ・ド・ドゥで華やかにクライマックスを迎えます。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、夢から覚めたクララはくるみ割り人形を胸に抱きしめます。
※上演される国やバレエ団によってストーリー設定や結末が異なる場合があります。
『くるみ割り人形・花のワルツ』〜シーン〜
『花のワルツ』は『くるみ割り人形』の第2幕に登場します。
お菓子の国に迎えられたクララは、金平糖の精から手厚い歓迎を受けます。
その際に金平糖の精と※コールドとで、繰り広げられるワルツが『花のワルツ』です。
また、『花のワルツ』は金平糖の精と王子による華やかなグラン・パ・ド・ドゥの前に踊られるバーションもあります。
※コールド・・・コールドバレエ(corps de ballet)とは、バレエの群舞や、バレエ団のダンサーで構成される集団を指します。
『くるみ割り人形・花のワルツ』〜衣装〜
『くるみ割り人形』の『花のワルツ』の衣装は、妖精役などに多く着用されるロマンティック・チュチュであることが多いです。
実は『花のワルツ』の花はマリーゴールドであると言われています。
マリーゴールドは、悲劇的な死を遂げた製作者の愛娘の魂に違いないと考えた製作者たちが、華やかなワルツのイメージとして選んだ花だそう。
初演の『花のワルツ』では、製作者たちの弔いの気持ちが込められた黄金の花が舞台を彩りました。
現代では初演のイメージに近い、オレンジやゴールドに加えてホワイト(ゴールド刺繍入り等)やピンクといった様々な色の衣装が使用されています。
衣装も上演する国やバレエ団によっても異なります。
『花のワルツ』はこれから、お菓子の国で繰り広げられる楽しい時間を導くような華やかなワルツです。
そのワルツにふさわしい衣装となっていますので、衣装にも注目してみてくださいね!
有名なワルツはもう一曲!『眠れる森の美女』の花のワルツ

『くるみ割り人形』とともに有名な『花のワルツ』は『眠れる森の美女』にも登場します。
『眠れる森の美女』の『花のワルツ』はディズニー映画の『眠れる森の美女』にも登場するので、聞いたことがあるという方も多いかもしれません。
バレエ演目である『眠れる森の美女』についてや『花のワルツ』はどんなシーンで登場し、どんな衣装なのかについて紹介します。
『眠れる森の美女』とは
バレエ演目『眠れる森の美女』はチャイコフスキーが作曲した、『くるみ割り人形』と『白鳥の湖』と共に3大バレエの1つです。
作品の中には多くの有名なヴァリエーションが登場し、発表会やコンクールなどでも見かける機会が多いです。
『眠れる森の美女』の概要やあらすじについてみていきましょう!
『眠れる森の美女』概要
『眠れる森の美女』には『くるみ割り人形』と同様にチャイコフスキーが作曲したバレエ音楽が使用されています。
原作はシャルル・ペローによる昔話『眠れる森の美女』で、1890年にマリウス・プティパの振り付けによってサンクトペテルブルク、マリインスキー劇場にて初演されました。
現在もクラシックバレエを代表する作品として世界中で上演されています。
『眠れる森の美女』あらすじ
悪の精であるカラボスにかけられた呪いによって、100年の眠りにつくことになったオーロラ姫。
王子のキスによって100年の眠りから覚めるという、王道のおとぎ話です。
オーロラ姫と王子の結婚式には宝石やおとぎの国から豪華なゲストたちがお祝いにやってきます。
『眠れる森の美女・花のワルツ』〜シーン〜
『眠れる森の美女』で『花のワルツ』が登場するのは第1幕のオーロラ姫の16歳の誕生日を祝うパーティーのシーンです。
美しいワルツ曲にのって踊られるこのシーンは幸福感に満ちた雰囲気となっています。
※バレエ団によっては『ガーランドの踊り(ワルツ)』・『花輪のワルツ』と称されている場合もあります。
『眠れる森の美女・花のワルツ』〜衣装
『くるみ割り人形』の『花のワルツ』と同様にピンクのロマンティック・チュチュであることが多いです。
しかし、上演される国やバレエ団によっては設定がオーロラ姫の16歳の誕生日を祝うパーティーに招かれた村人であるバーションもあり、その際には村人の衣装を身にまとっています。
『ガーランドの踊り(ワルツ)』・『花輪のワルツ』と称されることもあるように、花のアーチを持って踊るバージョンもあります。
他にもたくさん!一度は聞いたことがあるバレエの有名曲

前述の『花のワルツ』以外にもバレエの有名な曲はたくさんあります!
一度は耳にしたことがあるバレエの有名曲を紹介します。
くるみ割り人形』の有名曲
『くるみ割り人形』には『花のワルツ』以外にも有名な曲があります。
中には映画やCMに起用されているものも。
『くるみ割り人形』の有名な曲は下記の通りです。
トレパック
『くるみ割り人形』のお菓子の国で踊られるお菓子の一つ『トレパック』
『トレパック』はロシアの大麦糖のねじられた飴菓子のことで、ロシアの踊りとも称されます。
この曲は映画『ホームアローン』のBGMでも使用され、クリスマスのストーリーであることから『くるみ割り人形』を知らずとも思い出す人も多いでしょう。
あし笛の踊り
『くるみ割り人形』のお菓子の国で踊られるお菓子の一つである『あし笛の踊り』
あし笛はフランスのミルリトンという伝統菓子のことです。
この曲はソフトバンクモバイルのCM「ホワイト家族シリーズ」で登場し、『くるみ割り人形』を知らない人でも一度は聞いたことがあるというほど有名になりました。
『白鳥の湖』の有名曲
『くるみ割り人形』、『眠れる森の美女』と共に3大バレエの一つである『白鳥の湖』
バレエといえば『白鳥の湖』を思い浮かべる人も多いでしょう。
そんな『白鳥の湖』にも有名曲がたくさんありますので、特に有名な2曲を紹介します。
情景
『白鳥の湖』の最も有名な曲といっても過言ではないのが『情景』です。
実は情景と言ってもたくさんありますが組曲にある情景は第2幕の前奏曲に当たります。
非常に美しく有名なメロディで白鳥の湖といえばこの曲。
この曲を聴けば誰もが『白鳥の湖』だと分かるでしょう。
四羽の白鳥の踊り
『白鳥の湖』第2幕の『白鳥たちの踊り』の中に含まれている『四羽の白鳥』
リズミカルな伴奏とオーボエのメロディが印象的です。
踊りの振り付けは手をつないだ四羽の白鳥が横移動する様子が特徴的な曲として知られています。
まとめ

『くるみ割り人形』と『眠れる森の美女』に登場する『花のワルツ』はどちらも幸福感に満ち溢れた華やかなワルツとなっています。
上演される国やバレエ団によっても、登場シーンや設定、衣装が異なる場合があり、そのことも含めてバレエ作品を見る楽しみでもありますね。
バレエ公演を観る際には、バレエの有名な曲にも注目してみてくださいね!!
-
7.152025
【小中学生編】新国立劇場バレエ団付属のバレエ研修所について徹底解説!!


日本で唯一、公演のための専用劇場を持つバレエ団である新国立劇場バレエ団。
日本を代表するバレエ団であり、どうしたら団員になれるのか気になる方も多いでしょう。
今回は新国立劇場バレエ団の歴史やオーディション、また付属のバレエ研修所についても紹介します。
新国立劇場バレエ団について

新国立劇場を専属劇場とするバレエ団です。
日本の文化政策の一環として活動している日本を代表するバレエ団で、日本全国から優秀なダンサーが揃っています。
2020年からは長年、英国でプリンシパルダンサーとして活躍した吉田都さんを芸術監督に迎え、さらなる飛躍が期待されています。
古典バレエのみならず「アラジン」や「不思議の国のアリス」といった他のバレエ団では見ることができない演目を上演するなど、人気の高いバレエ団の1つです。
公式HP 新国立劇場バレエ団
新国立劇場バレエ団の団員や演目について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください↓
日本で唯一!国立の劇場所属 新国立劇場バレエ団について知ろう
新国立劇場バレエ団付属のバレエ研修所

新国立劇場バレエ団には付属のバレエ研修所があります。
バレエ団への入団を志している方や本格的なバレエのレッスンを受けたい方にはオススメの場所となっています。
バレエ研究所の概要や募集要項について紹介します。
バレエ研修所の概要
2001年4月にバレエ研修所は、プロを目指す若いダンサーのために、開設されました。
研修場所は主に西新宿の芸能花伝舎及び新宿村スタジオと新国立劇場です。
研修期間中にダンサーとして必要な技能を幅広く磨き、多様な講義を通じて知識や教養を身につけることを目的としています。
年2回の研修公演や海外で活躍する日本人ダンサーを迎えて上演する「バレエ・アステラス」、新国立劇場バレエ団公演など、新国立劇場の舞台で実習を行っています。
また、バレエ研修所では、海外のバレエ学校フェスティバルへの参加や、海外のバレエ学校の招聘による国際交流も積極的に行います。
さらに2018年より新国立劇場若手バレエダンサー育成支援事業「ANAスカラシップ」による海外研修が開始され、貴重な経験をしています。
研修所が輩出したダンサーは、新国立劇場バレエ団の主役級をはじめとする第一線の舞台で活躍しています。
研修生の募集要項
2024年の募集要項は下記の通りです。
本科前期課程(15歳または16歳)
人数 男女あわせて8名程度(予定)
研修期間 2024年4月から原則4年間[原則として、月曜日から金曜日の10:00~17:30]
応募資格
・プロフェッショナルなバレエダンサーとしての舞台活動を目指していること。
・これまでのバレエトレーニングでバレエの基礎を有していること。
・2024年4月1日時点で、15歳または16歳であること。
・義務教育課程(中学校)を卒業、もしくは卒業見込みの者。
・提携通信制高校あり。
・家族・親族の管理の下、研修(通学)可能なことが望ましい。
・外国籍の場合、日本語が理解できること、及び研修期間中の在留資格が取得できること。
本科後期課程(17歳以上19歳以下)
人数 男女あわせて12名程度(予定)
研修期間
2024年4月から原則2年間[原則として、月曜日から金曜日の10:00~17:30]
2年間の研修の後、専科(2026年度開始予定)に進む者は最長3年間
応募資格
・プロフェッショナルなバレエダンサーとしての舞台活動を目指していること。
・バレエ学校等の養成課程を修了していること、またはそれと同等の実力を有すること。
・2024年4月1日時点で、17歳以上19歳以下であること。※提携通信制高校あり。
・外国籍の場合、日本語が理解できること、及び研修期間中の在留資格が取得できること。
※2025年度入所生より「本科後期」の受験資格は17~18歳に変更となります。
注意事項
バレエ研修所の研修は、原則として平日10時から17時30分までです。
そのため全日制の他の学校等との両立はできません。
また舞台実習等が、平日夜、土・日に実施される場合があります。
原則として研修期間中は研修に専念するため、芸能活動を含む他の活動は、控える必要があります。ジュニアクラスについて
バレエ研修所には研修所に入る前にジュニアクラスも開講されています。
バレエ研修所のジュニアクラスについて紹介します。
ジュニアクラスの概要
バレエ研修所では、2023年秋からジュニアクラスが新設されました。
プロをめざすジュニアの心技体づくりに大切な基礎強化として、バレエ研修所入所前に学べるクラスとなっています。
バレエ研修所入所年齢相当まで、しっかりと基礎を学ぶことができ、週2回のクラスレッスンのほか、バレエ研修所公演の鑑賞や舞台稽古見学等も予定されています。
ジュニアクラスの募集要項
募集人数 10名程度
研修日と時間 2024年度は9月下旬より開講予定。
月曜夜クラスと金曜夜クラス、または、月曜夜クラスと土曜朝クラスの原則週2回(予定)
[平日夜クラス18:30~20:20、土曜朝クラス10:30~12:20]
受講対象者
・2025年4月1日時点で13歳または14歳の方
・新国立劇場バレエ研修所 夏の特別バレエレッスンを受講した方のうち、ジュニアクラスの受講を希望する方(定員あり。夏の特別バレエレッスンにて選考の上決定。)
受講条件
・本ジュニアクラス以外に、週に2回以上レッスンできるバレエ学校(教室)に所属していること
・所属バレエ学校(教室)の先生から、新国立劇場バレエ研修所ジュニアクラスの受講許可を受けていること
備考
・バレエ研修所の公演鑑賞や、舞台稽古見学などの特典があります。
・ジュニアクラスを受講している方は、バレエ研修所選考試験の書類審査(書類確認)が免除されます。まとめ

新国立劇場バレエ団付属のバレエ研修所では13歳から受講可能なジュニアクラスも開講するなど若手の育成にも力を入れています。
新国立劇場バレエ団を目指している方や本格的なレッスンを若いうちから受けたい方などは、ぜひクラスの受講を検討してみてくださいね。
-
7.152025
人気のヴァリエーション!キュートなキューピットについて知ろう!!


キューピットは発表会やコンクールで目にする機会の多いヴァリエーションの1つです。
見た目も可愛く、人気のあるヴァリエーションなので、踊ることを目標にしている方も多いかもしれませんね。
今回はキューピットが登場する演目やヴァリエーションの振り付け、難易度について紹介します。
キューピットを踊ってみたいという方は参考にしてみてくださいね!!
キューピットの登場する演目は!?その役柄についても徹底解説!!

コンクールや発表会で見かけることの多いキューピット。
しかし、一体なんの演目なのか、具体的にどんな役割を果たしている役柄なのか?意外と知らない場合も。
キューピットが登場する演目や役柄とその役割について紹介します!
『ドン・キホーテ』について
『ドン・キホーテ』はスペインの小説が元となっているクラシックバレエ作品。
タイトルにあるドン・キホーテも登場しますが、お話のメインは主人公のキトリとバジルが結婚するまでのドタバタ劇です。
ドン・キホーテはお話のメインではないものの、中世の騎士になりきっているという少しヘンテコな役です。
そんなドン・キホーテはお話の所々で、やらかしてくれます(笑)
ダイナミックでユニークなキャラクターたちが多く登場し、見終わったあとは、明るくハッピーな気持ちになれること間違いのない作品です。
『ドン・キホーテ』においてキューピットの役割とは
前述のバレエ演目『ドン・キホーテ』の第2幕「夢の場」に登場するキューピット。
キューピットといえば一般的には「恋のキューピット」とも言われるように恋愛を成就させるイメージがありますね。
『ドン・キホーテ』の中のキューピットの役割は、ドン・キホーテの夢の中の案内人のような役割を持っています。
風車を敵と勘違いし、立ち向かおうとして気絶してしまったドン・キホーテが夢の中で理想的な女性であるドルネシア姫と出会います。
その夢の中でドン・キホーテを導くのがキューピットなんです。
キューピットのヴァリエーションを詳しく知ろう!!

可愛いイメージのあるキューピットのバリエーションに憧れている方も多いですよね。
他のヴァリエーションに比べ、キャラクター性の高い役柄で個性が発揮できるヴァリエーションともいえます。
キューピットの振り付けや音楽、衣装などについて紹介します。
キューピットのヴァリエーションを踊ることを検討している方は参考にしてみてくださいね!
キューピットの音楽
比較的、難易度の高くないイメージのあるキューピットですが、実は音楽はアップテンポで短いので見た目よりも難しいのが事実です。
早いテンポの中でもしっかり膝やつま先を伸ばすといった足さばきやキューピットになりきることが重要です。
キューピットの振り付け
キューピットの音楽は前述の通り、アップテンポです。
振り付けは、その音楽に合わせ細かい足さばき、素早い移動、回転(移動しながらも!)、静止のポーズなどが多いヴァリエーションです。
また、ただ踊るだけでなくキャラクター性の高い役柄なので、キューピットの可愛さ、お茶目さも表現する必要があります。
素早い動きが多いので、お子さまや大人の方では小柄な方が踊りやすいでしょう。
テクニックに関しても難易度は低いものの、回転しながら移動するといったテクニックが必要です。
そのため、小柄で素早い動きが得意、回転が得意な方には向いているヴァリエーションといえるでしょう。
キューピットの衣装
キューピットは『ドン・キホーテ』第2幕の夢の場に登場します。
夢の場といえば幻想的な雰囲気ですよね。
そんな、夢の場に登場するキューピットの衣装は白く、丈の短いものが一般的です。
また、くるくるヘアーが可愛いカツラを被ることも多いです。
バレエの他のプリンセスや妖精といったチュチュを着る役柄とは違うキューピットは衣装の面からも個性的なキャラクターであることがわかりますね。
キューピットは初心者向け?初心者向けのヴァリエーション紹介

トゥシューズを履いたら憧れのヴァリエーションを踊ってみたいですよね。
トゥシューズでヴァリエーションデビューする方にオススメの初心者も踊れる、難易度の低めのヴァリエーションを紹介します。
キューピット
今回紹介したキューピットの踊りはキャラクター性が高い個性的な踊りでお子様からも人気があるヴァリエーションです。
振り付けの難易度も低めで、踊りの時間も短いです。
そのため初心者も挑戦しやすいヴァリエーションとなっていますが、曲のテンポが早いのでしっかり音に乗ることが重要です。
フロリナ王女
バレエ演目『眠れる森の美女』第3幕に登場するブルーバードと共に登場するのがフロリナ王女です。
エシャッペやパッセといった初歩的な動きが多いので難易度は低めとなっています。
しかしながら、初歩的なステップだからこそ膝やつま先を伸ばすといったことに目がいきます。
また、美しく軽やかに表現できないと単調な踊りになってしまうので表現力も必要なヴァリエーションです。
オーロラ姫(第3幕)
『眠れる森の美女』第3幕に登場するオーロラ姫のヴァリエーションです。
発表会やコンクールでも人気のヴァリエーションで、定番で有名なのでコンクール初挑戦の方も挑戦しやすいです。
難易度は低めなものの、最後にピケで一周するので最後まで体力のいるヴァリエーションとなっています。
まとめ

コンクールで見かける場合も小柄で身軽そうなキューピットが多い気がしますね。
小学校高学年といったトウシューズを履いてヴァリエーションデビューで踊るという方も多いようです。
キュートでお茶目なキューピットを踊ってみたいという方は、挑戦してみてくださいね!!
-
7.152025
信じていれば夢は叶う!!夢と魔法がつまったバレエ作品『シンデレラ』の全幕を徹底解説!


ディズニーのアニメーション映画が有名で人気のある『シンデレラ』ですが、バレエ版の『シンデレラ』も人気があり、様々なバレエ団が公演を行なっています。
バレエ教室の発表会でも演目に選ばれることも多いですよね。
今回はそんな『シンデレラ』のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションなどを紹介します。
バレエ版『シンデレラ』の全幕公演を観てみたい方や、これから『シンデレラ』の演目を踊る予定のある方などは参考にしてみてくださいね!!
『シンデレラ』について知ろう!!

よく知られている童話『シンデレラ』が元になっていますが、同じく有名なディズニー作品とは異なる人物も登場するバレエ版『シンデレラ』
そんな、バレエ版『シンデレラ』の概要や登場人物を紹介します。
『シンデレラ』の概要
『シンデレラ』(英語: Cinderella)は、ロシアの作曲家であるセルゲイ・プロコフィエフが作曲したバレエ音楽です。
また、そのバレエ音楽を用いたバレエ作品となっています。
物語の元となっているのはフランスの詩人シャルル・ペローの童話集の中の童話『シンデレラ』です。
『シンデレラ』の初演が行われたのは、1945年11月21日、モスクワのボリショイ劇場。
ディズニーのアニメーション映画『シンデレラ』が公開されたのは1952年なので実はバレエ版の方が早く世に出ていたのですね。
初演の際の台本はニコライ・ヴォルコフ、振付はロスチスラフ・ザハロフ、主演のシンデレラ役はガリーナ・ウラノワが演じました。
初演は大成功し、作曲者のプロコフィエフは1946年にソビエト連邦における国家最高賞である、スターリン賞を受賞しました。
登場人物
『シンデレラ』には個性豊かな人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・シンデレラ…物語の主人公、継母・義姉らと暮らしている
・継母…シンデレラと暮らすいじわるな継母、シンデレラを召使いのようにこき使っている
・2人の義姉…継母の実娘、継母とともにシンデレラをいじめる
・仙女…シンデレラに魔法をかけて助けてくれる魔法使い
・王子…城の王子様
・四季の精…仙女とともに現れる春・夏・秋・冬の精、それぞれの季節を踊りで表現する
四季の精といった、よく知られているディズニー版にはない登場人物も登場します。
ディズニー版の魔法使いはバレエ版では仙女にあたります。
『シンデレラ』第1幕

第1幕ではシンデレラの置かれている状況や、シンデレラの心情などが描かれています。
バレエ版『シンデレラ』のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションを紹介します。
『シンデレラ』第1幕のあらすじ
バレエ版『シンデレラ』はシンデレラが住む家から始まります。
そこにはシンデレラを召使いのように扱う継母や義理の姉たちも一緒に暮らしていています。
いつものようにシンデレラは、掃除や家事といった雑用を命じられています。
一方で、継母や義理の姉たちはお城で開かれる舞踏会の準備で大忙し。
ダンスのレッスンや舞踏会へ着ていくドレスを仕立てたり、シンデレラには見向きもしないのです。
そこへ、物乞いをする老婆が現れ、シンデレラはその老婆に親切に接しパンを恵んであげました。
準備を終えた継母と義理の姉たちは舞踏会へと出発。しかし、舞踏会へ着ていくためのドレスがないシンデレラは一人ぼっちで留守番です。
留守番中にシンデレラは、自分が舞踏会で踊っている様子を想像し1人で踊ります。
その時です!先ほどパンを恵んであげた老婆が美しい仙女となって現れたのです!!
仙女は親切に接し、パンをくれたお礼にと四季の贈り物をします。
四季の精たちは春・夏・秋・冬とそれぞれの美しい踊りをシンデレラに披露します。
そして、最後に仙女が魔法の杖を一振りした、その時、シンデレラの着ていた洋服はたちまち美しいドレスに変わり、カボチャは馬車に変身します。
仙女は「この魔法は12時には解けてしまいます。12時の鐘がなる前には必ず帰りなさい。」とシンデレラに告げます。
そして、シンデレラはお城の舞踏会へと旅立ちます。
『シンデレラ』第1幕のみどころ
継母や義理の姉たちから召使いのように扱われているシンデレラ。
シンデレラの義理の姉役は男性がトゥシューズを履いてコミカルな演技を見せるという演出もあり、そのコミカルっぷりを楽しみにしている人も多いほどです。
継母や義理の姉たちから仲間外れにされ舞踏会へも置いていかれてしまうシンデレラ。
1人でほうきを相手に舞踏会を夢見て踊りだします。
そんな、健気なシンデレラの様子がわかるのが1幕です。
このような状況であっても決して卑屈にならず、老婆に親切に接することができるシンデレラの心の美しさがわかるシーンです。
『シンデレラ』第1幕のヴァリエーション
バレエ版『シンデレラ』にはコンクールで使用されるヴァリエーションはあまりないものの、発表会や小作品集などではよく見かける有名なものが多いです。
『シンデレラ』第1幕に登場するヴァリエーション一覧は下記の通りです。
・シンデレラのソロ(ほうきで踊るシーン)
・四季(春・夏・秋・冬)それぞれのヴァリエーション
ヴァリエーションではありませんが、シンデレラが仙女や四季の精たちと踊る、賑やかなワルツも有名なシーンです。
見逃さないようにチェックしましょう!!
『シンデレラ』第2幕

シンデレラが憧れていた舞踏会に到着!
王子と出会うことはできるのでしょうか!?
バレエ版『シンデレラ』第2幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションを紹介します。
『シンデレラ』第2幕のあらすじ
お城では華やかな舞踏会が繰り広げられています。
そこへ、仙女の魔法のおかげで美しく変身を遂げたシンデレラが登場します。
あまりの美しさに継母や義理の姉はシンデレラだということに気がつきません。
それどころか、舞踏会に来ていたいた人たちもシンデレラの美しさに見惚れています。
そして、シンデレラと王子は出会い、お互いに一目見た瞬間から恋に落ちます。
王子はシンデレラに踊りを申し込み、2人は美しいパ・ド・ドゥを踊ります。
シンデレラが1人、留守番をしていた際に夢見ていた王子との踊りが現実に叶った瞬間でした。シンデレラは仙女からの忠告を忘れ、王子との踊りに夢中になってしまいます。
そして、12時の鐘がなり始めます。
魔法が解けそうになり慌ててお城を後にするシンデレラは履いていたガラスの靴を片方落としてしまいます。
王子は、突然去ってしまったシンデレラの残されたガラスの靴を胸に、シンデレラを必ず探し出す決意をするのでした。
『シンデレラ』第2幕のみどころ
第2幕はとにかく華やかな舞踏会の様子が魅力です。
一人ぼっちで留守番をしていた際に夢見ていた、舞踏会での王子との踊りが、現実に叶った瞬間は見ている方も感動してしまいますね!!
シンデレラと王子のパ・ド・ドゥも見逃し厳禁です!
『シンデレラ』第2幕のヴァリエーション
一番のみどころといっていい程、美しい王子とシンデレラのパ・ド・ドゥ。
下記が『シンデレラ』第2幕に登場するヴァリエーション一覧です。
・シンデレラのヴァリエーション
・王子にヴァリエーション
第2幕のシンデレラのヴァリエーションは緩急のある美しいメロディーが特徴的です。
美しいシンデレラの様子が描かれていますが、美しいだけでなくテクニックの難易度が高いことでも知られています。
長さも2分近くあるので、主役にふさわしい難易度の高い踊りとなっています。
『シンデレラ』第3幕

ガラスの靴を残しお城を後にした、シンデレラ。
王子はシンデレラを見つけ出すことができるのでしょうか!?
バレエ版『シンデレラ』第3幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションを紹介します。
『シンデレラ』第3幕のあらすじ
シンデレラが残していったガラスの靴を手に、様々な国へ出かけシンデレラを探す王子。
ついにシンデレラの家に王子がやって来ますが、謙虚なシンデレラはガラスの靴の持ち主が自分であることを言いだせません。
そんなシンデレラをよそに、王子の結婚相手になりたい欲深い義理の姉たちは我先にとガラスの靴が自分のものであると主張します。
そして、代わる代わるガラスの靴を履こうとしましたが一向に履けません。
無理やり足をねじ込もうとする義理の姉たちを止めようとシンデレラが動いた、その時!
シンデレラのポケットからもう片方のガラスの靴がこぼれ落ちます。
舞踏会の時のような美しいドレスではなく、みすぼらしい格好をしていたシンデレラですが、王子はシンデレラに気づき舞踏会で恋に落ちた女性であることを確信します。
そして、2人は手を取り、めでたく結婚するのでした。
『シンデレラ』第3幕のみどころ
魔法が解けてしまったシンデレラに王子が気づくことができるかも重要なシーンですが、
ガラスの靴を必死に履こうとする義理の姉たちのコミカルな演技も、1幕に引き続き隠れたみどころの1つです(笑)
『シンデレラ』第3幕のヴァリエーション
バレエ版『シンデレラ』第3幕ではヴァリエーションはないものの、王子が各国をガラスの靴を手にシンデレラを探す際に出会う各国の踊りが披露されます。
・東洋の踊り
・シンデレラと王子のワルツ
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

バレエ版『シンデレラ』はよく知られている童謡やディズニー版と同じように幸せな結末を迎える場合が多いです。
信じていれば夢は叶うと教えてくれる『シンデレラ』の舞台には勇気をもらえるはず!
人気のある演目なので『シンデレラ』を上演するバレエ団も多いです。
全幕公演を見る機会があれば、ぜひ足を運んでみてくださいね!!
-
7.152025
ロマンティク・バレエの代表作!「ジゼル」の全幕を徹底解説!


パリ・オペラ座にて初演されたロマンティック・バレエの代表作『ジゼル』。
現在では世界中で上演されているバレエ作品です。
死後の世界が描かれるなど衝撃的な設定ですが、幻想的な世界観は観るものを引き込みます。
今回は『ジゼル』のあらすじやみどころを徹底解説します!
『ジゼル』について

『ジゼル』は1841年にパリ・オペラ座で初演されました。
『ジゼル』を発案し構想を考えたのは、詩人で作家でもあるテオフィル・ゴーティエです。
舞踊評論家でもあったゴーティエは、ハインリヒ・ハイネの著作『ドイツ論』に登場する民間伝承に着想を得て、バレエの台本を書こうと考えました。
その民間伝承の内容は「結婚前に死んだ若い女たちが「ウィリ」という幽霊になり、生前手に入らなかったダンスの喜びを味わうために若い男を捕まえて死ぬまで踊らせる」というものでした。
パリ・オペラ座での初演が成功を収め、ミラノ・スカラ座(イタリア)やニューヨークなどで上演されました。
パリ・オペラ座での上演が途絶えたのちはロシアで継承されるなど、現在まで語り継がれロマンティック・バレエの代表作となっています。
※ロマンティックバレエとは・・・文学・芸術において流行したロマン主義の影響を受けて1830年代〜1840 年代に最盛期を迎えたバレエのスタイル及び作品のことです。
登場人物
『ジゼル』には数々の魅力的な人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・ジゼル (村娘)
・アルブレヒト(身分を隠して村人を装っているが実は公爵)
・バティルド(アルブレヒトの婚約者)
・ヒラリオン(森番の青年でジゼルに想いをよせている)
・クルランド大公
・ベルト(ジゼルの母親)
・ミルタ(妖精ウィリの女王)『ジゼル』全2幕

『ジゼル』は全2幕と他のバレエ作品に比べ短いように思いますが、第1幕は村で開催されているブドウの収穫祭の様子、第2幕は精霊ウィリたちが登場する死後の世界が表現されるなど他のバレエ作品にはない雰囲気を味わうことができる作品です。
幕ごとのあらすじやみどころを紹介していきますので、これから『ジゼル』を観られる方は参考にしてみてくださいね。
『ジゼル』第1幕
『ジゼル』第1幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
舞台は中世ドイツのとある村。
病弱ながら踊りが好きなジゼルはアルブレヒトと恋人同士。
しかし、アルブレヒトは身分を偽っており、本当は公爵という身分です。
ジゼルに想いをよせている森番のヒラリオンはアルブレヒトを疑い、その正体に疑念を抱いています。
村ではブドウの収穫祭が行われ、収穫祭の女王にジゼルが選ばれジゼルは村人たちと楽しそうに踊ります。
病弱なジゼルを案じたベルト(ジゼルの母)はジゼルに「踊りに夢中になっていると、死後に精霊ウィリとなって踊り続けることになってしまう」と伝説を語ります。
そして、クルランド大公とその娘のバティルドが狩りのために村を訪れました。
そこへヒラリオンが現れアルブレヒトは公爵であり、バティルドの婚約者であることも暴露してしまいます。
真実を知ったジゼルはショックのあまり、正気を失い命を絶ってしまいます。
- 《みどころ》
病弱ながら健気に踊るジゼルの姿が印象的です。
しかし、第1幕最大のみどころはアルビレヒトに婚約者がいることを知ったジゼルの「狂乱の場」です。
実はこの「狂乱の場」では踊りの振り付けはなく、ジゼル役のダンサーの演技が重要な場面。
この場面では胸が痛くなる方や、ジゼルが命を落としてしまう場面では涙するという方も多いようです・・。
- 《ヴァリエーション》
・ペザントのヴァリエーション(収穫を祝う踊りで「ペザント」とは農民を意味します)
・ジゼルのヴァリエーション
・アルブレヒトのヴァリエーション
『ジゼル』第2幕
『ジゼル』第2幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
《あらすじ》
ジゼルのお墓がある森の夜。
女王ミルタが率いるウィリ(結婚を前にして死んでしまった若い乙女たちの精霊)たちが現れます。
ジゼルはお墓から呼び出されウィリたちに迎え入れられます。
そこへ、ヒラリオンとアルブレヒトはジゼルのお墓に現れます。
ウィリたちに捕まってしまったヒラリオンは踊らされた上に命を落としてしまいます。
女王ミルタの命令によりアルブレヒトも踊らされることに・・。
しかし、ジゼルはアルブレヒトの命を守ろうとかばいます。
やがて夜が明けて朝の鐘が鳴り響くと、ウィリたちとジゼルは姿を消します。
永遠の別れを告げ消え去ったジゼルのお墓の前にアルブレヒトは取り残されてしまいます。
《みどころ》
ウィリの女王であるミルタのソロは人間ではないことを思わせる振り付けとなっており、圧巻の存在感を放っています。
また、ウィリたちの踊りは精霊として個性を持たない設定であるため立ち位置、脚を上げる角度、顔の向きなど、全ての動きをぴったりそろえる必要があります。
一糸乱れぬウィリのコールド(群舞)は『ジゼル』のみどころの一つです。
また、ジゼルとアルブレヒトのパ・ド・ドゥは死後の世界であることから重量を感じさせないリフトがウィリとなってしまったジゼルを表しています。
ミルタやウィリたちからアルブレヒトを守ろうとするジゼルの姿も涙を誘います。
《ヴァリエーション》
・ウィリの女王ミルタのソロ(厳密にはヴァリエーションではなくソロ)
・ジゼルのヴァリエーション
・アルブレヒトのヴァリエーションバレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

ペザントやジゼルの踊りは発表会やコンクールで踊られることが多い有名なバリエーション。
ジゼルは高度なテクニックだけでなく感情の表現も求められる高度なヴァリエーションとなっています。
そのため全幕観ておくことで、よりジゼルの感情を理解できそうですね。
興味がある方はぜひ、ジゼルの全幕を観てみてくださいね。
-
7.152025
バレエを描いた映画やドラマ・アニメはある?おすすめ作品紹介!


近年バレエやダンスの習い事がとても人気になってきています。
その背景には、バレエやダンスを扱った映画やドラマ、アニメの影響があるんです。
そこで今回は、バレエを描いた作品をご紹介します!
バレエに情熱を注いでいるあなたも、これからバレエを始めたいと思っているあなたも楽しめることまちがいなしです。
バレエの魅力が詰まった作品の数々で、バレエの美しさやキャラクターの成長に共感し、新たな目標や夢に向かうモチベーションを高めましょう!バレエ映画①『ブラック・スワン』

『ブラック・スワン』は、2010年公開のバレエ映画です。
バレエの世界のリアルと葛藤を描く衝撃作として話題になりました。あらすじ
ニューヨークのバレエ団で働く主人公ニナは、厳しい競争の中で白鳥の湖の主役に選ばれることを夢見ていますが、周囲のプレッシャーや自己完璧主義に苦しみ、次第に精神的な限界に追い込まれていきます。
彼女のライバルであるリリーとの関係も複雑になり、舞台裏での苛烈な競争や自分自身の内面との葛藤が描かれています。
現実の厳しいバレエ業界をリアルに表現している作品です。見どころ
この作品は、バレエの舞台裏や、役に入り込むことの苦悩が緻密に描かれています。
バレエの舞台裏にある過酷な練習や心理的プレッシャーがリアルに描かれており、ニナが内面の葛藤と向き合いながら踊りに没入していく様子が見所です。
また、白鳥の湖の「白鳥」と「黒鳥」の二面性がニナ自身の変化とリンクしており、演技を通じて人間の本質に迫る奥深い描写が圧巻です。おすすめポイント
バレエの厳しさや努力、自己と向き合うことの難しさがリアルに描かれており、バレエに真剣に取り組んでいる人にとって共感と刺激を得られる作品です。
成長するための過程や自己発見の重要性がテーマとなっており、より深い次元でのバレエへの愛情と情熱を感じられるでしょう。
シリアスなストーリー展開で、心の葛藤やプレッシャーと向き合うバレエダンサーのリアルな姿が映し出され、バレエへの情熱や目標への思いが強まるかもしれません。バレエ映画②『リトル・ダンサー』

『リトル・ダンサー』(原題:Billy Elliot)は、2000年に公開されたイギリスの青春ドラマ映画です。
笑いと涙の両方を呼び起こす魅力的な映画で、ミュージカル化もされています。あらすじ
1980年代のイギリス、炭鉱町で育った少年ビリー・エリオットは、ボクシング好きの父親の影響でボクシングを習っていました。
殴り合うというボクシングの特性に馴染むことができずにいたビリーは、ある日ボクシングのクラスの隣で行われていたバレエ教室に魅了され、いつしかバレエに熱中していきます。
しかし、彼の家庭は保守的で、バレエを男子がすることに対して否定的でした。
ビリーは父親や兄弟の反対を受けつつも、バレエへの情熱を諦めず、ロンドンのロイヤル・バレエ学校を受験します。見どころ
ビリーが初めてバレエに触れてから自分の夢を見つけ、家族や社会の偏見に立ち向かう姿が感動的に描かれています。
バレエシーンの撮影も美しく、ビリーが自分を表現する瞬間の輝きが強く心に残ります。
また、労働者階級の背景が色濃く反映された舞台設定がリアリティを増し、炭鉱町の風景がビリーの心情と共鳴しているのも見どころの一つです。おすすめポイント
バレエを通して夢に向かって挑戦する勇気や家族愛が丁寧に描かれており、バレエに関心がない人でも夢を追いかける大切さを教えてくれる作品です。
家族で一緒に楽しみながら、成長や人との絆について考えさせられる映画です。バレエ映画③『眠れる森の美女(ディズニー)』

ディズニーの長編アニメーション映画『眠れる森の美女』(原題:Sleeping Beauty)は、1959年に公開されました。
大人気のディズニープリンセスであるオーロラ姫が登場する作品で、知名度も人気も高い作品です。あらすじ
悪い魔女マレフィセントの呪いによって、16歳の誕生日に永遠の眠りにつくことを予言されたオーロラ姫。
フィリップ王子が彼女を真実の愛で目覚めさせるまでの冒険物語が描かれています。
バレエ「眠れる森の美女」の要素を取り入れたストーリーは、音楽と絵が華やかに彩られています。見どころ
チャイコフスキーの名曲「眠れる森の美女」を全編で使用し、映画がまるでバレエの舞台のように進行するところが見どころです。
オーロラ姫とフィリップ王子が踊るシーンは特に美しく、バレエの要素が自然に取り入れられています。
映画全体にバレエのエレガントな雰囲気が漂い、視覚的にも楽しめます。おすすめポイント
ディズニーのファンタジーとクラシックバレエの融合が見事で、バレエ初心者にも親しみやすい作品です。
バレエの優雅さや物語のロマンティックな世界観を楽しみたい方には特におすすめです。
バレエへの理解も深まる作品です。バレエドラマ①『タイニー・プリティ・シングス』

『タイニー・プリティ・シングス』(原題:Tiny Pretty Things)は、2020年にNetflixにて公開された作品です。
バレエ学校を舞台に人間関係を描いたヒューマンドラマです。あらすじ
アメリカの一流バレエ学校に通う若きダンサーたちが、厳しい競争と謎の事件に直面します。
互いにライバル心を抱えながらも、技術と心理戦でぶつかり合う姿が描かれます。
さらに、寮での生活の中で発生する複雑な人間関係やミステリアスな事件が物語をスリリングに展開します。見どころ
舞台裏の緊張感や、ダンサーたちが厳しい練習に打ち込みながらも人間関係に悩む姿がリアルに描かれています。
また、バレエシーンが非常に精緻に再現されており、迫力のあるダンスパフォーマンスが魅力です。
ストーリー自体がミステリー仕立てなので、飽きることなく視聴できます。おすすめポイント
バレエの美しさと、競争の厳しさが共存する独特の世界観を体験できる作品です。
大人向けの内容が多いため、バレエに関心がある方やミステリー好きの方に特におすすめです。
スリリングな展開が続くため、一気に見たくなる作品です。バレエドラマ②『プリマダム』

ドラマ『プリマダム』は、2006年に日本テレビ系列で放送されたテレビドラマです。
バレエ経験のある女優が多く出演し注目を集めました。あらすじ
専業主婦である竹中桜子が、ふとしたきっかけで再びバレエの世界に戻ることを決意。
家事や家族の世話に追われて夢を諦めていた桜子ですが、バレエを通じて新たな自分に出会い、自信を取り戻していきます。
主婦が青春を取り戻す物語で、家族や友人との絆も描かれます。見どころ
バレエを再び始めた桜子が、挑戦の中で夢に対する情熱を取り戻していく姿が感動的です。
バレエの初心者であるため、基礎から少しずつ成長していく桜子の姿に共感できる人も多いでしょう。
また、主婦としての立場や家庭の葛藤が描かれていることで、さまざまな世代が感情移入できる作品になっています。おすすめポイント
「夢に挑戦する勇気」を描いており、特に主婦や大人世代が共感できるドラマです。
趣味や再挑戦を始めるきっかけになり、バレエに限らず、夢を再び追いかける全ての人に希望を与える作品です。
このドラマをきっかけに再びバレエを始めた大人もいるのではないでしょうか?^^バレエアニメ①『プリンセスチュチュ』

『プリンセスチュチュ』は2002年から放送されていたテレビアニメです。
構想10年以上という長い準備期間を経て製作され、多くの子どもたちにバレエの魅力を伝えました。あらすじ
金冠町という町の金冠学園バレエ科の落ちこぼれ生徒・あひるは、憧れの先輩・みゅうとと一緒にパ・ド・ドゥを踊ることが夢。
あひるは謎の老人に力を授けられ「プリンセスチュチュ」に変身し、仲間と共に人々の失われた心を取り戻す冒険に挑むファンタジーアニメです。
物語はクラシックバレエをベースに展開し、魔法と芸術が融合した独特の世界観を持っています。見どころ
作品内で使用されるクラシック音楽が、キャラクターの心情や場面と絶妙にマッチしています。
チャイコフスキーの「白鳥の湖」などが使われており、シーンごとに音楽とバレエが繊細に描写されているため、まるでバレエ舞台を見ているかのような臨場感があります。
ファンタジーとバレエが調和し、視覚と聴覚を楽しませてくれます。おすすめポイント
バレエのエレガントさをアニメで感じられる稀有な作品です。
ファンタジー好きや子供から大人まで幅広い世代におすすめで、バレエに興味のある人も楽しめます。
バレエ作品に親しみがなくても、アニメならではの視点でバレエを身近に感じられるでしょう。バレエアニメ②『ダンス・ダンス・ダンス―ル』

『ダンス・ダンス・ダンスール』は、『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて連載されたジョージ朝倉作の漫画が原作のテレビアニメです。
原作の単行本の売上は300万部を突破している大人気作品です。あらすじ
小学生の時にバレエに憧れたものの、男子らしくありたいという理由で一度は諦めた少年・潤平。
中学生になり、再びバレエの魅力に引き寄せられ、本格的にバレエを始めることを決意。
彼の情熱と苦悩、仲間との関係を通じて、バレエに対する真剣な姿勢と青春の葛藤が描かれます。見どころ
バレエに対する強い思いを持つ潤平の成長が描かれ、彼が技術と精神の両面でバレエと向き合う姿がリアルに表現されています。
練習や公演シーンも精密に描かれており、実際のバレエパフォーマンスのような迫力を感じます。
友情や恋愛の葛藤が絡み合うドラマが青春らしさを際立たせています。おすすめポイント
バレエに情熱を注ぐ若者たちの純粋な熱意が描かれており、バレエを通じて自分を表現することの大切さや挑戦の意味が伝わる作品です。
特に、努力や夢を追いかける若い世代に共感される内容で、バレエの美しさを改めて知るきっかけにもなるでしょう。
これまでバレエを扱ったアニメでは女の子が主人公であることがほとんどでしたが、本作品は男の子が主人公で人気を集めています。まとめ

いかがでしたか?
今回はバレエを描いた映画・ドラマ・アニメをご紹介しました。
バレエの技術や精神面の美しさだけでなく、バレエを取り巻く人々の葛藤や成長もリアルに描いているので、きっとバレエを頑張るみなさんの心に響くはずです。
気になる作品があったら是非見てみてくださいね♪ -
7.142025
舞台が魔法に包まれる!?バレエ版『アラジン』を徹底解説!!


ディズニーが製作したアニメーション映画として有名な『アラジン』
最近では、バレエ版が上演され話題となっています。
そのため、バレエ版『アラジン』が気になっているという方も多いでしょう。
今回はバレエ版『アラジン』のあらすじや登場人物、どこで観られるのかなどを徹底解説していきます!
『アラジン』を観てみたいという方は参考にしてみてくださいね!!
バレエ版『アラジン』について知ろう!!

バレエ版『アラジン』はどういった作品なのでしょうか。
概要や使用されている音楽についてや登場人物などについて紹介します。
バレエ版『アラジン』の概要
2008年11月にバレエ版の『アラジン』(Aladdin)が新国立劇場バレエ団にて初演されました。
全3幕10場のバレエ作品で、振付はデヴィッド・ビントレー、音楽はカール・デイヴィスが製作を担当しています。
本作はビントレーが新国立劇場バレエ団のために創作したオリジナル作品で、高評価を得たため同バレエ団のレパートリーとして定着しています。
日本国外ではバーミンガム・ロイヤル・バレエ団(2013年)やヒューストン・バレエ団(2014年)がレパートリーに加えて上演を行なっています。
バレエ版『アラジン』の音楽について
ディズニーのアニメーション映画のイメージが強い『アラジン』ですが、バレエ版では映画・テレビ・舞台音楽の作曲家として知られるカール・デイヴィスが製作を担当しました。
デイヴィスが作曲した『アラジン』はユーモアと色彩が随所に散りばめられた、まるで映画音楽のような作品となりました。
中国やモロッコ、その他の地域の要素が幅広く取り入れられており、太鼓(ライオンダンスやドラゴンダンスを表現)や※5音音階旋律(東アジア)、北アフリカのリズムなどが用いて『アラジン』の世界を描写しています。
※5音音階旋律・・・1オクターブに5つの音が含まれる音階のことです。
東アジア(日本、朝鮮半島、中国(漢民族)、モンゴル、チベット、ブータンなど)、東南アジア、アフリカ、南アメリカの音楽では、1オクターブの音域内で5つの音を持つ音階に基づくものがあります。
登場人物
どんな登場人物が登場するのかも気になりますよね!?
バレエ版『アラジン』の登場人物一覧は下記の通りです。
- ・アラジン
やんちゃで好奇心が強く勇気のある若者。
出会いやさまざまな試練によって、人間として大きく成長し、真実の愛を知ります。
- ・プリンセス
名前はバドル・アドブダル(アラビア語)で、その意味は「満月の中の満月」を意味します。
退屈な日々に飽き飽きしていた彼女は、アラジンの大胆さに魅せられて恋に落ちます。
- ・ランプの精ジーン
古ぼけたランプの中に閉じ込められていた魔神で、強大な魔力を持っていますが、ランプの持ち主には逆らえません。
- ・マグリブ人
邪悪な気質の魔術師で、ランプの精ジーンを手に入れようとさまざまな策を巡らせています。
- ・サルタン
プリンセスの父で王国の王様
- ・アラジンの母
女手一つでアラジンを育て上げました。
アラジンと母は中国からの移住者という設定となっています。
- ・その他
アラジンの友人たち、金・銀・宝石たち、商人たち、王宮の人々、砂漠の風など。
ディズニー版『アラジン』とは異なる登場人物や設定となっている場合があるので、あらかじめ予習しておくと、よりバレエ版『アラジン』に理解を深められそうですね。
気になるバレエ版『アラジン』の全幕のあらすじを解説!!

バレエ版『アラジン』は全3幕10場で構成されています。
新国立劇場バレエ団で予定されている上演時間は 約2時間45分(第1幕55分 休憩25分 第2幕35分 休憩20分 第3幕30分)となっています。
バレエ版『アラジン』全幕のあらすじをみていきましょう!!
バレエ版『アラジン』第1幕のあらすじ
バレエ版『アラジン』のあらすじをプロローグと1場から5場まで解説していきます!!
プロローグ
邪悪な魔術師マグリブ人が登場し、手の届かないところに存在する古ぼけたランプを物欲しげに凝視しています。
第1幕1場『昔むかしのアラビアの市場』
賑わっている市場の中にアラジンが現れます。
やんちゃでいたずら好きな彼はいつも問題を起こしており、宮殿の警備隊に捕縛されてしまいます。
マグリブ人は魔法でアラジンの窮地を救ってあげ、「自分の仕事を手伝わないか」と誘いかけ、財宝に眼がくらんだアラジンはその誘いを受け入れます。
第1幕2場『砂漠への旅』
強い風に運ばれてアラジンとマグリブ人は砂漠にたどり着きます。
アラジンはマグリブ人に「自分がなくしたランプを洞窟の中へ取りに行くように」と命じられます。
恐れをなして逃げようとするアラジンでしたが、マグリブ人は押しとどめ、絶世の美女の幻影を魔法で呼び出し、「洞窟の財宝があれば、あの美女を自分のものにすることが叶う」と告げアラジンをそそのかします。
第1幕3場『財宝の洞窟』
洞窟に下りたアラジンは、たくさんの宝石の山を見つけます。
彼は大喜びでポケットに宝石を詰め込みますが、マグリブ人の言いつけを思い出して古ぼけたランプを探し出すことに成功します。
マグリブ人は洞窟から出ようとするアラジンを押しとどめ、「まず、ランプをよこせ」と命じました。
アラジンが抵抗すると、マグリブ人は怒り、出口の扉を閉めてしまいます。
アラジンは闇の中で出口を探しますが見つけることができません。
そのとき、アラジンはランプの存在を思い出すのでした。
第1幕4場『アラジンの家』
アラジンの母はなかなか帰ってこない息子のことを心配しています。
そこへアラジンが現れ、今までの冒険について母に打ち明けますが、なかなか信じてもらえません。
そこでアラジンがランプをこすって見せると、ランプの精ジーンが洞窟の財宝と共に登場します。
第1幕5場『王宮の外』
市場の方からサルタンの娘、プリンセス・バドル・アドブダル が宮殿内の浴場に向かっていることを知らせるファンファーレが聞こえます。
高貴な身分であるプリンセスの姿を見ることは禁じられているので、人々はひざまずいて目をつぶります。
アラジンのみがこっそりと垣間見ると、プリンセスこそが、幻影で見た美女であることに気づきます。
バレエ版『アラジン』第2幕のあらすじ
バレエ版『アラジン』第2幕は1〜2場となっています。
それぞれ、詳しく解説していきます!!
第2幕1場『浴場』
プリンセスに一目惚れしたアラジンは、捕まれば死刑になるとわかっていながらも、彼女が身を清めている浴場に忍び込みます。
プリンセスはアラジンの存在に気づき、彼の大胆さに心惹かれますが、宮殿の警備隊が駆けつけ、アラジンを捕縛してしまいます。
第2幕2場『宮廷』
アラジンはプリンセスを覗き見た罪で宮廷に設けられた法廷に引き出されてしまいます。
プリンセスはアラジンが助かるようお願いしますが、即刻死刑の宣告がなされます。
その時です!傍聴席にいたアラジンの母が進み出て許しを請い、隙を見てアラジンにランプを渡しました。
するとランプの精ジーンが法廷に現れ、大混乱を引き起こします。
その騒ぎが沈静化すると立派な身なりに変身したアラジンの姿が。
アラジンは大勢の奴隷を従えてサルタンの前に立ちます。
奴隷たちはたくさんの財宝をサルタンに献上し、サルタンは大喜びでアラジンをプリンセスにふさわしい若者と認めるのでした。
2人の結婚式が盛大に行われ、たくさんの人々が祝福するが首相(正体はマグリブ人)のみは祝宴に参加していません。
マグリブ人はアラジンがランプの精ジーンの主人になっていることに気づいたのです!!
そして、ランプを手に入れるための作戦を考え始めるのでした。
バレエ版『アラジン』第3幕のあらすじ
バレエ版『アラジン』第3幕は1〜3場となっています。
それぞれ、詳しく解説していきます!
第3幕1場『王宮の一室』
アラジンとプリンセスは夫婦となり、王宮で新婚生活を始めます。
2人がチェスを楽しんでいると、アラジンの友人たちが訪れました。
アラジンは誘いに応じて彼らと狩りに出かけ、プリンセスが一人残されます。
そこへ物乞いに変装したマグリブ人が「古いランプを新しいランプと交換します」と呼びかけるのを聞いたプリンセスはランプを渡してしまいます。
すると、マグリブ人は正体を現し、ランプの精ジーンに自らとプリンセスをモロッコにあるハーレムに連れて行くように命じてしまいます。
第3幕2場『魔術師マグリブ人のハーレム』
ハーレムに幽閉されてしまったプリンセスは自分の運命を嘆き、自決しようとしますが、アラジンが彼女のもとにたどり着きます。
アラジンが持ってきた眠り薬を彼女に渡すと、「マグリブ人に飲ませるように」と告げて姿を隠します。
マグリブ人が戻ってくると、プリンセスは踊りを披露し、喉の渇きを訴えました。
マグリブ人は2人分の酒を用意していると、隠れていたアラジンが現れ、てマグリブ人の気を逸らします。
その間に、プリンセスは眠り薬をマグリブ人の酒に注ぐと、その酒を飲み干したマグリブ人は体の異変に気づき、ランプの精ジーンを呼びだそうとします。
しかし、アラジンはそれを妨げ、マグリブ人を打ち負かすのでした。
第3幕3場『アラジン国へ帰る』
ジーンはアラジンとプリンセスのために魔法の絨毯を用意し、2人はそれに乗って故郷へ帰還し、家族と再会を果たします。
多くの試練を乗り越え真実の愛に目覚め、人間としても大きく成長したアラジンは、プリンセスを2度と1人にしないと誓いを立てます。
そしてアラジンはジーンを解放し、ジーンはその計らいに感謝し、遠く彼方へと飛び去って行きました。
冒険を終えたアラジンとプリンセスは、国民たちから歓喜と祝福をもって迎えられ物語は幕を閉じます。
舞台版の『アラジン』はどこで観れる?舞台版を上演する場所を紹介

舞台の上で繰り広げられる魔法の数々を見てみたい!という方も多いでしょう。
現在、舞台で『アラジン』を観られるのは、バレエ版を上演している新国立劇場バレエ団と、ミュージカル版を上演している劇団四季となっています。
それぞれ、詳しく紹介していくので参考にしてみてくださいね!!
バレエ版『アラジン』が観られるのは新国立劇場バレエ団
バレエ版『アラジン』は概要でも紹介した通り、新国立劇場バレエ団のために創作されたオリジナル作品です。
そのため、公演を観られるのは新国立劇場となっています。
2024年は新国立劇場で、6月14 日から6月23日の間で上演されました。
新国立劇場以外では7月6日と7日の2日間で上演されています。
『アラジン』は人気作品として新国立劇場バレエ団のレパートリーに定着していますので、毎年上演される可能性が高いですね。
ミュージカル版『アラジン』が観られるのは劇団四季
ミュージカル版『アラジン』を上演しているのは劇団四季です。
『アラジン』は数多くある劇団四季の演目の中でも人気がありロングラン上演となっています。
ストーリーはディズニーアニメーション映画『アラジン』が元となっており、音楽も映画と同様にアラン・メンケンの曲が使用されています。
登場人物の名前も映画と同じになっていますので、映画を観たことがある人なら観やすい作品となっています。
上演場所は東京の電通四季劇場「海」で2024年は7月2日から2025年6月29日までの上演スケジュールが決まっています。
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

ディズニーのアニメーション映画にバレエ版、ミュージカル版と、どれも人気のある『アラジン』。
それぞれの違いを見つけるのも楽しみの1つですね。
また、馴染みのあるストーリーなので他のバレエ作品よりも観やすいのでバレエ鑑賞デビューにもオススメです。
『アラジン』の世界がどのように舞台で表現されているのか、観てみたいという方もぜひ、バレエ版やミュージカル版を観に行ってみてくださいね!
-
7.142025
バレエの人気作品!「コッペリア」の全幕を徹底解説!


可愛らしい衣装で発表会やコンクールなどで踊れらることが多い『コッペリア』のヴァリエーション。
有名で人気のある作品ですが、意外と全幕のストーリーが知られていないことも多いようです。
今回は『コッペリア』のあらすじやみどころを徹底解説します!
『コッペリア』について

『コッペリア』は動く人形を題材としたバレエ作品で、E.T.A.ホフマンの物語『砂男』にヒントを得、台本はサン=レオンとシャルル・ニュイッテルにより制作されました。
初演は1870年5月25日にパリ・オペラ座で上演され、現在も世界中で上演され続けている人気作品です。
タイトルはコッペリアですがバレエ作品において、コッペリアやコッペリウス博士は重要な役ではありますが、主役はスワニルダとフランツとなっています。
登場人物
『コッペリア』には数々の魅力的な人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・スワニルダ:(村の娘、フランツの恋人)
・フランツ:(村の青年、人形と知らずにコッペリアに恋をする)
・コッペリア:(コッペリウス博士が造った自動人形)
・コッペリウス:(コッペリアを造った博士)
・スワニルダの友人たち:(スワニルダとともにコッペリウス邸に忍び込んだり、さまざまなシーンでスワニルダと行動を共にします)『コッペリア』全3幕
『コッペリア』は喜劇のようにコミカルな動きが散りばめられており、観客を楽しい気分にさせてくれる作品です。
演出家によって結末が異なるのも最後まで目が離せないポイントです。そんな『コッペリア』のあらすじや登場するヴァリエーションなどを紹介します。
『コッペリア』第1幕
『コッペリア』第1幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
舞台はポーランドのとある農村。
人形作りの職人であるコッペリウスは陰気で気難しい性格で村人たちから変人扱いされていました。
コッペリウスの家のベランダには、彼が造った人形の少女コッペリアが座って本を読んでいます。
しかし、村人たちはコッペリアが人形であることを知りません。
コッペリウスの向かいに住んでいるのは明るく人気者の少女スワニルダ。
村の青年、フランツとは恋人同士ですが、最近フランツは可愛らしいコッペリアが気になる様子です。
これに気づいたスワニルダはヤキモチを焼いて、このことがきっかけで2人はケンカをしてしまいます。
ある日、コッペリウスが町に出かける際に家の前に鍵を落としてしまいます。
そのことに気づいた好奇心たっぷりのコッペリアと友人たちは、コッペリウスの家に入ってみることにしました。
- 《みどころ》
1幕では個性的な登場人物が登場し、それぞれのキャラクターや関係性がわかります。これからコッペリウスの家に忍び込むスワニルダと友人たちのドキドキ感も。コンクールでも踊られることが多い1幕のスワニルダのヴァリエーションにも注目です。
- 《ヴァリエーション》
スワニルダのヴァリエーション
『コッペリア』第2幕
『コッペリア』第2幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
コッペリウスの家の室内には様々な種類の人形たちがところ狭しと並べられています。
スワニルダと友人たちは探索しているうちにコッペリアも人形の1つであることに気づきました。
運悪くコッペリウスが帰ってきてしまい、スワニルダたちは怒鳴られてしまいます。
友人たちは逃げて行きましたが、スワニルダだけはコッペリウスに気づかれずに室内に身を隠すことができました。
そこへフランツもコッペリアを見るために窓から忍びこんできました。
当然、コッペリウスに見つかってしまったフランツは怒られてしまいます。
そして、コッペリウスは一計を案じフランツに眠り薬を混ぜたワインを飲ませ眠らせます。
酔っ払ったフランツから命を抜いて自信作の人形であるコッペリアに吹き込もうと考えたのです。
その一部始終を見ていたスワニルダはコッペリアになりすましコッペリウスをからかい、いたずらの限りをつくします、この騒ぎにフランツも目を覚まし、コッペリアの正体が人形であることを知ったフランツはスワニルダと仲直りを果たします。
- 《みどころ》
ミステリアスなコッペリウスの家の中は緊迫感がありますが、スワニルダがコッペリアのふりをするシーンはコミカルな人形の動きが可愛らしく引き込まれます。
コミカルな動きやシーンが多いのも『コッペリア』の特徴です。
- 《ヴァリエーション》
ありません。(スワニルダがコッペリアに扮して踊るソロはあります)
『コッペリア』第3幕
『コッペリア』第34幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
仲直りしたスワニルダとフランツは村のお祭りの日に結婚の日を迎えます。
にぎやかな祝宴の最中に人形を壊されたコッペリウスはカンカンになって怒鳴り込みにやってきました。
しかし、スワニルダとフランツによる謝罪と村長がなだめたことによりコッペリウスも機嫌を直し2人を祝福します。
祝宴では「時」、「曙」、「祈り」、「仕事」、「結婚」、「戦い」、「平和」の踊りが披露され、ラストには登場人物全員でフィナーレを迎えます。
- 《みどころ》
村の盛大なお祭りの日にスワニルダとフランツの結婚式が行われお祝いムードの中、フィナーレへと向かいます。
発表会ではこの第3幕だけを上演する教室も多くあります。
そのため「時」、「曙」、「祈り」、「仕事」、「結婚」、「戦い」、「平和」の踊りを踊ったことがある、これから踊る予定という人も多いかもしれません。
スワニルダやフランツのヴァリエーションはコンクールでもよく踊られている人気のある踊りです。
- 《ヴァリエーション》
・「時」、「曙」、「祈り」、「仕事」、「結婚」、「戦い」、「平和」のヴァリエーション(ソロではない場合もあります。)
・コッペリアのヴァリエーション
・フランツのヴァリエーション
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

『コッペリア』は他のバレエ作品に比べ、コミカルな動きが多く観ていて楽しい気分になれる作品です。
ストーリーをあらかじめ知っておくとより作品を理解して公演を楽しめますね。
また役柄を理解することでヴァリエーションを踊る時も表現が深くなるでしょう。
『コッペリア』を予習してから踊ったり、公演を観に行ってみてくださいね。
-
7.142025
実はあらすじがある!?バレエ『ボレロ』を徹底解説!!


バレエ作品の『ボレロ』を知っていますか?
バレエをはじめたばかりの方は聞きなれないワードかもしれません。
『ボレロ』のジャンルはコンテンポラリーです。
今回は古典バレエ作品とは違った魅力のある『ボレロ』について徹底解説していきます!!
コンテンポラリーとは

コンテンポラリーという言葉の意味は「現代的な」です。
クラシックバレエといった既存の分類に当てはまらない新しいスタイルの踊りをコンテンポラリーと呼びます。
振り付けや表現方法に決まりがなく、身体表現を自由に行うことで時代の先端を体現しています。
見た目もバレエの衣装やトウシューズを身につけない自由で開放的なもので、尋常ではない体の使い方やストーリー性のない象徴的なものまで幅広く表現されています。
既存のスタイルにとらわれることなく現在も進化し続けています。
いつどこで始まった?
1980年代前後のフランスでルールの多いクラシックバレエから脱却しようという考えが主流となり、コンテンポラリーバレエは誕生しました。
コンテンポラリーの代表的な作品
- 『ボレロ』〜モーリス・ベジャールバレエ団〜
『ボレロ』は、モーリス・ラヴェルが作曲したバレエ音楽で、一定のリズムで進行する独特の音楽は一度は聞いたことがある方も多いでしょう。
中でもモーリス・ベジャール振付による『ボレロ』が最も有名で、巨大な赤い円卓の上で踊るダンサーは圧巻です。不朽の名作といわれる作品です。
- 『ザ・ステイトメント』〜ネザーランド・ダンス・シアター
ネザーランド・ダンス・シアターは、1959年に創立されたオランダを代表する舞踊団です。
クラシックバレエを基礎としたオリジナルのコンテンポラリー作品を多く上演しています。
『ザ・ステイトメント』は世界中のバレエ団からオファーが絶えないと言われるクリスタル・パイトが振付した代表作で、語りながら踊るダンサーによって、支配・戦い・責任などの現代社会を映し出した作品です。
ボレロについて知ろう

前述の通り『ボレロ』はコンテンポラリーの代表的な作品です。
『ボレロ』の音楽は聞いたことがあるけど、よく知らないという方も多いかもしれませんね。
下記にバレエ作品『ボレロ』について詳しく解説していきます。
ボレロとは
『ボレロ』はバレエ音楽のタイトルで、作曲者はフランスのモーリス・ラヴェルです。
イダ・ルビンシュタインというバレリーナが自身のバレエ団のためにモーリス・ラヴェルに作曲を依頼したことがきっかけで『ボレロ』という楽曲が生まれました。
そして、その楽曲にモーリス・ベジャールが振り付けを行いバレエ作品の『ボレロ』が誕生し有名となりました。
あらすじ
セビリアの酒場で、スペイン人の踊り子が舞台でゆったりとリズムを取り始めます。
最初はまわりの客たちは見向きもしませんでしたが、踊り子の踊りが徐々に華やかな踊りになっていくと、高揚感がまわりに伝わり、酒場の客たちも踊りだします。
そして最後にはみんなで踊るというあらすじです。
円形の赤い台について
『ボレロ』の中で特徴的なのは円形の赤い台を使用すること。
主役である踊り子は赤い円形の台を舞台に踊り、舞台の下に酒場の客がいます。
主役の踊り子は『メロディー』と称されています。
過去にボレロを踊ったダンサー
実は『ボレロ』は誰でも踊れるものではありません。
これは難しくて踊れないという意味ではなくベジャールが振り付けた『ボレロ』を踊ることができるのはモーリス・ベジャールバレエ団に許可されたバレエダンサーやバレエ団のみということなんです。
特に主役の踊り子『メロディー』を踊ることができるのは世界のトップバレエダンサーの中でも選ばれしもののみとなっています。
過去に『ボレロ』を踊った経験のあるバレエダンサーは下記の通りです。
《女性バレエダンサー》
・シルヴィ・ギエム
・上野水香
・マヤ・プリセツカヤ《男性バレエダンサー》
・首藤康之
・ジョルジュ・ドン日本でボレロを観るには

知れば知るほど魅力的な作品である『ボレロ』。
一度は実際に観てみたいという方も多いでしょう。
日本でも度々上演されることがあり、2024年には下記のバレエ団が日本で上演を行いました。
参考にしてみてくださいね!
ボレロ公演〜モーリス・ベジャール・バレエ団〜
モーリス・ベジャールバレエ団は日本で来日公演を行うことがあり、他の作品と共に『ボレロ』が上演されます。
毎年観られるわけではないかもしれませんが、2024年は下記のように上演されました。
- タイトル
モーリス・ベジャール・バレエ団2024年バレエ公演 - 上演日時
2024/9/27(金)〜2024/9/29(日) 13:30~ (開場 12:50~) - 場所
東京文化会館大ホール (東京都) - 曲目・演目
「ボレロ」「だから踊ろう…!」「2人のためのアダージオ」「コンチェルト・アン・レ」 - 上演時間
約1時間55分(休憩含む)】
※『ボレロ』は15分程度の演目なので他の作品と一緒に上演されることもあります。
ボレロ公演〜東京バレエ団〜
日本のバレエ団では東京バレエ団が『ボレロ』を上演しています。
主役の踊り子「メロディー」を踊ることが許されているのは上野水香さんです。
2024年は下記の通り上演されました。
- タイトル
東京・春・音楽祭2024 60周年記念シリーズ4 東京バレエ団〈上野水香オン・ステージ〉 - 上演日時
024/3/19(火)19:00、2024/3/20(水・祝)16:00 - 場所
東京文化会館大ホール (東京都) - 曲目・演目
『ボレロ』ほか
まとめ

最近ではコンクールでもコンテンポラリーの種目があったり、ほとんどのバレエ団がコンテンポラリー作品を上演しています。
そのため、クラシックバレエ以外にコンテンポラリーも踊れた方が活躍の場が広がりそうです。
コンテンポラリーというと難しいイメージがありますが、まずは有名な作品を観てみるのもイメージが湧いて良いかも知れません。
なかなか公演を観に行けないという方はYou Tubeなどでも見れるので参考にしてみてくださいね。
-
7.142025
バレエ作品『エスメラルダ』のあらすじ・どこで観れる?を徹底解説!


『エスメラルダ』といえばタンバリンを持って踊るヴァリエーションが有名ですよね。
少し難しいヴァリエーションですので、いつか踊ってみたい!挑戦してみたいと思っている方も多いかもしれません。
しかし、そのストーリーについては意外と知られていません。
今回はバレエ作品『エスメラルダ』のあらすじやどこで観られるかを徹底解説します!
バレエ作品『エスメラルダ』について

『エスメラルダ』は1831年にヴィクトル・ユーゴーが発表した小説『ノートルダム・ド・パリ』に着想して作られた3幕5場のバレエ作品です。
チェーザレ・プーニの曲にジュール・ペローが振付し、ウィリアム・グリーブが美術、コペール夫人が衣装を担当しました。
1844年3月9日、ロンドンのハー・マジェスティーズ劇場バレエ団により初演さましたが、現在では、ロシア、東ヨーロッパ、そしてアメリカのニュージャージー州以外で全幕の上演が行われることはほとんどありません。
主役であるエスメラルダが登場するパ・ド・ドゥとパ・ド・シスの二場面と、「ディアナとアクティオンのパ・ド・ドゥ」のみをガラ公演にて上演されることが多いです。
そのことから『エスメラルダ』内のヴァリエーションは人気があり有名なので、コンクールでよく踊られることが多いです。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
バレエ作品『エスメラルダ』登場人物
『エスメラルダ』には数々の魅力的な人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・エスメラルダ:美しいジプシーの娘でカジモド、フロロ、フェビュスの3人から思いを寄せられる。
しかし、本人が思いを寄せているのはフェビュスで婚約者がいる。
・カジモド:ノートルダム大聖堂の前に捨てられていたところを聖職者フロロに拾われた醜い外見を持つ男。
成長し、ノートルダムの鐘つき役となる。
・フロロ:カジモドを拾った聖職者で神に仕える身でありながらエスメラルダに思いを寄せ、苦悩している。
・フェビュス:フロロの差し金でカジモドに連れ去られそうになったエスメラルダを助けた夜警隊の隊長。
エスメラルダと恋に落ちるが、実は婚約者がいる。
・フルール:フェビュスの婚約者。
・クロパン:悪党浮浪者グループのリーダー
・グランゴワール:詩人、クロパンにより絞首刑になりかけたところをエスメラルダの機転で助けられ、ジプシーの掟に従って仮の夫婦となる。
『エスメラルダ』あらすじ

美しいジプシーの少女エスメラルダは、詩人ピエール・グリンゴワールがジプシーの王に処刑されるのを防ぐため、グリンゴワールと結婚します。
グリンゴワールはエスメラルダに心奪われるが、エスメラルダはこの結婚はあくまでグリンゴワールの命を救うための仮初めのものだとはっきり言い放ちます。
一方、グリンゴワールのみならずノートルダム大聖堂の助祭長クロード・フロロもエスメラルダに執心していました。
フロロの熱の上げようは危険なほど異常で、醜い下男カジモドにエスメラルダを誘拐するよう命じます。
カジモドは通りでエスメラルダに襲いかかるが、エスメラルダはフェビュス率いる衛兵隊に助けられ、カジモドは捕らえられます。
フェビュスはカジモドを拷問にかけようとするが、エスメラルダは自分を襲ったカジモドを釈放してやるよう願い、カジモドはエスメラルダの優しさに深く感動するのでした。
エスメラルダはフェビュスに想いを寄せ、フェビュスもまたエスメラルダに魅了されて婚約者フルール・ド・リスから贈られたスカーフをエスメラルダに与えてしまいます。
翌日、フルール・ド・リスとその母親はフェビュスとの婚約を祝う壮大な祝賀パーティーを開くが、当のフェビュスはエスメラルダのことで頭がいっぱいです。
エスメラルダはパーティーの余興を演じるために呼ばれていましたが、会場でフルール・ド・リスの婚約者がフェビュスであることを知って心を痛めます。
一方のフルール・ド・リスは、自分がフェビュスに贈ったスカーフをエスメラルダが身に着けていることに気づき、フェビュスが他の娘と恋に落ちたことを知ってしまいます。
フルール・ド・リスは大いに怒って婚約を破棄し、フェビュスはエスメラルダと共に去って行きます。
フェビュスはエスメラルダは酒場で愛を誓い合うが、それを居合わせたフロロに盗み聞きされてしまいます。
嫉妬に狂ったフロロは、エスメラルダの部屋から盗み出していた短剣を持って
2人の背後から忍び寄り、フェビュスを突き刺してしまいます。
フロロは警察を呼び、倒れたフェビュスと凶器の短剣を見せると、短剣がエスメラルダのものだと分かり、エスメラルダはフェビュス殺害犯として警察に連行され死刑を宣告されました。
翌朝の夜明けにエスメラルダはフェビュス殺害の罪で絞首刑に処されることになりました。
エスメラルダの友人やグリンゴワールがやってきてエスメラルダに別れを告げ、その様子を見たフロロは勝ち誇っています。
エスメラルダが絞首台に引き出されるが、そこに死んだはずのフェビュスが現れます!
実は刺し傷は致命傷ではなかったのです!フェビュスは真犯人はフロロであり、エスメラルダはまったくの無実だと宣言し、悪事が露見したフロロは短剣を取り、フェビュスたちに襲いかかりますが、カジモドに奪われて刺し殺されます。
こうしてエスメラルダとフェビュスは幸福のうちに再会するのでした。
エスメラルダが登場する『ノートルダムの鐘』について

前述の通り、バレエ作品の『エスメラルダ』は日本では全幕公演を行なっていません。
そのため、プロダンサーが踊る『エスメラルダ』を観るためにはガラ公演でのみです。
しかし、何らかの形で『エスメラルダ』を観てみたいという方も多いでしょう。
バレエ作品ではありませんが、下記のような作品を観ることにより理解を深めることができますので、参考にしてみてくださいね。
ディズニー作品『ノートルダムの鐘』
『ノートルダムの鐘』は1996年にディズニーの長編アニメーション映画として公開されました。
ディズニー版の『ノートルダムの鐘』は見た目は醜いけれど心優しいノートルダムの鐘つき男カジモドが中心となってストーリーが展開されます。
カジモドが、自由を愛し強く生きるジプシーの娘エスメラルダと出会い、初めて友情を知り、そして自らの運命を変えてしまうような冒険に引き込まれていくというお話です。
原作と異なる点はいくつかありますが、強く美しいエスメラルダのキャラクターを知ることができます。
- どこで観れる?
DVD・ブルーレイ・デジタル配信(ディズニープラス)
劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘』
日本では劇団四季が『ノートルダムの鐘』のミュージカルを上演しています。
バレエ作品やディズニー作品と同様に世界的な文豪であるヴィクトル・ユゴーの代表作『ノートルダム・ド・パリ』に着想して製作されました。
劇団四季が上演するのはディズニー・シアトリカル・プロダクションズが製作し、2014年に米国カリフォルニア州サンディエゴのラ・ホイヤ劇場で初演されたもので、日本での初演は2016年です。
ディズニーの場合はアニメーションですが、劇団四季はミュージカルなので実際に人がエスメラルダを演じている姿を観ることができます。
2023年には6年ぶりに東京公演が5月14日から8月6日まで上演されました。
毎年上演されるわけではないのが残念ですが、上演の際には観てみたいですね。
- どこで観れる?
2022年 横浜 KAAT神奈川芸術劇場
2023年 東京・JR東日本四季劇場[秋]
※2025年の上演はありません。
まとめ

残念ながらバレエ作品としての『エスメラルダ』は全幕で上演されていませんがディズニー作品やミュージカル作品としてエスメラルダのストーリーやキャラクターを知ることができます。
『エスメラルダ』のヴァリエーションを踊る場合は一度、観ておくとイメージが湧きやすいですね。
強く美しい魅力的なキャラクターであるエスメラルダのヴァリエーションにぜひ挑戦してみてくださいね!
-
7.142025
体が硬くても大丈夫!小学生の柔軟性を高めるバレエストレッチ


バレエを始めたけど体が硬くてなかなか上達しない…と悩んでいませんか?
実は、家で簡単にできるストレッチで、少しずつ体を柔らかくすることが可能です。
この記事では、バレエ初心者でも楽しく続けられる効果的なストレッチ方法をご紹介します。バレエにはなぜ柔軟性が必要なの?

バレエをやっている人は体が柔らかいというイメージを多くの人が持っていると思います。
ではなぜバレエをやっている人は体が柔らかいのでしょうか?
バレエに柔軟性が必要な理由を3つご紹介します。バレエの美しさには柔軟性が必須!
バレエでは、しなやかな動きや優雅なポーズが求められます。
柔軟性があると、足を高く上げたり、腕や背中を美しく伸ばす動きがしやすくなります。
特にアラベスクやグランバットマンといった基本の動作も、柔らかい体で行うとより美しく見えます。体が柔らかいとケガ予防になる?
硬い筋肉や関節は、無理な動きをしたときにケガをしやすい状態です。
ストレッチを習慣にして体を柔らかくすると、筋肉や関節の可動域が広がり、衝撃を吸収しやすくなります。
これはバレエだけでなく、日常生活や他のスポーツでも役立つポイントです。技術の精度と範囲が広がる!
柔軟性が向上すると、動きの幅が広がります。
ジャンプやターン、リフトといったダイナミックな技にも挑戦しやすくなり、踊りの完成度がアップします。
バットマンが高く上がるようになったり、ジャンプの高さが上がったり足がさらに開くようになったりといったいい影響があります。
柔軟な体は技術的な挑戦をサポートしてくれるんです。自宅でできる!柔軟性を高めるバレエストレッチ

柔軟性を高めるために大切なのが継続すること!
毎日少しでもストレッチをして筋を伸ばすことが重要です。
そこで、自宅で簡単にできるストレッチ方法をご紹介します。ストレッチを始める前の準備
ストレッチは体が温まった状態でやることが大切です。
お風呂あがりや、筋トレなどをしたあとにやるのがおすすめです。
冷えた体でストレッチをすると、逆に筋を痛めてしまったり、ストレッチの効果が減ってしまうことがあります。
夏場でもエアコンで体が冷えやすいので、ストレッチをする際は部屋の温度にも気をつけてみてください。基本のストレッチ3選
バレエにおいて特に柔軟性が必要な部位のストレッチ方法を3つご紹介します。
前屈ストレッチ
足を揃えて座り、膝を伸ばしたまま体を前に倒します。
つま先に手が届かなくても大丈夫!
少しずつ深く曲げられるように続けてみましょう。
気をつけるポイントは2つ!
・膝が曲がらないようにする
・背筋が曲がらないようにする
この2つに気をつけることで、よりストレッチの効果が得られます。足首回しストレッチ
バレエダンサーにとって足首周りの柔軟性はとても大切です。
足首が柔らかいことで踊りの中で深くプリエを踏めるようになります。
前屈ストレッチをするときのように足を伸ばして座り、片足を曲げてもう片方の膝の上あたりに乗せます。
足の指の間に手の指を入れて足指を広げながら、足首を大きく回していきます。
このストレッチはウォームアップ時にやるのもおすすめですよ。開脚ストレッチ
開脚はももと股関節を伸ばすことができます。
開脚の柔軟性はジャンプなどの美しさにつながります。
足を大きく開いて座り、両手で片足のつま先をつかむように体を左右に倒します。
このときおしりが床から離れないように注意しましょう。
最後に体を中央に倒してストレッチを深めましょう。
中央に倒れる時は、膝の向きを天井に向けたままできるようにしましょう。道具を使ったストレッチ方法
ストレッチをする際、ストレッチバンドやヨガブロックなどを使ってさらに負荷をかけてみるのもおすすめです。
ヨガブロックなどで高さを出して180度以上のストレッチをすることをオーバーストレッチといいます。
オーバーストレッチによって柔軟性をより高めることで、踊っているときの可動域がさらに広がり、美しい踊りにつながります。親子でできる!簡単ストレッチ

子どもが自発的にストレッチをしてくれない・・・とお困りの保護者の方も多いのではないでしょうか?
そこで、親子で一緒にできるストレッチ方法をご紹介します!
バレエについてよくわからないという方でも一緒にできる簡単なストレッチなので、是非お子様と一緒に試してみてください。前屈ストレッチ
大人が子どもの背中を押して負荷をかけてみましょう。
背後から両手で膝が曲がらないように抑え、上半身を使って背中を押すことで膝の曲がりを防ぐやり方もあるので、試してみてください^^
前屈ストレッチは、一人でやると膝が曲がりやすかったり負荷が足りず柔軟性を高められなかったりするので、親子でストレッチをして柔軟性を高めましょう。開脚ストレッチ
左右にストレッチするときは、大人が倒れていない方の足の付け根を床に向かって抑えることで、おしりの浮きを防ぎます。
中央に倒れる際は、膝が前に向かないように抑えてあげましょう。
開脚ストレッチでは、左右に倒れたときにおしりが浮きやすかったり、前に倒れたときは膝が前に向いてしまったりしがちなので、親子で協力してストレッチをするのがおすすめです。足の甲のストレッチ
前屈ストレッチをする時のように足を前にまっすぐ伸ばします。
正面から大人が足の甲を床に向かって押してみましょう。
ここで注意するポイントが2つあります。
・指先を押すのではなく、足首あたりから押すこと(指先を床につけることを目的としがちですが、それでは足の甲は伸ばせません💦)
・膝が曲がらないように子どもに意識してもらうこと
バレエにおいて足の甲の柔軟性はとても大切です。
特に、トゥシューズを履くと足の甲が出ている方が美しいとされます。
毎日足の甲をストレッチして、美しい足先を手に入れましょう!股関節ストレッチ
うつぶせになってカエルの足のように両足を曲げます。
足の裏を合わせて、合わせた足を床につけるように押してみましょう。
簡単に床についてしまう子は、足をおしりに近づけるように膝を深く曲げて押すと負荷がかかって効果が高まります。
お腹や骨盤が床から浮かないように気をつけましょう。
股関節の柔軟性もバレエにおいて非常に重要になるので、毎日の継続が大切です。ストレッチに関するお悩みを解決!

バレエを習っていると、ストレッチに関する悩みは尽きませんよね。
よくあるストレッチのお悩みを一緒に解決していきましょう!体が硬すぎても柔らかくなる?
お教室にいる他の子に比べて我が子は体が硬い…と悩んでいる方も多いですよね。
大丈夫です!
体が硬くても、ストレッチを継続することで必ず柔らかくなります。
柔軟性を高めるためには、とにかく毎日ストレッチをすることが大切なので、5分でも3分でも毎日継続してみてください。ストレッチで痛みを感じたときはどうすればいい?
ストレッチ中に子どもが痛がる…というお悩みをよく耳にします。
少しの痛みは問題ないのですが、あまりにも痛がる場合は無理に続けないでください。
押す力が強すぎたり、体が緊張して逆効果になったりする場合もあります。
息を吐きながら、少しずつ負荷を増やすように押してみてください。忙しい中で継続するコツは?
レッスンや学校の宿題、他の習い事などでなかなかストレッチの時間をとれない…という声もよく聞きます。
そんなときは、時間を決めて習慣化するのがおすすめです。
例えば、寝る前やお風呂あがりなど、日常生活の一部として取り入れると無理なく続けられます。
また、時間をかけてストレッチをするのも大切ですが、忙しいときは時間を短縮してストレッチをしてもよいでしょう。
大切なのは毎日継続することです。
短い時間でも毎日ストレッチをすることで、柔軟性を高めることができますよ。まとめ

いかがでしたか?
今回はバレエのストレッチ方法をご紹介しました。
バレエの上達に柔軟性は欠かせませんが、無理なく続けられるストレッチで少しずつ体を柔らかくすることができます。
おうちで簡単にできる方法から、親子で楽しめる方法まで、ぜひ実践してみてください。
日々の小さな積み重ねが、バレエの美しい動きを叶えてくれるはずです! -
7.112025
子どものバレエスタジオ選びで後悔しないために!親が知っておくべき4つのポイント


お子様がバレエを始めたいと言ったとき、まず考えるのはどのスタジオに通わせるかということ。
特に初めての習い事の場合、スタジオ選びは非常に重要です。
どんな雰囲気のスタジオがいいのか、指導者の経験はどうなのか、さらには通いやすさや費用まで考えなければなりません。今回は、バレエを始める子どもにぴったりのスタジオを選ぶ際に知っておきたいポイントについて、
・スタジオの雰囲気・指導方法が合ってるか
・通いやすいか
・長期的に見て成長できるスタジオか
・スタジオのサポート体制
の4つの視点から詳しくご紹介します!子どもに合ったスタジオを見つけるための「雰囲気」と「指導方法」

スタジオ選びのポイント1つ目は、雰囲気と指導方法を見ること。
お子さまに合ったスタジオを見つけるために注目すべき点をご紹介します。レッスンの楽しさが最優先!
バレエは継続が大切な習い事です。
特に小さな子どもには、楽しいと感じられるかどうかが最も重要なポイントになります。
スタジオの雰囲気が明るく、笑顔があふれるクラスであれば、子どもがレッスンを楽しみやすく、続けやすい環境が整っています。
初めて見学や体験レッスンに行ったときに、自分の子どもだけでなく、スタジオの雰囲気や他の生徒たちの表情を確認することが大切です。初心者向けのクラスがあるか?
バレエ教室のクラスには、大きく分けて年齢別のクラスとレベル別のクラスの2種類の形態があります。
バレエを初めて習う子どもには、初心者向けクラスがあるスタジオを選ぶと良いでしょう。
バレエは基礎が大切なため、初心者向けクラスで一から丁寧に教えてくれるスタジオを選ぶと安心です。
柔軟体操やリズム遊びから始めるクラスがあれば、無理なくバレエの基礎が身につきます。指導者の経験と指導歴をチェック
バレエスタジオを選ぶ際には、指導者の経験や指導歴も重要なポイントです。
豊富な経験を持つ指導者であれば、初心者の子どもにもわかりやすく指導してくれるだけでなく、子ども一人ひとりの成長をサポートしてくれるでしょう。
教室のHPがある場合、講師の経歴が描かれている場合もあるため、確認してみましょう。
また、見学や体験の際に、指導者が生徒にどのように接しているかを観察するのもおすすめです。レッスン費用や通いやすさを考慮したスタジオ選び

スタジオ選びのポイント2つ目は、通いやすさです。
バレエは継続が大切な習い事です。
バレエを続けるためには、通いやすい教室を選ぶことが重要になります。月謝の相場はどれくらい?
バレエスタジオの月謝は、地域やスタジオの規模によって異なりますが、週1回のレッスンの場合、8000円前後の月謝が相場です。
高額なスタジオもありますが、必ずしも高ければ良いというわけではなく、費用と指導内容のバランスを確認することが大切です。
初めて通う場合は、週に1回や2回のクラスから始めると良いでしょう。月謝以外の費用はかかる?
バレエスタジオには、月謝以外に発表会や衣装代、シューズなどの追加費用がかかることもあります。
特に発表会に参加する場合は、衣装代やリハーサル費用が必要になることが多いので、事前に確認しておきましょう。
発表会に出るとなると、平均10万円前後の追加費用がかかると言われています。
予算を把握して、無理なく続けられるスタジオを選ぶことが大切です。通いやすさも重要な要素!
スタジオへの通いやすさも継続のためには重要です。
学校や家から近い場所にあるスタジオであれば、送り迎えの負担も少なく、無理なく通うことができます。
バレエは継続が鍵となるため、通いやすいスタジオを選ぶと長く続けられる可能性が高まります。「長期的な成長」を見据えた選び方

スタジオ選びのポイント3つ目は、長期的な成長を見据えて選ぶことです。
バレエを長く続けていくと、コンクールへの出場やバレエ留学などを考え始める子もいます。
そうなった場合、教室を移動する子も少なくありません。
しかし、教室を変えることは子どもにとっても保護者にとっても負担が大きいですよね。
そこで先を見据えた教室選びが重要になります。楽しいだけじゃない!長期的な視点も大切
バレエは技術の習得に時間がかかるため、楽しいだけではなく長期的に成長できる環境があるかも重要なポイントです。
子どもが楽しく続けられることはもちろんですが、成長とともに新しい技術や表現力を身につけられる指導方針があるスタジオを選ぶと良いでしょう。
また、将来的にレッスン回数を増やした場合の月謝やスタジオに中学生や高校生が在籍しているかどうかなども合わせて確認しましょう。発表会やコンクールの機会があるか?
バレエスタジオによっては、発表会やコンクールへの参加機会が設けられていることもあります。
発表会に参加することで達成感が得られ、子どもが自信を持つきっかけにもなります。
また、コンクールに挑戦することで新しい目標ができ、やる気が高まる効果も期待できます。
発表会の頻度や参加費用についても、あらかじめ確認しておきましょう。スタジオの実績は?
スタジオが過去にどのような実績を持っているかも、選ぶ際の参考になります。
特にコンクールなどで優秀な成績を収めた生徒がいるスタジオや、長く運営されているスタジオは指導力が高い可能性が高いです。
実績が豊富なスタジオであれば、子どもが成長するための環境が整っているかもしれません。安心して通える!スタジオ選びで親が知っておくべきサポート体制

スタジオ選びのポイント4つ目は、安心して通えるかどうか。
バレエはケガのリスクもあるため、スタジオの安全面が気になりますよね。
また、保護者のサポート体制も気になるところです。安全性と設備の充実
バレエは跳躍やターンなど体を使う動きが多いため、安全面への配慮が必要です。
床材やバレエバーなどの設備がしっかり整っているスタジオを選ぶと安心です。
また、ケガ予防のための指導を行っているスタジオであれば、子どもが安全にレッスンを受けられます。
教室によっては月謝に保険が含まれていたり、別途加入する必要があったりする場合もあるので、事前に確認しておきましょう。親同士のコミュニティの存在
子どもが通うスタジオに、親同士の交流の場があると心強いです。
特に初めての習い事の場合、親も不安に感じることが多いですが、他の親と情報交換ができる場があれば、悩みや不安を共有しやすくなります。
保護者同士がどのように交流しているかもチェックポイントです。
また、習い事に際して、どの程度保護者のサポートが必要になるかも確認しておきましょう。
スタジオによっては、発表会の衣装を保護者で手作りしなければならなかったり、舞台裏でサポートしたりなどする場合があるため、特に仕事などが忙しい場合は要チェックです。体験レッスンでスタジオの雰囲気を確認しよう
多くのスタジオでは体験レッスンを提供していますので、子どもと一緒に実際のレッスンを体験することをおすすめします。
スタジオの雰囲気や指導者の様子を直接確認できるため、安心してスタジオ選びができるでしょう。
体験を通して、お子様が「楽しい!」と感じられるスタジオが見つかるとベストです。
また、子どもだけでなく、保護者も通わせたいと思えるスタジオに出会えるといいですね。まとめ

いかがでしたか?
お子様がバレエを始めるにあたって、スタジオ選びは非常に重要です。
楽しい雰囲気と初心者向けの指導があるスタジオ、通いやすさや費用が無理のないスタジオ、そして長期的に成長できる環境が整ったスタジオを見つけることが、バレエを続ける鍵となります。
親がサポート体制についても把握し、安心して通えるスタジオを選んでください。
みなさんにぴったりのスタジオが見つかりますように☆ -
7.112025
初心者でも簡単!美しいバレエポーズの基本とコツ


バレエといえば高く上がる足、きれいに伸びたつま先、指先までもが美しいさまざまなポーズが印象的ですよね。
そんなバレエのポーズにはたくさんの種類があります。
この記事では、バレエの基本的なポーズや美しく見せるためのコツをご紹介します!
バレエ初心者の方もベテランの方も是非参考にしてみてください♪バレエの基本の動きを覚えよう!

バレエでは足や腕のポジションに名称があります。
レッスン中にもよく聞く名称なので、是非覚えてみましょう!足のポジション
足のポジションは全部で6種類あります。
1番ポジション
両足のかかとをつけ、つま先を外側へと開いたポジションが1番です。
足首だけを動かして足を開くのではなく、足の付け根から足全体を外側へと開いていくのがポイントです。
つま先は180度開いた状態、つまり右のつま先から左のつま先まで一直線になった状態が理想ですが、初心者はまず90度を目指して練習するといいでしょう。
無理はせずに、焦らずに少しずつ足を開けるように、練習していきましょう。2番ポジション
1番ポジションから自分の足の1つから1つ半の幅を開けて立つポジションが2番です。
重心は2本の足の真ん中です。
お腹が出やすくなるため、お腹を引き上げる意識をもつことがポイントです。3番ポジション
3番ポジションは、右足(または左足)のかかとの外側と、左足(または右足)のかかとの内側がくっついている姿勢です。
2番のポジションから片足をもう一方の足の土踏まずあたりまできて重ねます。4番ポジション
4番ポジションは、3番ポジションの前にある足を足の幅1~2つ分くらいさらに前に出した状態のポジションです。
4番は上半身がねじれやすいため、真っすぐな姿勢を保てるように注意しましょう。
また、後ろに重心が傾きやすいため、真ん中にする意識が必要です。5番ポジション
5番ポジションは右足(または左足)のかかとが左足(または右足)のつま先にくっついている状態です。
4番ポジションから前に出ている足を軸足の方へと戻します。
足が前後に置かれることで、不安定になりやすく、真っすぐ立つのが意外と難しいポジションです。6番ポジション
6番は両足をくっつけ、つま先の向きがパラレル(平行)の状態です。
誰でもできると思いがちですが、意外としっかり真っすぐ立つことは難しいので、お腹が出ないように引き上げて立ちましょう。腕のポジション
バレエの腕のポジションは全部で5種類あります。
腕の位置や形によって、ポーズ全体の雰囲気や印象が大きく変わるため、指先まで丁寧に練習することが重要です。アン・バー
アン・バーは「下に」という意味です。
両腕を下ろし、肘を軽く曲げてだ円を作ります。
腕は体にくっつかないように少し離した状態で、手のひらは内側に向けます。
肘が後ろに向かないように、横に張るようにすることがポイントです。アン・ナヴァン
アン・ナヴァンは「前に」という意味です。
アン・バーをみぞおちの高さまで上げた状態です。
腕を上げたときに肩も一緒に上がらないように注意しましょう。アン・オー
アン・オーは「上に」という意味です。
アン・バーを頭の上まで上げていきます。
頭の真上ではなく、少し前にするのがポイントです。
アン・ナヴァン同様、肩が上がらないように注意しましょう。ア・ラ・スゴンド
ア・ラ・スゴンドは、「第2ポジションに」という意味です。
アン・ナヴァンから腕を横に開きます。
肘を伸ばしきらないように、大きな木を抱えているイメージを持ちましょう。アロンジェ
アロンジェには、「引き伸ばす」「長くなる」という意味があります。
手のひらを下に向けて、腕を伸ばします。
手首は折り過ぎないように気をつけましょう。
ポーズを決める際にはとても重要なポジションなので、きれいにできるようになりましょう♪初心者でもできる!基本のバレエポーズを覚えよう

ここではレッスンでもよく耳にする基本的なポーズを6つご紹介します。
すべて基本的な動作なので、是非名称を覚えてマスターしましょう♪プリエ
プリエは、膝を曲げて体を下げる動作で、バレエの基本動作のひとつです。
バレエにおいてすべての動きに関係し、ジャンプや回転などさまざまな動作の準備動作として重要な技法です。
この動作は、柔軟さと力強さを兼ね備えた足腰を育てるためにも欠かせないトレーニングです。
しっかりと膝を外側に開き、安定した体重の位置を意識して行うことがポイントです。タンジュ
タンジュは、つま先を床に沿わせて伸ばす動きです。
足先を伸ばして遠くまで届かせるイメージで動作を行うと、美しいラインが生まれます。
つま先から膝までが一直線になるよう意識して、優雅さを引き出しましょう。アラベスク
アラベスクは、片足を後ろに伸ばしてバランスを取るポーズです。
このポーズでは、軸足で体を支えながら、もう一方の足を真っ直ぐ伸ばすことで、スリムで長いラインを強調します。
背筋を伸ばして、重心を均等に保つことが美しいアラベスクのポイントです。アティテュード
アティテュードは、片足を曲げたまま空中で保つポーズで、優雅な印象を与えます。
膝を軽く曲げ、ふんわりと持ち上げるようなイメージで行うと、柔らかさと美しさが際立ちます。
上半身の姿勢も大切なので、胸をしっかりと開きながら行うと良いでしょう。ルティレ
ルティレは、片足をもう片方の足の膝まで引き上げるポーズです。
5番からルティレをし、また5番に戻す一連の動きをパッセと言い、バレエの足運びの基礎にもなります。
軸足で体を支えながら行い、上半身のバランスが崩れないように意識して行うことがポイントです。
回転系の技の際にも登場する基本的なポーズです。バレエポーズを美しく見せるためのコツ

バレエを美しく踊るためには、ポーズを美しく見せることが大切です。
そこで、ここではポーズを美しく見せるコツをご紹介します!姿勢の基本:背筋を伸ばしてエレガントに
バレエでは、正しい姿勢を保つことがとても重要です。
背筋をまっすぐに伸ばし、胸を張ってエレガントな立ち姿を意識するだけで、ポーズが美しく見えます。
また、頭を軽く持ち上げるようにすることで、さらに洗練された雰囲気が生まれます。
操り人形のように、頭を糸で持ち上げられているようなイメージを持ってやってみてください♪手足の動き:指先からつま先までのラインを意識
指先からつま先までのラインを意識することで、より一層美しい動きを表現できます。
特に手の指先までしなやかさを保ち、腕と足の伸びやかなラインが一貫するように動かすと、より洗練された印象を与えます。
美しいバレエダンサーの写真などを見ると、指の先まで美しく感じますよね。
細部に気を配ることで、バレエならではの繊細な美しさが引き立ちます。バレエならではの優雅さ:動きに余韻をつける
バレエでは、動きを途中で止めずに、余韻を持たせることが重要です。
動きの流れを感じながら、静かに次のポーズに移ることで、滑らかで優雅な印象を与えることができます。
動作の終わりを意識せず、常に連続しているかのような柔らかい動きがバレエの美しさを際立たせます。自宅でできる!バレエポーズの練習方法

バレエは基礎がとても大切です。
教室でのレッスンだけではなかなか上達は感じにくいもの。
そこで重要なのが自宅でのトレーニングや自主練習です。
ここでは自宅でできるポーズの練習方法をご紹介します!鏡を使ってフォームをチェック
自宅でのバレエ練習には、鏡を使ってフォームを確認する方法がおすすめです。
鏡を見ながらポーズをとることで、正しい姿勢やラインがキープできているかを確認できます。
気になる部分をその場で修正できるので、効果的に上達することが可能です。
全身が映る鏡を是非用意してみましょう。スマホで動画を撮ってセルフチェック
全身が映る鏡がなかったり、置く場所がなかったりする場合には、スマホで動画を撮影して自分の動きをチェックする方法も有効的です。
動画を撮影することで、後から自分の動きを確認し、改善点を見つけやすくなります。
ポーズの細かなラインや動きの滑らかさもチェックし、練習に役立てましょう。ストレッチとポーズを組み合わせたトレーニング
柔らかな動きと美しいラインを作るためには、体の柔軟性が不可欠です。
柔軟性を高めるために、ストレッチとポーズを組み合わせたトレーニングも取り入れてみましょう。
定期的なストレッチで体をほぐしつつ、ポーズの練習をすることで、より美しいバレエの動きができるようになります。
ストレッチバンドなどを使うことで、柔軟性を高めつつポーズに必要な筋力を同時に鍛えることができます。まとめ

バレエの基本的なポーズを覚え、美しく見せるためのコツを意識することで、初心者の方も自信を持って踊れるようになります。
背筋や手足のラインを意識しながら、自宅での練習も続けていくと、さらにポーズが安定し、優雅さが増すでしょう。
美しいバレエのポーズを身につけて、ぜひ自分らしいバレエを楽しんでくださいね! -
7.112025
華やかさと大人な雰囲気が魅力『パキータ』のあらすじとヴァリエーションを徹底解説!!


華やかな衣装に大人っぽい雰囲気のヴァリエーションが多い『パキータ』
コンクールや小作品集で見かける機会も多く、一度は踊ってみたいヴァリエーションと憧れている方も多いのではないでしょうか。
そんな『パキータ』ですが、全幕公演は珍しく、あらすじや登場人物など実はよく知られてない場合も。
今回は『パキータ』のあらすじや登場人物、登場するヴァリエーションまで徹底解説していきます!!
気になる方は参考にしてみてくださいね!!
『パキータ』について知ろう!!

独特の華がある『パキータ』はフランスで作られた作品です!!
まずは、『パキータ』の概要や登場人物について紹介します。
『パキータ』の概要
『パキータ』 (Paquita) は、1846年にフランスで作られた全2幕3場のバレエ作品です。
原振付はジョゼフ・マジリエ、音楽はエドゥアール・デルデヴェス。
舞台はナポレオン軍占領下のスペインで、ジプシーの娘パキータがフランス軍将校リュシアンを陰謀から救う恋物語となっています。
民族色あふれるスペイン風の踊りやジプシーの踊りが見せ場の1つとなっており、若きマリウス・プティパがロシアで初めて演出を手がけた作品としても知られています。
初演は1846年4月1日にパリの帝室音楽アカデミー(現在のオペラ座)で行われました。
今日ではプティパ版の抜粋(音楽はレオン・ミンクス)が1幕の作品として上演されることが多いですが、まれに全幕公演が行われることもあります。
登場人物
『パキータ』には個性豊かな人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・パキータ(ジプシーの美しい娘・実は貴族の娘)
・リュシアン・デルヴィリ(フランスの伯爵・パキータに恋をする)
・イニゴ(ジプシーのリーダー、パキータを自分のものにしようとする)
・ドン・ロペス(スペイン人の地方監督、フランス人をよく思っていない)
・コント・デルヴィリ(リュシアンの父)
主役はジプシーの娘として育てられたパキータです。
フランス軍将校リュシアンとの恋物語がストーリーの主軸となっています。
『パキータ』全2幕のあらすじを知ろう!!

全幕公演が珍しく、実はそのストーリーはあまり知られていないのが『パキータ』
しかし、あらすじを理解しておくことで役の表現がしやすくなりますね。
『パキータ』の第1幕と第2幕のあらすじを紹介していきます。
『パキータ』第1幕のあらすじ
舞台はサラゴサ郊外の谷間。
デルヴィリ将軍と息子のリュシアン、総督ロペス、ロペスの妹セラフィナらが集まっていました。
戦役で権力者となったデルヴィリ伯爵は、息子を総督の妹と縁組させようとしていますが、リュシアンは愛情を感じないセラフィナとの結婚には気乗りしていない様子。
ロペスもまた自国に攻め込んできたフランス人たちを心密かに憎んでいました。
その時、イニゴの率いるジプシーの一団が山から下ってきます。
この中にジプシーらしからぬ雰囲気のパキータがいました。
リュシアンは一瞬で彼女に惹きつけられますが、一方でイニゴ(ジプシーのリーダー)も以前からパキータに好意を抱いていました。
そのため、リュシアンに対して激しく嫉妬するイニゴ。
2人は衝突しそうになりますが、総督のとりなしで何とかその場は収まります。
イニゴがリュシアンに敵意を抱いていることを見てとった総督ロペスは、イニゴを雇ってリュシアンを暗殺する計画を思いつきます。
『パキータ』第2幕のあらすじ
シーンはジプシーの集落。
パキータは昼間に出会った将校リュシアンが忘れられず思い悩んでいます。
そこへ、仮面をつけたロペスとイニゴが現れたことで、リュシアン暗殺の計画を知ってしまったパキータは驚き、なんとか計画を阻止したいと考えます。
やがてリュシアンがやってきて、食事と一緒に毒が入ったお酒を渡されます。
パキータはなんとかリュシアンにお酒を飲ませないようにし、パキータの様子がおかしいことにリュシアン気づきます。
そして、パキータは一瞬の隙をついてイニゴとリュシアンのお酒を入れ替えました。
すると、毒入りのお酒を飲んでしまったイニゴは倒れこんでしまいます。
その隙に、2人は逃げ出しその場を後にするのでした・・。
上手く逃げ出すことができた2人はフランス将軍主催の舞踏会に参加します。
そこにはイニゴとリュシアン暗殺計画を企てたロペスがいました。
パキータがロペスに気づいたことで、ロペスは連行されていきます。
リュシアンは自分の命を救ってくれたパキータに求婚しますが、パキータはどうしても身分の差が気になってしまいます。
そんな時、壁に飾られた肖像画がパキータの目に入ります。
その肖像画はパキータが幼い頃からずっとつけていたロケットペンダントの中の肖像画と同じものだったのです!
その肖像画の人物はリュシアンの叔父であるシャルル・デルヴィイーでした。
実はパキータはシャルル・デルヴィイーの娘で、リュシアンとはいとこ同士であることが判明しました。
パキータの身分が明らかになり身分の差がなくなった2人は晴れてめでたく結ばれます。
『パキータ』に登場するヴァリエーションはいくつある!?ヴァリエーションまとめ

実は『パキータ』に登場するヴァリーションの数は正確には決まっていません。
プティパのオリジナルの演出ではパキータのヴァリエーションは7つとなっていましたが、再演や改訂が繰り返される中でヴァリエーションが追加や変更されていきました。
その影響もあり現在では、数多くのパターンのヴァリエーションが踊られています。
『パキータ』に登場するパ・ド・トロワとヴァリエーションについて紹介します。
『パキータ』に登場するパ・ド・トロワ
パ・ド・トロワとは女性2人と男性1人が踊ることです。
『パキータ』に登場するパ・ド・トロワ の一覧は下記の通りです。
・パ・ド・トロワ 第1ヴァリエーション(パ・ド・トロワの中の女性が踊るヴァリエーション)
・パ・ド・トロワ 第2ヴァリエーション(パ・ド・トロワの中の女性が踊るヴァリエーション)
・パ・ド・トロワ 第3ヴァリエーション(パ・ド・トロワの中の男性が踊るヴァリエーション)
『パキータ』のパ・ド・トロワに登場するヴァリエーションは発表会やコンクールで見かけることが多い人気のものとなっています!
『パキータ』に登場するヴァリエーション
ヴァリエーションの数が多いのも『パキータ』のみどころの1つです!
全幕公演は珍しく、公演によって演出も異なり登場するヴァリエーションも様々な場合があり、使用されている曲も様々な作品から引用されています。
『パキータ』に登場する可能性の高いヴァリエーションの一覧を紹介します!
※カッコ内はヴァリエーションに使用される音楽です。
・第1ヴァリエーション(リッカルド・ドリゴ作曲の「泉」)
・第2ヴァリエーション(チェーザレ・プニ作曲の「ナイアードと漁夫」)
・第3ヴァリエーション(リッカルド・ドリゴ作曲の「カウンダウル王」よりニシアのヴァリエーション)
・第4ヴァリエーション(「ドン・キホーテ」よりキューピットのヴァリエーション)
・第5ヴァリエーション(ニコライ・チェレプニン作曲の「アルミードの館」)
・第6ヴァリエーション(『パキータ』よりエトワールのヴァリエーション)
・第7ヴァリエーション(ユリー・ガーバー作曲の「トリルビ」)
・第8ヴァリエーション(『パキータ』よりリュシアンのヴァリエーション)
・第9ヴァリエーション(『パキータ』 よりエカテリーナ・ヴァーゼムのバリエーション)
『パキータ』特に有名・人気のヴァリエーション
上記で紹介したヴァリエーションの中でも特に有名で人気のあるヴァリエーションについて詳しく解説します。
ヴァリエーション選びの参考にしてみてくださいね!!
- ・パ・ド・トロワ 第1ヴァリエーション(パ・ド・トロワの中の女性が踊るヴァリエーション)
回転系のテクニックから跳躍系のものまでまんべんなく入っているのがこのヴァリエーションです。
そのため、ヴァリエーションを踊る初心者にもオススメです。
曲の早さもそこまで早くないので練習しやすいでしょう。
- ・第6ヴァリエーション(『パキータ』よりエトワールのヴァリエーション)
コンクールや発表会で良く目にする『パキータ』の有名なヴァリエーションは第6ヴァリエーション(エトワール)です。
バレエダンサーには階級があり最高位はプリンシパルといわれていますが、パリ・オペラ座ではエトワール(フランス語で星の意)と称されています。
このことからパキータ第2幕で結婚の喜びを表すソロの踊りは「パキータ エトワール』のヴァリエーションと呼ばれています。
- ・第8ヴァリエーション(『パキータ』よりリュシアンのヴァリエーション)
男性の主役であるリュシアンのヴァリエーションは難易度の高いテクニックが組み込まれており中級者以上向けのレベルとなっています。
『ドン・キホーテ』のバジルにも似たコンビネーションで前半は跳躍系、後半は回転系の動きで構成されているので、まんべんなくテクニックをこなす必要があります。
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

発表会や小作品集では第2幕の舞踏会の様子のみが描かれていることが多く、全幕公演は珍しい印象です。
しかしながら、まれに全幕公演が行われる場合も・・。
その際にあらすじやみどころを把握しておくことで見逃しがなく、より『パキータ』を楽しめそう!!
たくさんのヴァリエーションが登場しますので、何のヴァリエーションを踊るか考え中の方にもぴったりの演目となっています。
-
7.112025
ダイナミックで勇ましいバレエ作品『海賊』の全幕を徹底解説!


バレエ作品の1つである『海賊』はヴァリエーションや短編集などではよく耳にしますが、実は全幕のストーリーを知らないという方も多いかもしれません。
最近では日本でも『海賊』を全幕上演するバレエ団も増えたので、全幕公演を観れる機会も多くなりました。
今回は『海賊』のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションなどを紹介します。
『海賊』のヴァリエーションを踊ってみたい、『海賊』の全幕公演を観に行く予定の方などは参考にしてみてください!!
『海賊』について知ろう!!

『海賊』は他の三大バレエやロマンティックバレエ作品とは違った、ダイナミックでワイルドな雰囲気のあるバレエ作品です。
まずは、『海賊』の概要や登場人物について紹介します。
『海賊』の概要
『海賊』(かいぞく、仏: Le Corsaire) は、 アドルフ・アダンの作曲したバレエ音楽、およびそれを用いたバレエ作品です。
ギリシア独立戦争に参加した、イギリスの詩人ジョージ・ゴードン・バイロンによって1814年に長編物語詩 『海賊』 をもとに作られました。
台本はジョゼフ・マジリエとジュール=アンリ・ヴェルノワ・ド・サン=ジョルジュ、振付はジョゼフ・マジリエ。
後にチェーザレ・プーニ、レオ・ドリーブ、リッカルド・ドリゴ、レオン・ミンクスらによる楽曲が追加され、近年の舞台では1899年にマリウス・プティパにより振り付けられた改訂版をベースとすることが多いです。
初演は、1856年1月23日、パリ・オペラ座で行われ、主役のメドーラとコンラッドは、それぞれカロリーナ・ロザティとドメニコ・セガレッリが演じました。
登場人物
『海賊』には数々の個性豊かな人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・メドーラ(ギリシアの美しい娘)
・コンラッド(海賊の首領(かしら))
・ランケデム(奴隷商人でメドーラやギュリナーラ達を奴隷として売買する)
・パシャ(トルコ総督で女奴隷たちを集めてハーレムにし、美女を何人も夫人にしている)
・ビルバント(海賊でコンラッドの手下)
・アリ(コンラッドの忠誠な奴隷)
・ギュリナーラ(ギリシアの美女でメドーラと仲良し。奴隷市場に出さてしまう)
メドーラやギュリナーラのヴァリエーションはコンクールなどでも多く踊られているので名前を聞いたことがある人も多いでしょう。
『海賊』第1幕

『海賊』はバレエ作品では珍しく男性ダンサーが多く登場する作品でもあります。
第1幕では海賊とその手下や、ギリシャの美女など物語に重要なポジションの登場人物が次々に登場します。
『海賊』第1幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションを紹介しますので、見逃しのないようにチェックしておきましょう!!
『海賊』第1幕のあらすじ
ストーリーは海賊の領主コンラッド率いる海賊船が嵐に巻き込まれ沈没するプロローグから始まります。
コンラッド(海賊の首領)とビルバント(コンラッドの手下)、アリ(コンラッドの奴隷)はギリシャに面した地中海の浜辺に流れ着きます。
3人は偶然通りかかったギリシャの娘、メドーラとギュリナーラに助けられます。
このことがきっかけでコンラッドとメドーラは恋に落ちるのでした。
しかし、そこへトルコ兵がやってきてメドーラたちは捕らえられてしまい、奴隷市場へと連れ去られてしまいます。
コンラッドたちはメドーラたちを助けようと決心します。
奴隷市場では奴隷商人のランケデムが集められた奴隷たちを売り買いし活気に溢れています。
トルコ総督のパシャは、自分の宮殿に招き入れるための美しい美女を探しに奴隷市場を訪れます。
そこで、美しいギュリナーラが競りにかけられているのを一目見たパシャはギュリナーラをすぐに競り落とします。
続いて、メドーラが競りに出されるとパシャは彼女の美しい容姿に魅了され、どんな価格でも手に入れる決心をします。
そこへやってきた商人に扮したコンラッドは「さらに高値で引き取る」と申し出ます。
その高すぎる値段に、パシャはコンラッドの正体を怪しみます。
正体がバレそうになったコンラッドは、自ら正体を明し、その混乱に紛れてメドーラと女奴隷たちを救い出し、奴隷商人のランケデムを連れて姿をくらまします。
『海賊』第1幕のみどころ
バレエ作品では女性ダンサーがメインであることが多いですが『海賊』の場合は男性ダンサーがメインとなりストーリーが展開されます。
また、奴隷市場ランケデムと売りに出されるギュリナーラのグラン・パ・ド・ドゥが踊られます。
日本では「奴隷のパ・ド・ドゥ」とも呼ばれることもあり、短編集を集めたガラ公演や発表会などでも人気です。
『海賊』第1幕のヴァリエーション
『海賊』では第1幕から多くのヴァリエーションが登場します。
『海賊』第1幕に登場するヴァリエーション一覧は下記の通りです。
・メドーラのヴァリエーション
・※オダリスクの第1ヴァリエーション
・※オダリスクの第2ヴァリエーション
・※オダリスクの第3ヴァリエーション
・ランケデムのヴァリエーション
・ギュリナーラのヴァリエーション
男性ダンサーが多い中、女性ダンサー3名のオダリスクは華やかで美しいです。
ぜひチェックしてみてください!
※オダリスクとは女性の奴隷のことで、3人のダンサーによるパ・ド・トロワの踊りです。 アントレ・第1〜第3ヴァリエーション・コーダ の一連の踊りとなっています。
『海賊』第2幕

第1幕に引き続き、海賊たちや奴隷商人が物語を牽引します。
ドキドキの展開から目が離せない第2幕!
『海賊』第2幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションを紹介しますので、見逃しのないようにチェックしておきましょう!!
『海賊』第2幕のあらすじ
海賊たちの潜む洞窟では、海賊たちがメドーラたちを助け出したことを祝って宴が行われています。
メドーラはランケデム(奴隷商人)に一緒に捕まっていた女奴隷の解放をお願いします。
しかし、コンラッド以外の海賊は全員反対します。
海賊たちの反対を押し切り、女奴隷たちを解放してあげるコンラッド。
このことがきっかけでコンラッドに不満を抱いたビルバンド(コンラッドの手下)はランケデムと共謀しコンラッドに罠を仕掛けます。
メドーラに睡眠薬を振りかけた花束を渡し、何も知らないメドーラは友人たちを救ってくれたお礼にとコンラッドにその花束を渡してしまいます。
コンラッドはぐっすりと眠りについてしまい、ビルバンドはコンラッドを殺害しようと試みます。
そのことに気づいたメドーラは抵抗しますが、この混乱に乗じてランケデムはメドーラを捕まえ洞窟から逃げ出します。
『海賊』第2幕のみどころ
第1幕に引き続き男性ダンサーがストーリー展開のメインとなっています。
特に第2幕の「海賊の潜む洞窟」の場面では海賊たちのダイナミックで勇ましい踊りを観ることができます!!
また、コンラッド、メドーラ、アリによるパ・ド・トロワもこの場面で踊られますので見逃さないようにしましょう!
『海賊』第2幕のヴァリエーション
『海賊』第2幕では前述のコンラッド、メドーラ、アリによるパ・ド・トロワによる、それぞれのヴァリエーションが登場します。
下記は『海賊』の第2幕に登場するヴァリエーションの一覧です。
・アリのヴァリエーション
・メドーラのヴァリエーション
・コンラッドのヴァリエーション
『海賊』第2幕では海賊たちの踊りの他にも、男性のヴァリエーションがみどころの1つ。
男性で何のヴァリエーションを踊ろうか考えている方も参考になりそうです!
『海賊』第3幕

今までのダイナミックで勇ましい雰囲気とは一転、美しい花園のシーンに目を奪われます。
また、コンラッドとメドーラはどうなってしまうのか・・。
その結末から目が離せません!
『海賊』第3幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションを紹介します!!
『海賊』第3幕のあらすじ
場面はパシャ(トルコ総督)の美しい女性たちを集め花園が築かれた宮殿。
パシャは奴隷市場で見つけたギュリナーラの踊りに満足していましたが、他の女性たちからは不満を持たれていました。
そんな中、奴隷商人のランケデムがメドーラを連れてやってきます。
メドーラが自分の元に戻ったことを喜ぶパシャ。
上機嫌になっているパシャは、メッカへの巡礼へ向かう一向に「一晩泊めて欲しい」と頼まれ快諾します。
しかし、実は彼らの正体はメドーラたちを救いにきたコンラッドたちだったのです!
パシャの隙をついたコンラッドはメドーラたちを救出し、海賊船に乗り込みます。
新たな旅に向けて出発した海賊たちでしたが、船は嵐に遭遇し沈没してしまいます。
コンラッドとメドーラだけが奇跡的に助かることができ物語は終わりを迎えます。
『海賊』第3幕のみどころ
第1幕と第2幕では男性ダンサーがメインで活躍し、冒険や勇ましい踊りが繰り広げられましたが、第3幕では美しい花園シーンが登場します。
その美しさはクラシックバレエらしく、ロマンティックな雰囲気です。
踊りも男性たちによる勇ましいものとは打って変わり、優雅で美しい女性の踊りやヴァリエーションが披露されます。
『海賊』第3幕のヴァリエーション
第3幕のパシャの花園では女性ダンサーのヴァリエーションが登場します。
下記は『海賊』の第3幕に登場するヴァリエーションの一覧です。
・ギュリナーラのバリエーション
・メドーラのバリエーション
『海賊』は同じシーンでもバレエ団によって異なるヴァリエーションが披露されることも多いです。
それぞれの違いを楽しむのも『海賊』を観る楽しみかもしれませんね。
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

女性、男性ともにコンクールや発表会でよく見かける『海賊』のヴァリエーション。
『海賊』自体、ヴァリエーションの多い作品ですので「何を踊るか迷っている」という方は必見です。
男性ダンサーが多く登場し、メインでストーリー進行していきますので、バレエをしている男の子や男性も参考になることが多いでしょう!
ぜひ、この機会に『海賊』の全幕公演を観てみてくださいね!
-
7.112025
3大バレエの1つ!『くるみ割り人形』の全幕を徹底解説!


毎年、秋が過ぎた頃の冬の始まりからクリスマスにかけて『くるみ割り人形』の公演が多く上演されます。
様々なバレエ団がそれぞれの個性あふれる公演を行います。
今回は冬の定番演目である『くるみ割り人形』のあらすじやみどころを全幕解説していきます!
気になっている方は参考にしてみてくださいね!!
チャイコフスキーの名作!!『くるみ割り人形』について知ろう

『くるみ割り人形』はピョートル・チャイコフスキーが作曲したバレエ音楽で、その楽曲を用いた、バレエ作品でもあります。
チャイコフスキーが手掛けた最後のバレエ音楽で、バレエの公演は1892年にサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で初演されました。
『くるみ割り人形』の原作はドイツのE.T.A.ホフマンによる童話『くるみ割り人形とねずみの王様』を、アレクサンドル・デュマ・ペールがフランス語に翻案した『はしばみ割り物語』です。
クリスマスにちなんだ作品なので、毎年クリスマス・シーズンには世界中で上演されています。
クラシック・バレエを代表する作品の1つで、同じくチャイコフスキーが作曲した『白鳥の湖』『眠れる森の美女』と共に「3大バレエ」となっています。
登場人物
『くるみ割り人形』には数々の魅力的な人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・クララ(マリー・マーシャ):主人公の少女
・王子:お菓子の国の王子
・ドロッセルマイヤー:人形遣いのおじさん
・フリッツ:クララの弟
・くるみ割り人形:変身させられた王子
・ねずみの王様:ねずみたちのボス
・雪の精(※コールド)
・スペイン(チョコレート)
・アラビア(コーヒー)
・中国(お茶)
・ロシア(トレパック)
・フランス(葦笛)
・金平糖の精
・花のワルツ(コールド)
※コールドについて
群舞の集団を意味し、ソリスト以外の、群舞や大人数の情景を担当するダンサーをひとまとめに指していいます。
バレエ団によって異なる主役やストーリー展開
実は『くるみ割り人形』は公演を行う国やバレエ団によって主役が異なることがあります。
主役であるクララの名前もマーシャやマリーといった呼ばれ方をすることも。
また、「クララが少女で金平糖がお菓子の国の女王という設定」や「クララが成長して金平糖の精を踊るという設定」といったストーリー展開や設定も異なります。
そういった演出も『くるみ割り人形』を観る際の楽しみの1つですね!
『くるみ割り人形』第1幕

『くるみ割り人形』は全2幕で上演時間は約2時間10分~2時間15分程度と他のバレエ演目に比べ短めなためお子さまにも観やすい作品です
そして、第1幕にはクリスマスを楽しむ子どもたちや、謎めいたドッセルマイヤー、ネズミたちとの戦いなど盛りだくさん!
『くるみ割り人形』の第1幕の詳しいあらすじやみどころについて紹介します。
『くるみ割り人形』第1幕のあらすじ
クララの家でクリスマスパーティーが開かれ、招かれたお客たちが雪道の中続々と集まります。
そして、楽しいクリスマスパーティーでしゃぐ子どもたちと、おしゃべりに花を咲かせる大人たち。
そんな中、遅れてやってきたのは少し怪しい雰囲気のあるドッセルマイヤーです。
ドッセルマイヤーはクララのお父さんの友人の人形師で、子どもたちにピエロやムーア人形といった機械仕掛けの人形を踊らせてみせてくれます。
そして、クララに少し変わったくるみ割り人形をプレゼントしてくれました。
クララはくるみ割り人形をとても気に入りましたが、兄のフリッツがからかいクララからくるみ割り人形を取り上げ壊してしまいます。
その様子を見ていたドッセルマイヤーはフリッツをしかり追い払います。
やがて、クリスマスパーティーはお開きになり、来客たちが雪の中帰っていきます。
みんなが眠りについたところ、クララはふと目を覚まし広間にやってきます。
すると突然、ネズミの大群が現れ、クララは襲われそうに!
そこへ、くるみ割り人形が現れクララをかばい戦いますが、がなかなかネズミに勝てません。
そして、クララも応戦することで、ネズミたちはようやく退散します。
するとくるみ割り人形は美しく立派な王子に代わり「ネズミから救ってくれたお礼にクララを、一面雪の世界を通り※お菓子の国へと導きます。
※お菓子の国は公演によって異なり、魔法の国や人形の国と表現されることもあります。
『くるみ割り人形』第1幕のみどころ
『くるみ割り人形』第1幕のみどころは楽しいクリスマスの雰囲気が一転し、怪しい雰囲気のドッセルマイヤーが繰り出す機械人形(人が演じています)にクギ付けになる場面。
また、ドッセルマイヤーがクララにくれたくるみ割り人形も不思議な雰囲気のある人形なのでこれからの展開が気になる重要なアイテムとなります。
ネズミの大群とクララ、くるみ割り人形の戦いはドキドキ、ハラハラ!
そして、くるみ割り人形が王子となりお菓子の国へ行く際に登場する、幻想的な雪の精たちの踊りにも注目です。
くるみ割り人形』第1幕のヴァリエーション
『くるみ割り人形』は第1幕にはヴァリエーションはありません。
しかしながら、クララが1人で踊るシーンや、ネズミとの戦いのシーン、雪の精のコールドバレエは有名なシーンとなっていますので注目度が高いです。
見逃さないようにしましょう!
『くるみ割り人形』第2幕

お菓子の国へと旅立ったクララと王子が到着したのは、様々な国のお菓子の精が登場する華やかで可愛い世界でした。
個性豊かなお菓子の精たちの踊りやクライマックスが気になる第2幕のあらすじやみどころなどを紹介します!!
『くるみ割り人形』第2幕のあらすじ
お菓子の国に到着したクララと王子は、様々な国のお菓子の精に歓迎されます。
そして、お菓子の精による華やかな宴が始まります。
まず、踊りを披露するのはチョコレートの精(スペインの踊り)そして、コーヒーの精(アラビアの踊り)、お茶の精(中国の踊り)、トレパック(ロシアの踊り)、あし笛(フランスの踊り)と続きます。
コールドバレエの花のワルツも華やかに登場し、ラストを飾るのは王子と金平糖の精のパ・ド・ドゥです。
そして、お菓子の国全員で華やかな※コーダを踊り、クララは再び夢の中へ・・。
目を覚ますとそこはクララの家の広間でした。
横には壊れたくるみ割り人形が。
クララが体験した出来事は夢だったのでしょうか?
クララは愛おしそうにくるみ割り人形を抱え、ストーリーは終わります。
※バレエにおけるコーダ(Coda)とは、幕の終わりに大団円を迎える部分をさします。楽曲においては、独立してつくられた終結部分のことです。
『くるみ割り人形』第2幕のみどころ
第2幕のみどころは何といっても個性的なお菓子の国のお菓子の精たち!
それぞれの国の特徴を掴んだ個性的で可愛いお菓子の精が踊る踊りは『くるみ割り人形』の定番で、発表会などでも上演されることが多いです。
また、王子と金平糖の精の王子と金平糖の精のパ・ド・ドゥはクライマックスにふさわしく、うっとりするほど華やかです。
くるみ割り人形が王子になる設定と同様に、クララが金平糖の精になる設定も存在します。
くるみ割り人形がお菓子の国の女王という設定もあります。
『くるみ割り人形』第2幕のヴァリエーション
『くるみ割り人形』の第2幕では王子と金平糖の精のパ・ド・ドゥがあるので、それぞれのヴァリエーションも存在します。
また、ソロではない場合も多くありますが各国のお菓子の精のヴァリエーションも個性豊かで『くるみ割り人形』第2幕を観る楽しみの1つ!
下記は『くるみ割り人形』の第2幕に登場するヴァリエーションの一覧です。
・チョコレートの精(スペインの踊り)
・コーヒーの精(アラビアの踊り)
・お茶の精(中国の踊り)
・トレパック(ロシアの踊り)
・あし笛(フランスの踊り)
・王子のヴァリエーション
・金平糖のヴァリエーション
王子のヴァリエーションと金平糖のヴァリエーションはコンクールでも踊られることも多い人気のヴァリエーションです!
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

発表会の演目でも人気のある『くるみ割り人形』はバレエの定番といっても過言ではありません。
上演される国やバレエ団によってストーリーの設定や展開が異なるため、何度観ても楽しめる作品です。
毎年、冬の始まりを感じる11月頃から上演されることが多いので、興味がある方は一度観にいってみてくださいね!
クリスマス気分を盛り上げたいという方も必見です!!
-
7.112025
コミカルで華やか!!『ドン・キホーテ』の全幕を徹底解説!


明るくコミカルな『ドン・キホーテ』は誰でも楽しめるバレエ作品です。
バレエらしい華やかなシーンや幻想的なシーンまで、みどころもたくさん!
『ドン・キホーテ』を観る際に、さらに楽しめるよう、あらすじやみどころ、登場するヴァリエーションなどについて詳しく解説していきます!
鑑賞を予定している方や検討中の方は参考にしてみてくださいね!!
ドン・キホーテは実は脇役!?『ドン・キホーテ』について知ろう!!

登場人物が多くドタバタ劇がコミカルな『ドン・キホーテ』
実は主役はドン・キホーテではないんです!
登場人物について良く知っておくとストーリーを理解しやすいので、『ドン・キホーテ』の概要や登場人物について紹介します。
『ドン・キホーテ』の概要
『ドン・キホーテ』(英: Don Quixote)は、セルバンテスによる同名小説を翻案したバレエ作品です。
振付家マリウス・プティパがレオン・ミンクスの楽曲を用いて創作し、1869年12月26日にモスクワのボリショイ劇場で初演されました。
1900年に、振付家アレクサンドル・ゴルスキーが、プティパ版の大幅な改訂を行い、現在上演されている『ドン・キホーテ』の演出のほとんどがゴルスキーによる改訂版を基とされるようになりました。
『ドン・キホーテ』のストーリーはスペインのバルセロナを舞台に、主人公のカップルが親の反対を乗り越えて結婚に至るまでを描いた喜劇が主軸となっています。
そのため、実はタイトル・ロールであるドン・キホーテは脇役として登場します。
クラシック・バレエならではの高度なテクニックやスペイン舞踊、コミカルな演技が取り入れられた華やかな演目となっています。
登場人物
『ドン・キホーテ』には数々の個性豊かな人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・キトリ(主人公の明るく強気な女性でバジルの恋人)
・バジル(キトリの恋人で、床屋の息子)
・ドン・キホーテ(自称「騎士の旅人」)
・サンチョ・パンサ(ドン・キホーテの従者)
・ガマーシュ(街のお金持ちの貴族)
・ロレンツォ(キトリの父親で、金持ちの貴族ガマーシュと結婚させようとしている)
・エスパーダ(闘牛士)
・メルセデス(エスパーダの恋人)
・キトリの友人(キトリと幼なじみ、キトリとバジルを見守ります)
・ドルネシア姫(ドン・キホーテの夢の中に登場するお姫様)
・キューピット
・森の女王
このように『ドン・キホーテ』は登場人物が多い作品です。
これから、あらすじを通して詳しくみていきましょう!!
『ドン・キホーテ』第1幕

『ドン・キホーテ』第1幕はプロローグから始まり、賑やかなバルセロナ広場へと場面が変わります。
詳しいあらすじや、みどころ、登場するヴァリエーションなど見逃しがないよう、紹介していきます!
『ドン・キホーテ』第1幕のあらすじ
プロローグはとある村から始まります。
村に住む郷士(ごうし)アロンソ・キハーノは中世の騎士物語に夢中になっていました。
物語に夢中になるあまり、次第に現実と物語の区別がつかなくなってしまったアロンソは、自分が物語の主人公ドン・キホーテだと思い込み、服装から立ちふるまいも中世の騎士のようになっていきます。
そして、ついには空想の人物であるドルネシア姫を探すため、付き人のサンチョ・パンサと共に旅へと出発します。
場面は人々が行き交う活気に満ち溢れた、バルセロナの街の広場へと変わります。
この街では宿屋の看板娘のキトリと床屋の息子バジルが暮らしています。この2人は恋人同士で、いつも一緒ですが、キトリの父親ロレンツオはお金持ちの貴族マーシュとキトリと結婚させようと考えています。
しかし、そんな父親のもくろみも気にせず、キトリはバジルは一層仲良しです。
広場にはエスパーダ(闘牛士)たちが登場し、さらに活気づきます。
そこへやってきた、ドン・キホーテとサンチョ・パンサ。
街の人々は時代遅れの格好をしたドン・キホーテに驚きを隠せません。
そして、ドン・キホーテはキトリをドルネシア姫だと思い込んでしまいます。
そんな中、サンチョ・パンサが盗み食いをしたと勘違いされ、街中が大騒ぎに!
大騒ぎの中、キトリとバジルは街から逃げ出します。
キトリがいないことに気づいたドン・キホーテとサンチョ・パンサは慌てて2人を追いかけます。
『ドン・キホーテ』第1幕のみどころ
『ドン・キホーテ』第1幕のみどころは、賑やかな街で繰り広げられるドタバタ劇(ドタバタは続きます。笑)
バレエにはセリフがありませんが、キトリとバジルの仲の良さや、ドン・キホーテが中世の騎士姿で街に現れるコミカルさなどが描かれています。
また、キトリの父親の思惑も今後のストーリー展開に重要なポイントなので知っておくと展開がわかりやすいでしょう。
『ドン・キホーテ』第1幕のヴァリエーション
『ドン・キホーテ』第1幕に登場に登場するのはキトリのヴァリエーションです。
このヴァリエーションの長さは1分弱と短いですが、脚を素早くあげる、背中を反らせて大きなジャンプをする、連続でターンを回るといった高度なテクニックが含まれます。
また、テクニックをこなすだけでなくキトリの明るく活気のある性格や気の強さなどを表す表現力が必要となります。
中級レベル程度の難易度で、コンクールでも見かける人気のヴァリエーションとなっています。
『ドン・キホーテ』第2幕

『ドン・キホーテ』第2幕ではキトリとバジルは逃げ切ることができるのかと、ドン・キホーテの夢は叶うのかが描かれます。
どちらも展開が気になりますね!
それでは、『ドン・キホーテ』第2幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションをみていきましょう!!
『ドン・キホーテ』第2幕のあらすじ
街を後にしたキトリとバジルはジプシーたちが集まる場所までやってきました。
最初はジプシーたちに怪しまれてしまう2人でしたが、駆け落ちをしたことを伝えるとすぐに歓迎の踊りを披露してくれました。
そこへ、ドン・キホーテとサンチョ・パンサもやってきました。
ジプシーによる人形劇を観たドン・キホーテは、劇中に登場した悪役を本物の悪者だと勘違いし倒そうと飛びかかります。
そして、次には風車を悪者だと勘違いし、槍(ヤリ)を持ち突進してしまいます。
風車に舞い上げられたドン・キホーテは気絶してしました・・。
意識を失ったドン・キホーテは夢を見ます(ドン・キホーテの夢の場)
夢の中で森の中にいるドン・キホーテは、探し求めていたドルネシア姫やキューピット、森の女王に出会いました。
探し求めていたドルネシア姫が美しい踊りを披露し、キューピットや森の女王も続けて踊りを披露します。
キューピットに胸を打たれたドン・キホーテはようやく目を覚まします。
そこへ、キトリの父親ロレンツォと貴族のガマーシュがやってきてキトリとバジルの後を追います。
『ドン・キホーテ』第2幕のみどころ
『ドン・キホーテ』第2幕のみどころはなんといっても、ドン・キホーテの夢の中の様子が描かれた「夢の場」のシーンです。
幻想的な森の中で美しいドルネシア姫やキューピット、森の女王が登場します。
発表会ではこの「夢の場」を演目に入れている場合も多く有名で人気のあるシーンとなっています。
『ドン・キホーテ』第2幕のヴァリエーション
『ドン・キホーテ』第2幕の「夢の場」では多くのヴァリエーションが披露されます。
下記は『ドン・キホーテ』の第2幕に登場するヴァリエーションの一覧です。
・ドルネシア姫のヴァリエーション
・キューピットのヴァリエーション
・森の女王のヴァリエーション
上記のヴァリエーションはコンクールや発表会でも、よく踊られています。
特にキューピットのヴァリエーションはお子さまが挑戦しやすいので人気が高いです!
『ドン・キホーテ』第3幕

『ドン・キホーテ』第3幕では、これまでのドタバタ劇の結末が描かれます。
それでは、『ドン・キホーテ』第3幕のあらすじやみどころ、登場するヴァリエーションをみていきましょう!!
『ドン・キホーテ』第3幕のあらすじ
街の酒場ではキトリの友人とエスパーダ(闘牛士)とその恋人のメルセデスが踊りを楽しんでいます。
キトリとバジルがそこへ逃げ込んできます。
2人を追いかけてきたロレンツォたちに見つかってしまったキトリは、再びガマーシュとの結婚を強要されてしまいます。
すると、バジルは自殺をはかり周囲を驚かせます。
しかし、実はこれはバジルの作戦で自殺は演技でした。
すっかり腰を抜かしたロレンツォとガマーシュ。
ロレンツォはついに2人の結婚を許すことに!
キトリとバジルの結婚式が行われることになりました!
キトリの友人やエスパーダ、メルセデスも2人の結婚をお祝いし踊りを披露します。
キトリとバジルのパ・ド・ドゥも披露され最後は全員で※コーダを踊り物語は終わりを迎えます。
2人の結婚式を見届けたドン・キホーテとサンチョ・パンサは新たな冒険へと旅立ちます。
※バレエにおけるコーダ(Coda)とは、幕の終わりに大団円を迎える部分をさします。
『ドン・キホーテ』第3幕のみどころ
『ドン・キホーテ』第3幕のみどころは、結婚を許してもらうためにバジルが狂言自殺を試みるシーン。
ドキドキな展開から目が離せません。
また、ロレンツォに結婚を許してもらってからは、2人の結婚式が盛大に祝われます。
最大のみどころはなんといってもキトリとバジルのパ・ド・ドゥ。
うっとりするほど華やかで、高いテクニックも次々と披露されます。
中でもコーダで披露されるキトリのグランフェッテは32回転。
このシーンでは会場が最高に盛り上がります。
ぜひ、注目してみてくださいね!!
『ドン・キホーテ』第3幕のヴァリエーション
『ドン・キホーテ』第3幕ではたくさんの有名なヴァリエーションが登場します!
下記は『ドン・キホーテ』の第3幕に登場するヴァリエーションの一覧です。
・キトリの友人第1のヴァリエーション
・キトリの友人第2のヴァリエーション
・キトリのヴァリエーション
・バジルのヴァリエーション
キトリの扇子を持って踊るヴァリエーションはコンクールでもよく踊られる有名で人気の高いヴァリエーションです。
また、バジルのヴァリエーションも有名で人気が高くコンクールでも定番のヴァリエーションとなっています。
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れないこと・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間には余裕を持つようにしましょう。
まとめ

明るく元気なキトリと男気のあるバジルの華やかでダイナミックな恋模様やドン・キホーテとサンチョ・パンサのコミカルな動きから始終、目を離すことができません。
発表会では第2幕の「夢の場」から第3幕のキトリとバジルの結婚式までを演目として取り入れる場合が多いです。
誰でも楽しめる作品となっていますので、バレエの公演を観るのが初めての方も安心して観ることができるオススメの演目です。
-
7.112025
3大バレエの1つ!『白鳥の湖』の全幕を徹底解説!


3大バレエの1つである『白鳥の湖』は、バレエといえばこの作品を思い浮かべる方も多いでしょう。
今回は『白鳥の湖』のあらすじやみどころなどを徹底解説していきます!
これから『白鳥の湖』を見る方で内容を予習したい方は参考にしてみてくださいね。
『白鳥の湖』について

『白鳥の湖』はピョートル・チャイコフスキーが作曲したバレエ音楽『白鳥の湖』を用いたバレエ作品です。
1877年にモスクワのボリショイ劇場で初演されました。
当初はあまり高い評価を得られませんでしたが、チャイコフスキーの没後に振付家のマリウス・プティパとレフ・イワノフが大幅な改訂版を発表し、1895年にサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で蘇演されました。
以後、世界中で上演され『くるみ割り人形』、『眠れる森の美女』と共に3大バレエと呼ばれています。
登場人物
『白鳥の湖』には数々の魅力的な人物が登場します。
主な登場人物の一覧をご覧ください。
・オデット姫(白鳥)
・ジークフリート王子
・ロットバルト
・オディール(黒鳥/ロットバルトの娘)
・侍女たち(白鳥たち)
・王妃(王子の母)
・その他(村人・王子の友人・各国の花嫁候補)
『白鳥の湖』全4幕

『白鳥の湖』は全4幕と長いですが、白鳥と黒鳥を1人2役で演じ分けていることや白鳥たちのコールドバレエなどみどころの多い作品です。
また、結末はバレエ団や振付師により異なることがあり、最後まで目が離せません。
下記に1幕ずつあらすじやみどころを紹介していきます。
『白鳥の湖』をご覧になる際は参考にしてみてください。
『白鳥の湖』第1幕
『白鳥の湖』第1幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
とある国のお城の庭園で成人を迎えたジークフリート王子の前祝いが行われています。
お祝いの特別な場には村人たちも招待され賑やかな雰囲気です。
また、王子の友人たちもお祝いに駆けつけ踊りを披露します(※パドトロワ)。
そこに王妃が姿を見せ王子に、明日の舞踏会で花嫁を見つけるよう命じます。
独り身の最後を告げられた王子は浮かない気分になってしまいます。
しかし、大空に羽ばたく白鳥の群れを目にし、湖畔へ狩りに行くためお城を出発します。
- 《みどころ》
王子の誕生日前日の前祝いの場なので、村人たちや王子の友人などが集い和気あいあいとした賑やかなお祝いムードです。
しかし、王妃の登場によって雰囲気が一転してしまいます。
- 《ヴァリエーション》
・パドトロワ第1ヴァリエーション
・パドトロワ第2ヴァリエーション
・パドトロワ男性のヴァリエーション
※パドトロワはフランス語で3人(女性2人、男性1人)で踊るという意味です。
※王子の友人たちが踊るパドトロワとして有名なヴァリエーションです。(王子の誕生日を祝うために呼ばれた踊り手という設定の場合もあります。)
『白鳥の湖』第2幕
『白鳥の湖』第2幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
月に照らされた湖畔で一羽の美しい白鳥を見つける。
その白鳥はやがて美しい娘に姿を変えます。
王子に気づいた娘は怯えますが、「私はオデット(姫)です。悪魔の呪いによって昼間は白鳥に変えられており、夜の間だけ人間に戻れるのです」という身の上話をする。
続けて、「魔法を解くことができるのは、永遠の愛だけ」と語ります。
可憐なオデットに心惹かれ永遠の愛を誓う王子。
心許しあう2人でしたが、夜明けとともにオデットは白鳥に戻っていってしまいます。
- 《みどころ》
初めてオデットとジークフリート王子が出会います。
初めは怯えていたオデットが心を開いていく心情が繊細に描かれています。
また、白鳥たちの一糸乱れぬコールドバレエ(群舞)にも注目が集まります。
- 《ヴァリエーション》
・白鳥のヴァリエーション
・ジークフリートのヴァリエーション
・四羽の白鳥と二羽の白鳥(1人で踊るヴァリエーションではありませんが、有名な踊りなので、見落とし厳禁です)
『白鳥の湖』第3幕
『白鳥の湖』第3幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
- 《あらすじ》
お城の広間で花嫁候補たちが次々に華やかな踊りを披露します。
しかし、王子の気持ちはオデットへ募るばかりです。
そこに新たな来客を告げるファンファーレが鳴り一同の注目を集めます。
現れたのは騎士に扮したロットバルトとその娘のオディール(黒鳥)でした。
美しく妖艶なオディールをオデットと思い込んでしまった王子は永遠の愛を誓ってしまいます。
その瞬間、悪魔のロットバルトとオディールは本性を現し、高笑いとともに立ち去ります。
驚愕した王子はお城を飛び出し、オデットのいる湖畔へ向かいます。
- 《みどころ》
お城の広間では華やかな舞踏会が行われ、各国の花嫁候補が上品で華やかな踊りを披露します。
そして、3幕の楽しみはなんといってもオディール(黒鳥)の登場です。
高度なヴァリエーションと特に32回転のグラン・フェッテは一番盛り上がる場面といっても過言ではありません!
- 《ヴァリエーション》
・オディールのヴァリエーション
『白鳥の湖』第4幕
『白鳥の湖』第4幕のあらすじやみどころ、踊られるヴァリエーションを紹介します。
《あらすじ》
王子の裏切りに悲しみに打ちひしがれるオデット。
絶望のあまりオデットは湖畔に身を投げようとします。
同じように白鳥に変えられているオデットのお付きの者たちは必死にオデットを止めようとします。
そこへ王子がやってきてオデットへの変わらぬ愛を伝えますが、2人は湖に飛び込み命を落としてしまいます。
死をも恐れない2人の愛は悪魔に打ち勝ち物語は終わりを迎えます。
- 《みどころ》
白鳥の湖の結末はバレエ団によって異なる場合があります。
今回紹介したのは悲劇的な結末です。
中にはハッピーエンドで終わることもあります。
《ヴァリエーション》
『白鳥の湖』第4幕で踊られるヴァリエーションはありません。
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性 ジャケット、シャツ
女性 ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま (女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
- 持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもありますのでブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
- A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れない・外に出られないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もありますので、時間に余裕を持つようにしましょう。
まとめ

『白鳥の湖』はみどころがたくさんありますし、バレエ団や振付家によってストーリー展開が異なる点も最後まで見逃せません。
またコールドバレエ(群舞)のレベルは、そのバレエ団の実力を表しているといっても過言ではないほど重要です。
主人公だけでなく、白鳥たちにも注目してみてくださいね。
-
7.112025
3大バレエの1つ!『眠れる森の美女』の全幕を徹底解説!


3大バレエの1つである『眠れる森の美女』は日本でもよく公演が行われており、人気の作品です。
発表会やコンクールでも『眠れる森の美女』のヴァリエーションは踊られることが多く定番となっています。
今回はそんな『眠れる森の美女』のあらすじやみどころ、ヴァリエーションなどを徹底解説していきます!!
公演を観に行く予定の方や、『眠れる森の美女』の演目が気になっている方は参考にしてみてくださいね。
『眠れる森の美女』について

『眠れる森の美女』にはチャイコフスキーが作曲したバレエ音楽が使用されています。
原作はシャルル・ペローによる昔話『眠れる森の美女』で、1890年にマリウス・プティパの振り付けによってサンクトペテルブルク、マリインスキー劇場にて初演されました。
現在もクラシックバレエを代表する作品として世界中で上演されています。
登場人物
『眠れる森の美女』には数々の魅力的な人物が登場します。主な登場人物の一覧をご覧ください。
・オーロラ姫
・デジレ王子
・王(オーロラ姫の父)
・王妃(オーロラ姫の母)
・邪悪の精カラボス
・リラの精(善の精)
・純粋さ(優しさ)、活力(元気)、寛容さ、美声(美しい歌声)、「情熱(勇気)」の精
・4人の王子(花婿候補)
・金の精、銀の精、ダイヤモンドの精、サファイアの精
・ブルーバード(青い鳥)とフロリナ王女
・長靴をはいた猫と白猫
・赤ずきんと狼
『眠れる森の美女』エピローグ+全3幕

美しく華やかなオーロラ姫と、それぞれのカラーが輝く妖精たちや、おとぎの国のキャラクターたちの踊りと魅力が詰まった演目です。
ディズニー作品にもなっているので、内容はバレエ作品と異なる点はありますが、全体の流れを予習しておく上で観ておくと良いかもしれません。
『眠れる森の美女』エピローグ
『眠れる森の美女』エピローグのあらすじや、みどころ、踊られるヴァリエーションについて紹介します。
- 《あらすじ》
とある国の王と女王に待望の姫が誕生しオーロラと名付けられました。
オーロラの洗礼式には「純粋さ(優しさ)」「活力(元気)」「寛容さ」「美声(美しい歌声)」「情熱(勇気)」の精が招待され贈り物を捧げます。
最後にリラの精が贈り物を授けようとした、その時に洗礼式に招待されなかったことに怒る悪の精、カラボスが現れ「オーロラは16歳の誕生日に糸紡ぎの針に指を刺して死ぬ」という呪いをかけてしまします。
悲しみにくれる王と女王にリラの精は「呪いを解くことはできませんが、オーロラは死ぬのではなく100年の眠りにつくだけです。100年の眠りから覚める頃、王子のキスによって目覚めるでしょう」と慰めます。
- 《みどころ》
お祝いに駆けつけた「純粋さ(優しさ)」「活力(元気)」「寛容さ」「美声(美しい歌声)」「情熱(勇気)」の精たちの踊りはそれぞれの個性が光ります。
また、オーロラ姫誕生のお祝いムードから一転、、カラボスの出現で悲しみムードに・・。
《ヴァリエーション》
純粋さ(優しさ)の精/活力(元気)の精/寛容さの精美声(美しい歌声)の精/情熱(勇気)の精
『『眠れる森の美女』第1幕
『眠れる森の美女』第1幕のあらすじや、みどころ、踊られるヴァリエーションについて紹介します。
- 《あらすじ》
オーロラは美しく成長し16歳の誕生日を迎えます。
結婚を申し込むために招き入れられた4人の王子と楽しそうに踊るオーロラ。
最後の1人と踊り終えたその時、突然老婆が現れ花束を差し出します。
それを受け取ったオーロラは花束の中に隠されていた糸紡ぎの針に指を刺して倒れてしまいます。
老婆の招待はカラボスだったのです!
悲しみにくれる一同にリラの精は、「オーロラは眠っているだけ」とお城全体に眠りの魔法をかけて眠らせます。
「オーロラが眠りから覚めるとき、一同も眠りから覚めるでしょう」と魔法をかけました。
- 《みどころ》
オーロラ姫が4人の花婿候補の王子たち1人1人と優雅に踊ります。
また、カラボスの再出現によりお祝いムードが一変してしまいます・・。
物語の続きが気になる展開ですね。
- 《ヴァリエーション》
オーロラ姫のローズアダージオ(コンクールでもよく踊られます)
『眠れる森の美女』第2幕
『眠れる森の美女』第2幕のあらすじや、みどころについて紹介します。
- 《あらすじ》
100年後、美しいデジレ王子とお付きのものが狩りをしに森にやってきました。
しかし、デジレ王子は狩りに乗り気ではありません。
物思いにふけっていたデジレ王子にリラの精はオーロラ姫の幻想を見せます。
一目でオーロラ姫の美しさに心奪われたデジレ王子はリラの精の導きにより、オーロラ姫のいるお城に向かいます。
そして、勇敢にカラボスを倒すとオーロラにキスをしました。
するとオーロラは長い眠りから目覚めることができました。
- 《みどころ》
デジレ王子の勇敢な姿は必見!カラボスとの戦いには息を呑むでしょう。
『眠れる森の美女』第3幕
『眠れる森の美女』第3幕のあらすじや、みどころ、踊られるヴァリエーションについて紹介します。
- 《あらすじ》
オーロラ姫とデジレ王子の結婚式が行われます。
お祝いには様々な宝石の精、青い鳥(ブルーバード)とフロリナ王女、長靴を履いた猫と白い猫、赤ずきんと狼といったおとぎの国のキャラクターたちが駆けつけ踊りを披露します。
ラストを飾るのはオーロラとデジレ王子のパ・ド・ドゥです。
そして、一同に見守られながら賑やかで華やかなコーダ(幕終わりの大団円のこと)で物語は締めくくられます。
- 《みどころ》
結婚式をお祝いするために駆けつけたキャラクターたちと、幸せいっぱいで華やかなオーロラ姫とデジレ王子のパ・ド・ドゥ。
- 《ヴァリエーション》
宝石のヴァリエーション(金の精、銀の精、ダイヤモンドの精、サファイアの精)
フロリナ王女のヴァリエーション/ブルーバードのヴァリエーション(男性の踊り)
赤ずきんと狼のヴァリエーション/長靴をはいた猫と白い猫のヴァリエーション
オーロラ姫のヴァリエーション/デジレ王子のヴァリエーション
バレエ公演について

日本ではバレエの公演に行くことはまだあまり馴染みがないかもしれません。
そのため、敷居が高いと感じてしまうことも多いようです。
しかし、実際は案外気軽に行けるものです。
バレエ公演の基本について紹介しますので、「バレエ公演に行ってみようかな」という方は参考にしてみてください。
バレエ公演のチケット
バレエの公演に行くには、まずチケットが必要です。
チケットの価格はオーケストラ付きの生演奏と、そうでない場合か日本のバレエ団か海外のバレエ団か、全幕公演か※ガラ公演かによって価格は変わります。
※ガラ公演とは
各作品から抜粋されたパ・ド・ドゥや小作品を集めた公演のことです。
- チケットの価格
チケットの価格は大体が3.000円から20,000円くらいの場合が多いです。
- チケット(座席)の種類
座席は指定になっておりS席、A席、B席、C席のように分かれています。
会場にもよりますが、S席、A席は1階、B席、C席は2階や3階ということが多いです。
1階席は舞台が近く、ダンサーや衣装、舞台の背景など間近で舞台の細かいところまで観ることができます。
2階や3階席も舞台が遠くなってしまいますが、上から見えるので舞台の全体を観ることができるので意外とオススメです。
バレエ公演を観に行く時の服装
実は日本国内のバレエ公演ではドレスコードは決まっていません。
そのため、スーツやドレスなど普段よりドレスアップする必要はありません。
バレエ鑑賞は非日常を味わえる機会なので、せっかくなら少しおしゃれをして行くことをオススメします。
- オススメの服装
男性:ジャケット、シャツ
女性:ワンピース、スカート(パンツスタイルでもOK)
お子さま:(女の子)ワンピースやスカート(男の子)襟付きのシャツ、ポロシャツ等
※マストではありませんが綺麗めな服装がオススメです。
持っていると便利なもの
・オペラグラス
ダンサーの表情や衣装等といった細かい部分も見ることができます。
・ブランケット
会場内は空調が効いている場合が多く、夏には冷房が強く感じることもあります。ブランケットがあると肌寒く感じる時にも安心です。
・A4サイズが入るバッグ
プログラムを購入したり、他の舞台のチラシをいただいたりするので、それらを入れられるA4サイズのバッグがオススメです。
これらのものは必須ではありませんが、持っていると便利なものですので参考にしてみてくださいね。
バレエ公演の鑑賞中マナー
バレエ鑑賞はマナーに厳しいイメージもあるかもしれません。
しかし、基本的に意識したいのは「他の観客の邪魔をしないこと」です。
具体的には下記のことに気をつけます。
・上演中に客席を出入りしない
・上演中にしゃべらない
・物音を立てないようにする
・スマートフォンなどの電子機器の操作(上演中は電源をオフにするのが安心です)
・客席での飲食
・身を乗り出して見ること(後ろの人が見えにくくなってしまうため)
バレエの公演は一度始まってしまうと休憩まで中に入れない・外に出れないこともあります。
遅刻してしまった時は休憩までロビーで待たなければならない場合もあるので時間には余裕をもちましょう。
最近では子どもが観やすいよう配慮された公演も多いので、そういった場合は出入りが可能な場合もあります。
まとめ

プロローグ付きの全3幕と長く感じますが、色とりどりの衣装や個性豊かなキャラクターが多く登場するので飽きることが少ない作品です。
発表会やコンクールなどで踊られるヴァリエーションが多く登場するのでキャラクターが登場する背景などを理解しておくと、表現力が増しそう。
まだ、『眠れる森の美女』の全幕では観たことがないという方はぜひ、観てみてくださいね!
-
7.112025
発表会の必需品!!衣装バッグはどんなものが最適?衣装バッグを徹底解説


発表会やコンクールなどではバレエの衣装は必須ですが、実は衣装を入れるための衣装バッグも必須アイテムです。
初めて衣装をもらった場合、どのような衣装バッグが最適なのか迷うこともありますよね。
今回は衣装バッグとは何か、どのようなものが最適かなどおすすめも含めて紹介します。
衣装バッグをお探しの方は参考にしてみてくださいね!!
バレエ舞台の必需品!衣装バッグとは

バレエの衣装は飾りが細かくついていたり繊細なつくりになっているものが多いですよね。
そんな衣装を持ち運ぶ時にはどうしたらいいのでしょうか。
まずは衣装バッグについてと、衣装を持ち運ぶ際のポイントについて紹介します!
衣装バッグについて
衣装はバレエの発表会で重要な持ち物の一つですよね。
衣装が手元に来た際にはテンションが上がるという方も多いでしょう。
そんな、衣装は大切に持ち運ぶ必要があります。
そこで必要になるのが衣装が入るサイズの衣装バッグです。
バレエ専門店でも取り扱っていますし、バレエ用品でなくても大きいバッグで代用するという方もいらっしゃいます。
下記に、衣装を持ち運ぶ際のポイントについて紹介しますので、衣装バッグを選ぶ際の参考にしてみてください。
衣装を持ち運ぶ際のポイント
衣装はハンドメイドであることが多く、つくりがとても繊細です。
そのため、持ち運ぶ際にはいくつかの注意点があります。
衣装を持ち運ぶ際のポイントは下記の通りです。
衣装(チュチュ)をたたむ
衣装を衣装バックに入れる際は綺麗にたたむ必要があります。
クラシック・チュチュのたたみ方には3段階あり、具体的なたたみ方は下記の通りです。
- ボディ部分のホックをはずし、内側から裏返しになるようにショーツ部分を持ちあげます。
- 飾りなどが引っかからないようていねいに、ボディ部分を裏返しにしスカート部分にかぶせます。
- スカート部分がボディ部分の中に収まったらホックを留めていきます。
この方法はコンパクトにたたむことができますが、そのまま長時間放っておくとシワになったりスカートが下がってきてしまいます。
お家や会場に着いたらすぐに広げるようにしましょう。
ロマンティック・チュチュの場合も同じたたみ方で二つ折りにたたむことができます。
クラシック・チュチュと同様に家や会場に着いたらすぐに広げるようにしてくださいね。
衣装の形を崩さないようにする
バレエの衣装は形が崩れやすく繊細です。
そのため、形をなるべく崩さないように持ち運ぶ必要があります。
小さい衣装バッグに無理やり衣装を詰め込むと衣装がしわくちゃになったり、形が崩れてしまう原因になります。
衣装バッグは衣装の大きさに対して余裕があるものを選びましょう。
汚れや雨から守る
衣装は基本的に洗濯ができないので、汚れや雨などから守る必要があります。
衣装の一部が外に出ていたり、飲食物と一緒に入れるなどは避けた方が良いでしょう。
そのため、衣装専用の衣装バッグの方が安心ですね。
やってはいけないこと
上記以外で注意するべき点は衣装バッグに衣装を入れっぱなしにしないことです。
衣装を着た後に衣装バッグに入れっぱなしにしてしまうとカビが生えたり、黄ばみの原因となってしまいます。
衣装を着た後はすぐに風通しの良い場所で陰干しし、チュチュについた汗をよく乾かしましょう。
デザイン豊富!衣装バッグの種類について

実は様々な形やデザインがある衣装バッグ。
それぞれの特徴やおすすめのものを紹介します。
衣装の個数やサイズによって衣装バッグを選んでみてくださいね。
不織布衣装バッグ
不織布衣装バッグは不織布素材なので軽いのが特徴です。
またリーズナブルなものが多く、柄の展開も豊富なので好みのデザインがみつかります。
注意すべき点は、不織布が水に弱いこと。
そのため、雨や汚れから衣装を守るためにはやや弱いのが難点です。
お教室によっては不織布がNGな場合もありますので、先生に確認してみましょう。
ドラム型衣装バッグ
衣装(チュチュ)をふんわりと収納できるのがドラム型衣装バッグの特徴です。
ナイロン素材のものが多く雨や汚れにも強く、使用しない時にはたためるのも便利。
衣装は1〜2着収納可能です。
巾着型衣装バッグ
巾着型衣装バッグは衣装が2〜3着入るのでとにかく大容量!
使用しない時は小さくたたむことも可能です。
持ち手がないので両手が他の荷物でふさがっていても、斜めがけにして衣装を持ち運べます。
ショップバッグ
衣装バッグを市販のショップバッグにしている方もいます。
例えばIKEAやディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンといったテーマパークのショッピングバッグが大きくておすすめ。
最近では100円均一や無印良品でも大きいバッグが手に入ります。
バレエ用のものは大きいものが多いので、子ども用の衣装1着ほどでしたら市販のものでも良いでしょう。
ファスナーがついているものはバッグの口を閉じられるので汚れや雨から衣装を守れるのですが、衣装のチュール部分が巻き込まれることがあるので注意が必要です。
お教室によってはファスナー付きバッグを禁止しているところもあるようなので、先生に確認してみましょう。
衣装バッグはどこで買う?衣装バッグ手に入るバレエショップリスト

衣装を扱っている多くのバレエショップは衣装バッグも取り扱っていることが多いです。
最近ではバレエのオンラインショップも増え実店舗に行かなくても購入が可能です。
下記に実店舗のあるバレエショップとバレエのオンラインショップを紹介します。
バレエショップ実店舗
バレエタイツをバレエショップの実店舗で購入する利点は実際に試着できたり、バレエを熟知したスタッフの方にその場で質問や相談をできること。
特に初めての場合は何を買っていいかわからない場合も多いので、実店舗でのお買い物がおすすめです。
また、バレエタイツ以外のものも揃っているので、トータルコーディネートもでき、バレエに必要なものが全て揃うのも魅力です。
チャコット
バレエ用品といえばチャコットという方も多いほど有名なバレエショップ。
1961年に創業した国内随一の老舗バレエメーカーです。
バレエ用品だけでなくジャズダンス・エクササイズ用品、ボールルームダンス用品、コスメ用品を取り扱っています。また、ダンススタジオを全国10か所に展開し、衣裳レンタルと製作などの事業もあります。
初心者の方からプロのダンサーまで幅広くファンの多いブランドです。
実店舗
全国に31店舗(東京・大阪・福岡・名古屋・札幌など)
※店舗によって取り扱い商品が異なります。
オンラインショップURL:https://shop.chacott.co.jp/
シルビア
1967年に創業したバレエシューズブランドのシルビア。
1978年より自社ブランドのトゥシューズやバレエシューズを製造し、国内のバレエショップの中でも老舗で愛用者も多いです。
バレエシューズの他にはバレエウェアやバレエグッズの販売もあり、ホームページからはレオタードをオーダーメイドすることもできます
実店舗
名古屋、横浜、新宿、梅田、福岡、札幌、仙台の全国7店舗を展開
オンラインショップURL:https://www.shop.sylvia.co.jp/
ミルバ
ミルバ最大の特徴は海外メーカーの取り扱いが豊富なことです。
海外のトゥシューズの取り扱いも多いので今までしっくりくるトゥシューズが見つからなったという方も様々なメーカーをフィッティングできるので自分にあったものが見つかるかもしれません。
スタッフの方にも気軽に相談できますよ。
実店舗
新宿、横浜、大阪、札幌
オンラインショップURL:https://dance.milba.com/
バレエショップオンライン
バレエのオンラインショップでの購入は何といってもどこにいても買い物ができること。
また、実店舗で紹介したお店よりも値段設定が安価な場合もあります。
最近ではオンラインでもスタッフの方とメールやチャットなどでやりとりができることもあるので、商品に対する質問や相談も可能です。
ミニヨン
2003年創業のバレエショップ。
スタッフにはバレエ経験者や元バレエ団員の方が常駐しバレエの専門的な視点から商品の仕入れや開発を行なっています。
また海外バイヤーも所属しているのでトレンド感のあるバレエ用品が多く入荷されています。
オンラインショップURL:https://www.mignon-ballet.com
イーバレリーナ
メーカーや工場から直接仕入れを行なっている、イーバレリーナ。
そのためバレエ用品をお手頃価格で購入できます。
バレエ用品についての悩み事はメールで相談することができ、万が一サイズが合わなかった場合でも無料でサイズ交換をしてくれるなどのサポートも。
試しやすい価格と充実のサポートでオンラインショップで購入が初めてという方にもオススメです!
オンラインショップURL:https://www.mignon-ballet.com
まとめ

衣装を守るために衣装バッグは必須アイテムです。
衣装はかさばるので、衣装をすっぽり収納するためには大きめのバッグが必要となります。
衣装を急にもらった場合は持ち運びに困ってしまいますので、早めに用意する方が良いでしょう。
衣装を大切に運んで、本番を迎えてくださいね!!
-
7.112025
自分にぴったりのチュチュを探そう!バレエの衣装チュチュについて徹底解説!!


トゥシューズでヴァリエーションを踊ることを目標にしている方も多いでしょう。
ヴァリエーションを踊る際に欠かせないのがバレエの衣装であるチュチュです。
チュチュはバレエの演目や役柄を表す重要なアイテムです。
自分好みのチュチュを着ることもやる気アップに繋がりますね。
今回はチュチュの種類や、どんな役柄がチュチュを着るのかなどを紹介していきます。
ヴァリエーション選びや、チュチュ選びの参考にしてみてくださいね!
バレエの衣装といえばチュチュ!チュチュについて知ろう!

バレエの厳しい練習もチュチュを着ると忘れてしまうくらいチュチュには不思議な力があるような気がしますね。
演目や役柄を表現するチュチュには様々な種類があります。
そんなチュチュの歴史や種類について解説していきます。
チュチュの歴史
チュチュ(フランス語: tutu)は、主に古典バレエにおいて着用されるスカート状の舞台衣装です。
チュチュの起源は19世紀半ばのフランスにさかのぼります。
当時のバレエ衣装は長く、重く、精巧でダンサーが自由に動くのが困難なものでした。
ロマン派時代の有名なバレリーナ・マリータリオーニは自由な動きと柔軟性を高める短いスカートが特徴の新しいバレエ衣装を開拓したことで知られています。
マリータリオーニが考えた衣装はふくらはぎ丈のスカートでリボンやフリルがあしらわれ、何よりダンサーたちが踊りやすいデザインでした。
このスタイルがのちにクラシックチュチュとして知られることになりました。
チュチュのつくり
チュチュは下記の3つのパーツで作られています。
・ボディス(胴体部分のパーツ)
・バスク(ウェスト部分のボディスとスカーチをつなぐ箇所)
・スカート(バスクから大きく広がり、チュチュ全体の形を作り出す)
この3つのパーツがチュチュを構成しているのですね。
チュチュの種類
前述の通りチュチュはダンサーが踊りやすいように改良され現代の形となりました。
初めはクラシックチュチュのみでしたが、後に様々な種類のチュチュが誕生します。
ここではチュチュの種類や、主な着用演目などを紹介します。
クラシック・チュチュ
クラシック・チュチュはハリのある硬めのチュール生地で作られています。
スカート部分が水平に広がり、丈が短いのが特徴です。
足の動きが見えやすく、例えば『白鳥の湖』では白鳥と黒鳥が着用しテクニックを披露します。
主な着用演目
『白鳥の湖』(オデット(白鳥)・オディール(黒鳥))/『眠れる森の美女』(オーロラ姫・フロリナ王女・妖精の踊り等)
『パキータ』(エトワール・その他ヴァリエーション)/『くるみ割り人形』(金平糖の精)
ロマンティック・チュチュ
ロマンティック・チュチュはベル型のバレエチュチュです。
生地はチュールで作られており、くるぶしのあたりまである長い裾丈が特徴です。
ふわふわと柔らかい衣装なので妖精といった軽さを強調したい役に着用されます。
主な着用演目
『ラ・シルフィード』(シルフィード(妖精))/『ジゼル』(ジゼル・ミルタ(森の精霊の女王)・ウィリーたち(森の精霊たち))
オペラ・チュチュ
ロマンティック・チュチュとクラシック・チュチュの中間くらいの丈の長さが特徴的です。
『くるみ割り人形』のキャンディボンボンの踊りで着用されることが多いです。
主な着用演目
『くるみ割り人形』(キャンディ・ボンボン)/『シンデレラ』(シンデレラ)
ジョーゼット
ジョーゼット素材で作られ、薄手で軽いという特徴があります。
裾丈が長いチュニックやワンピース型の衣装です。
透け感があって体のラインがわかるようなデザインです。
大人っぽいイメージがありますが、『ドン・キホーテ』のキューピットの衣装もジョーゼットです。
着用演目
『ロミオとジュリエット』(ジュリエット) /『くるみ割り人形』(クララ)
『ドン・キホーテ』(キューピット)/『海賊』(メドーラ)
チュチュはどこで手に入れる?チュチュの入手方法

舞台で着用するチュチュは、バレエスタジオの先生が用意してくださることが多いです。
しかし、中には自分で用意することになったり、用意したいという方もいるでしょう。
そんな方のために、チュチュの入手方法について紹介します!
チュチュをレンタル
一般的に多いのがチュチュをレンタルすることです。
レンタルの場合はチュチュだけでなく頭飾りが一緒に付いていたりとトータルコーディネートされていることが多いので大変、便利です。
また、チュチュを購入するよりもレンタルの方が費用を抑えられるという利点も。
一度しか踊らない役柄のチュチュといった場合はレンタルの方がいいかもしれませんね。
下記はチュチュのレンタルを行なっているお店です。
チュチュを購入
チュチュを購入する場合、レンタルよりは費用が高くなりますが、その分オーダーメイドなので自分にサイズがぴったり合ったものを手に入れることができます。
また、オーダーメイドには1から自分でデザイン画から作るフルオーダーと既存の衣装に飾りなどをカスタマイズしていくセミオーダーがあります。
オーダーメイドがいいけれど費用を抑えたい場合は、セミオーダーをオススメします。
一度きりではなく、コンクールなどで何回も着る際は購入した方が良い場合もありますね。
下記はチュチュを購入できるお店です。
本番まで大切に保管必須!チュチュのお手入れ方法

チュチュにはスパンコールやラインストーンなどの装飾が付いていたり、スカート部分はチュール素材だったり繊細なつくりになっています。
そのため、お手入れや保管方法に少し気を使う必要があります。
チュチュのたたみ方やお手入れ方法について紹介します。
チュチュのたたみ方
今回はクラシック・チュチュのたたみ方について紹介します。
チュチュのたたみ方には3段階あり、具体的なたたみ方は下記の通りです。
- ボディ部分のホックをはずします。内側から裏返しになるようにショーツ部分を持ちあげます。
- 飾りなどが引っかからないようていねいに、ボディ部分を裏返しにしスカート部分にかぶせます。
- スカート部分がボディ部分の中に収まったらホックを留めていきます。
この方法はコンパクトにたたむことができますが、そのまま長時間放っておくとシワになったりスカートが下がってきてしまいます。
お家や会場に着いたらすぐに広げるようにしましょう。
ロマンティック・チュチュの場合も同じたたみ方で二つ折りにたたむことができます。
クラシック・チュチュと同様に家や会場に着いたらすぐに広げるようにしてくださいね。
チュチュのお手入れ方法<
チュチュを着た後に袋に入れっぱなしにしてしまうとカビが生えたり、黄ばみの原因となってしまいます。
チュチュを着た後はすぐに風通しの良い場所で陰干しし、チュチュについた汗をよく乾かしましょう。
チュチュはお家で洗濯することができないので、濡らしたタオルで汗を拭き取る程度にしておきましょう。
消臭スプレーもシミの原因となる可能性があるのでオススメできません。
また、クリーニングに出す場合も注意が必要です。
普通のクリーニングはチュチュにはスパンコールやラインストーンがたくさんついているので、そういった装飾が取れてしまったり、チュールにハリがなくなってしまう場合も。
クリーニングに出す場合は、衣装を取り扱っている専門店に確認してからにしましょう。
まとめ

バレエの踊りに欠かせないチュチュ。
自分に合ったものを着ることで踊りも格段に輝きます。
本番当日にチュチュの状態を良くしておくのも重要です。
チュチュの作りは繊細なので適切なお手入れ方法や保管方法で管理しましょう。
チュチュを着るために練習を頑張っている方も多いと思うので、ぜひ素敵なチュチュを身に舞台で輝いてくださいね!!
-
7.112025
バレエキッズはなにを履けばいいの?キッズにおすすめのバレエタイツ


バレエではレオタードと同じくらいレッスンの必須アイテムであるバレエタイツ。
バレエタイツはレッスン以外の舞台本番でも履くので着用する回数が多いアイテムです。
バレエを始めた頃は「なぜバレエタイツを履くのか」や「扱い方がわからない」といった方も多いでしょう。
今回はキッズのバレエタイツについて、おすすめのサイズやカラー、取り扱い方法について詳しく解説します。
キッズ向けのバレエタイツをお探しの方は参考にしてみてくださいね!!
なぜ履くの?バレエタイツについて知ろう

そもそもバレエでタイツを履くのはなぜでしょうか?
また、普通のタイツでは代用できないのかといったことも疑問に思う方も多いですよね。
まずは、バレエでタイツを履く理由や普通のタイツとの違いについて解説します。
バレエでタイツを履く理由
バレエのレッスンでバレエタイツを履くことによって、筋肉の使い方や脚のラインをはっきりと確認することができます。
先生にも見えやすく、アドバイスがしやすいんですね。
自分自身でも確認できるのでバレエタイツを履くことが上達への第一歩とも言えます。
また、バレエの舞台本番でもバレエタイツを履きますが、舞台では照明で全身が照らされた時に脚を綺麗に見せる必要があります。
そのため、ぴったりとしたピンクのバレエタイツを履いて脚を綺麗に見せるんですね。
普通のタイツとバレエタイツの違い
バレエタイツと普通のタイツの大きな違いは、伸縮性や耐久性、シルエットなどです。
バレエ用のタイツは、バレエの動きに合わせて作られているため、下記のような特徴があります。
・伸縮性があり伝線しにくい
・多少穴があいても破けて広がりにくい
・つま先部分が消耗しやすいので強くできている
・洗濯して毛玉ができにくい丈夫なつくりになっている
・脚の形がわかりやすい
普通のタイツと比べてバレエタイツはバレエの動きに対応できたり、脚が綺麗に見えるよう工夫されているんですね!!
キッズのバレエタイツ選び方について

キッズのバレエタイツのサイズやカラーはどのようなものを履けば良いのでしょうか?
キッズにおすすめのバレエタイツのサイズやカラーをチェックしていきましょう!!
バレエタイツのキッズサイズ
キッズの対象年齢は一般的に6歳から8歳といわれています。
6歳から8歳の平均身長とサイズは下記の通りです。
6歳平均身長・・・117cm サイズ目安110・120
7歳平均身長・・・122.9cm サイズ目安120・130
8歳平均身長・・・128.5cm サイズ目安130
※平均身長やサイズは個人差がありますので、参考にご覧ください。
バレエタイツのタイプ
実はバレエタイツには「フーター」と呼ばれるものと「穴あき」と呼ばれるものの2つのタイプがあります。
2つの違いについて解説します。
「フータータイプ」のバレエタイツ
「フーター」タイプはスタンダードなバレエタイツで 通常のタイツと同じように、つま先まですっぽりと隠れるデザイン。
バレエを始めたばかりの方やどれを買おうか迷っている方は、まずはフータータイプのバレエタイツの購入がおすすめです。
「穴あき」タイプのバレエタイツ
「穴あき」タイプは足の裏部分に穴があいているタイプです。
穴があいている理由は、トウシューズをはく際に、足の手入れがしやすくするため。
小さなお子さんはトウシューズを履く機会がまだないので「穴あき」タイプを着用するのはまだ少し先になりそうですね。
バレエタイツのカラー
バレエタイツのカラーは意外と多くあります。
カラーの種類は主にホワイト、ハニーベージュ、キャメル、ロイヤルピンク、ヨーロピアンピンクです。
バレエのレッスンや舞台で着用される定番カラーはロイヤルピンクとヨーロピアンピンクとなっています。
教室によってはカラーやブランドに指定があることがあるので、先生に確認してみましょう!
バレエショップ別!キッズ用バレエタイツのおすすめ

バレエタイツの種類は意外と多くどれがいいか分からない・・。という方も多いですよね。
そこでキッズにおすすめのバレエタイツをバレエショップ別に紹介します。
実店舗でもオンラインでも購入が可能なので参考にしてみてくださいね!!
チャコット
バレエショップの老舗であるチャコットのバレエタイツは、かかと部分が立体設計になっており足首にぴったり沿って浮きがでないなど履き心地にもこだわってつくられています。
そのため、キッズにも履きやすいバレエタイツといえますね。
【チャコット 公式(chacott)】ジュニア ベロネーゼタイツIII(フーター
シルビア
シルビアのバレエタイツは1デニールより細い極細の糸をよりあわせたナイロン糸を使用し、生地が柔らかく脚にしなやかにフィットします。
また、一番小さいサイズがChild SS(90cm以下)なので小さめのお子さんにもぴったりのサイズがみつかります。
ミニヨン
ミニヨンはバレエ用品のオンラインショップです。
ミニヨンのバレエタイツはリーズナブルでありながら丈夫で長持ちするのが特徴です。
バレエタイツは消耗品ですが2ヶ月の保証がついており、2ヶ月以内であれば穴が空いたといった商品劣化の際に新しいのものと交換してくれるので安心です。
正しく扱って美しく履こう!バレエタイツの扱い方

自分でできることが増えるキッズ世代。
バレエレッスンや舞台では自分で着替えるシーンも増えますね。
バレエのタイツは意外と履くのに時間がかかってしまうこともあります。
正しく美しくバレエタイツを履くために履き方と脱ぎ方のコツ、バレエタイツの取り扱い方法についてチェックしていきましょう!
バレエタイツの履き方と脱ぎ方<
バレエタイツの履き方と脱ぎ方のコツを紹介します。
自分自身で着替えるシーンが増えるキッズ世代の方も参考にしてみてくださいね!
バレエタイツの履き方
- タイツをはき口から足先までたぐり寄せて持ちます
- 左右それぞれ、足先から足首、ふくらはぎからひざ、最後に太ももまで引き上げます
- タイツの股下マチ部分と自分の股下をぴったり合わせて、ヒップからウエストまで引き上げます
- ウエストを合わせたら、つっぱるところがないか、均等に伸ばしてきれいにはけているかを調整しましょう
バレエタイツの脱ぎ方
タイツを脱ぐ際に足先を引っ張るとタイツが伸びてしまうことがあります。
タイツのウエスト部分を持って下げるようにしましょう。
両手で脱ぐことでタイツの長さに左右差ができにくくなりますよ。
バレエタイツのお手入れ方法
バレエタイツは普通に洗濯できるか気になるという方も多いでしょう。
バレエタイツのお手入れ方法は下記の通りです。
- 1足ずつ洗濯ネットに入れます
- 洗濯をします
- ウェスト部分と足先部分を合わせて2つ折にたたみます
- 3の状態でウェスト部分とつま先部分を軽く引っ張り形を整えます
- ウエストのゴム部分を上にして陰干しをしましょう
洗濯後にタイツを整えて干すことで、長さや形が整った仕上がりになりますよ!
長く綺麗に履くために洗濯をする際に注意してみましょう。
まとめ

意外と種類の多いバレエタイツ。
初めてタイツを購入するときは、お店で実際に試着するのが良いかもしれません。
お店の場合は専門のスタッフがいるので安心です。
バレエのレッスン着に着替える際に時間がかかってしまうことが多いバレエタイツ・・。
キッズの方は一人で履けるようお家でも練習してみてもいいかもしれませんね。
-
7.112025
寒さ対策&着痩せ効果にバッチリ!おしゃれなバレエトップスをみつけよう!!


肌寒い季節になると、いつものレッスン着に加えてバレエトップスを羽織る方も増えますよね。
バレエトップスの中には二の腕やウエストといった気になる部分のカバーに役立つものも多いです。
そんなバレエのレッスンに適したバレエトップスは一枚あると便利なアイテム。
今回はバレエトップスはレッスンで着用OKなのかや、おすすめのバレエトップスを目的別に紹介します。
購入を考えている方は参考にしてみてくださいね!!
バレエレッスンでトップスは着てもOK!?

バレエのレッスンでトップスを着こなしている方がいる反面、自分が着ることになると本当に着てもいいのか?どのように着るのが正解なのかわからないという方も多いかもしれません。
まずは、基本のバレエレッスン着についてと、レッスンでバレエトップスはOKなのかについて紹介します!
基本のバレエレッスン着について
バレエレッスン着の基本はタイツにレオタードです。
これは体のラインがわかる服装の方が、足や手の向きや位置、筋肉の使い方などがわかりやすいからです。
先生にとっても体のラインが見えやすいとアドバイスしやすく、自分でも鏡で見た際に正しい位置がわかりやすいです。
そのため、体のラインがわかりやすいレッスン着を着ることはバレエ上達の早道とも言えますね。
レッスンでバレエトップスはOKなのか
上記では体のラインが見えるレッスン着がバレエ上達の早道であると紹介しました。
しかし、タイツとレオタードのみでのレッスンにはなかなか抵抗があるという方も多いでしょう。
通っている教室にもよりますが、大人のレッスンの場合はタイツとレオタードに加えてバレエトップスや巻きスカート・ショートパンツといったものがOKな場合も多いです。
基本的には体のラインが見えるものを選べば、バレエトップスを着ても大丈夫。
バレエトップスの中には暖かさがあり防寒対策になるものや、二の腕などをカバーできるもの、それに加えておしゃれなものまで種類がたくさんあるので、自分にぴったりのものを探してお気に入りをみつけてみてくださいね!
防寒or着痩せするのはどれ?目的別おすすめバレエトップス

バレエのレッスン着の一つである、バレエトップスには様々なデザインや素材の異なる種類があります。
防寒対策や着痩せ、最近では重ね着をすることでおしゃれにも着こなせるものも多いです。
そんなバレエトップスの種類について目的別に紹介していきます。
一般のものとバレエトップスとの違い
バレエトップスと一般のトップスとの違いは、「動きやすい」、「体のラインが綺麗に見える」ようなデザインであることが多いことです。
加えて、暖かい素材や体型カバーにも役立ちます。
寒さ対策におすすめのバレエトップス
寒い季節になるとレッスンで体が温まるまで寒さを感じることもありますね。
また、リハーサルや舞台の待ち時間に体が冷えてしまうことも。
そういった場合にもバレエトップスは一枚あると便利なアイテムです。
寒さ対策に役立つおすすめのバレエトップスは下記の通りです。
カシュクール
カシュクール(cache-coeur)とは、フランス語で「胸を隠す」「胸を覆う」という意味で、胸元が着物のように打ち合わせになった衣服を指します。
バレエトップスの場合は、胸元が結び目になっているものが多く、丈が短めでウェストが見えるデザインとなっています。
体に沿ったサイズ感なので寒さ対策と共に、体のラインを見せつつも二の腕カバーもできます。
素材もニットや綿やナイロンなど様々です。
アームカバー
トップスやレオタードの上から重ね着しやすいのがアームカバーです。
カシュクールやTシャツよりもタイトで軽い印象ですっきりと着られます。
鎖骨部分が見えるのでデコルテを美しく見せ、首も長く見えるという特徴も!
前があいているので、舞台などでメイクをした後にもさっと羽織れるのも便利な一着です。
着痩せにおすすめのバレエトップス
バレエトップスはバレエ用に作られているので、普通のトップスよりも体のラインを美しく見せてくれるものが多いです。
二の腕や上半身をカバーしてくれるバレエトップスを紹介します。
Tシャツタイプ
Tシャツはダボっとした印象になりがちですがバレエ用のものだと二の腕やウェストをカバーしつつスタイルアップできるデザインも多いです。
また、レオタードや巻きスカートといった他のレッスン着との合わせやすさも◎
体のラインは見せつつもカバーできる安心感のあるTシャツコーディネートがおすすめです。
ロングスリーブデザイン
気になる部分は隠すよりも、あえて見せる方がレッスン中の意識が高まる場合もあります。
ロングスリーブは長袖のぴったりしたトップスです。
肌見せには抵抗がある方も、ロングスリーブなら気になる部分を隠しつつ、体のラインを確認できます。
また濃いカラーを選ぶことで引き締まった印象に。
おすすめのロングスリーブはこちらです。
その他
バレエトップスではありませんが、七分袖のレオタードは着痩せアイテムです。
七分袖は視覚効果で腕が長く見えるのでスタイルアップできます。
レオタードに挑戦してみたいという方におすすめのデザインです。
バレエトップスはどこで手に入れる!?おすすめのバレエショップリスト

バレエトップスは一般のトップスとは異なる点があるので、バレエグッズの専門店での購入がおすすめです。
下記に実店舗のあるバレエショップとオンラインショップを紹介していきます。
バレエショップ実店舗
バレエタイツをバレエショップの実店舗で購入する利点は実際に試着できたり、バレエを熟知したスタッフの方にその場で質問や相談をできること。
特に初めての場合は何を買っていいかわからない場合も多いので、実店舗でのお買い物がおすすめです。
また、バレエタイツ以外のものも揃っているので、トータルコーディネートもでき、バレエに必要なものが全て揃うのも魅力です。
チャコット
バレエ用品といえばチャコットという方も多いほど有名なバレエショップ。
1961年に創業した国内随一の老舗バレエメーカーです。
バレエ用品だけでなくジャズダンス・エクササイズ用品、ボールルームダンス用品、コスメ用品を取り扱っています。
また、ダンススタジオを全国10か所に展開し、衣裳レンタルと製作などの事業もあります。
初心者の方からプロのダンサーまで幅広くファンの多いブランドです。
実店舗
全国に31店舗(東京・大阪・福岡・名古屋・札幌など)
※店舗によって取り扱い商品が異なります。
オンラインショップURL:https://shop.chacott.co.jp/
シルビア
1967年に創業したバレエシューズブランドのシルビア。
1978年より自社ブランドのトゥシューズやバレエシューズを製造し、国内のバレエショップの中でも老舗で愛用者も多いです。
バレエシューズの他にはバレエウェアやバレエグッズの販売もあり、ホームページからはレオタードをオーダーメイドすることもできます
実店舗
名古屋、横浜、新宿、梅田、福岡、札幌、仙台の全国7店舗を展開
オンラインショップURL:https://www.shop.sylvia.co.jp/
ミルバ
ミルバ最大の特徴は海外メーカーの取り扱いが豊富なことです。
海外のトゥシューズの取り扱いも多いので、「今までしっくりくるトゥシューズが見つからなった」という方も様々なメーカーをフィッティングできるので自分にあったものが見つかるかもしれません。
スタッフの方にも気軽に相談できますよ。
実店舗
新宿、横浜、大阪、札幌
オンラインショップURL:https://dance.milba.com/
バレエショップオンライン
バレエのオンラインショップでの購入は何といってもどこにいても買い物ができること。
また、実店舗で紹介したお店よりも値段設定が安価な場合もあります。
最近ではオンラインでもスタッフの方とメールやチャットなどでやりとりができることもあるので、商品に対する質問や相談も可能です。
ミニヨン
2003年創業のバレエショップ。
スタッフにはバレエ経験者や元バレエ団員の方々が多く常駐し、バレエの専門的な視点から商品の仕入れや開発を行なっています。
また海外バイヤーも所属しているのでトレンド感のあるバレエ用品が多く入荷されています。
オンラインショップURL:https://www.mignon-ballet.com
イーバレリーナ
メーカーや工場から直接仕入れを行なっている、イーバレリーナ。
そのためバレエ用品をお手頃価格で購入できます。
バレエ用品についての悩み事はメールで相談することができ、万が一サイズが合わなかった場合でも無料でサイズ交換をしてくれるなどのサポートも。
試しやすい価格と充実のサポートでオンラインショップで購入が初めてという方にもオススメです!
オンラインショップURL:https://www.mignon-ballet.com
まとめ

寒さ対策や着痩せ効果など実用的なバレエトップス。
デザインも豊富なのでいつものレッスン着に加えるだけで、おしゃれな印象にもなりますね。
レッスンだけでなくリハーサルや舞台の待ち時間など一枚持っておくと便利なので、ぜひ自分にあったバレエトップスを見つけてみてくださいね!!
-
7.92025
【バレエ衣装】レンタルの流れって?レンタルとオーダーはどっちがいいの?


バレエの発表会で衣装をレンタルすることはよくあります。
バレエの衣装はとても高価なものですから、借りるときはとても緊張しますよね。
特に初めてのレンタルはわからないことだらけです。
そこで今回は、バレエ衣装レンタルの流れや、注意点についてご紹介します。初めての衣装レンタル!衣装の扱い方

バレエの衣装は高価なもの。
レンタルをするときは不安なことも多いですよね。
ここでは、初めて衣装をレンタルする方でも安心して衣装を扱えるように、衣装の扱い方についてお話しします。用意しておくもの
・衣装バッグ
お教室から衣装を借りて家まで持って帰る際や、発表会当日やリハーサル時の持ち運びに使用する衣装バッグを用意しましょう。
衣装バッグは、バレエ用品店で簡単に手に入れることができますし、大きめの手提げバッグなどでも良いでしょう。
大切な衣装を汚さない・傷つけないために、衣装は必ず袋に入れて持ち運びましょう。
・ハンガー
衣装を持ち帰り、衣装バッグに入れたまま保管していると衣装が型崩れしたりしわになってしまったりします。
自宅に持ち帰ったら、すぐにハンガーにかけて保管できるように、あらかじめ用意しておきましょう。
ハンガーは普通のハンガーでも良いのですが、長時間ハンガーにつるすと肩紐が伸びてしまうことがあるので、パンツやスカート用のピンチタイプのハンガーを用意することをおすすめします。
・アクセサリー用のケース
衣装と一緒にティアラなどの髪飾りも借りることがあります。
そういう場合は、髪飾りを入れるためのケースも用意しましょう。
100円ショップなどで売っているプラスチックのCDケースをアクセサリーケースとして使用している人が多いみたいですよ!自宅での保管方法
衣装を自宅に持ち帰ったら、ハンガーにかけて暗所で保管しましょう。
ただ、クラシックチュチュはハンガーでかけると重みでチュチュが下がってきてしまいます。
できれば床などの平らな場所で保管すると良いでしょう。
小さな子どもがいる家庭では、子どもの手の届かないところで保管しましょう。
また、ペットや食べ物などのにおい移りにも気をつけて保管してください。保護者がやること
衣装を受け取ったら、まずサイズを調節しましょう。
体にぴったりフィットさせて着るために、「ムシ」と呼ばれるホックをひっかける部分をつけて調節します。
バレエの衣装にはホックがついているのですが、そのホックを受けるループのことを「ムシ」と呼びます。
ホックを体にフィットする位置で止めるために、ムシを作る必要があります。
ムシの作り方については、こちらの動画が参考になりますよ♪
また、発表会では他の子のお母さんに衣装を着せてもらったり、他の子と一緒に荷物を置いたりするため、衣装に名札をつけましょう。
借りている衣装なので、衣装に直接名前を書いたり、アイロンなどで接着するのはもちろんいけません。
縫い付け用のゼッケン布などに名前を書き、衣装の内側に縫い付けましょう。
衣装を着せてくれる人に見えやすいように、ムシやホックの近くなどに縫うと良いでしょう。レンタルとオーダー、どっちがいい?

コンクールに出るようになると、衣装をオーダーする人も増えますよね。
ではレンタルとオーダーはどちらがいいのでしょうか?レンタルのメリット
レンタルの最大のメリットは、オーダーに比べて安価な値段で衣装を着ることができる点です。
オーダーの場合、少なくとも数万円はかかりますが、レンタルだと1回数千円から借りることができます。
高くても2万円弱ほどで衣装を借りられるため、頻繁に衣装を着ない人はレンタルのほうがお得かもしれません。
また、種類もたくさんあるため、発表会やコンクールの演目に合わせていろんな衣装を着ることができます。
成長が早い子どもの場合は、その時の体に合わせてサイズを選べるのもいいですね。レンタルのデメリット
レンタルのデメリットは、衣装の扱いにとても気を遣うことです。
自分のものではないため、汚れや破損などに自分の持ち物よりもさらに気を遣わなければなりません。
また、レンタルの場合は自分の体にぴったり合う衣装があるとは限りません。
ムシなどでサイズ調節をする人が多くいると思います。
自分の体にぴったりフィットする衣装を着たい!という場合はオーダーのほうがいいかもしれません。オーダーのメリット
オーダーのメリットは、自分にぴったりの衣装を着ることができる点です。
コンクールにたくさん出る場合、毎回レンタルしてサイズ調節をするのはなかなか大変ですよね。
オーダーの場合は採寸をしてぴったりフィットする衣装を作ってもらえるので、サイズ調節をする必要がありません。
また、デコレーションや衣装の色など、演目に合わせつつも自分好みの衣装にできるため、こだわりが強い人はオーダーがいいかもしれません♪オーダーのデメリット
オーダーのデメリットは費用が高い点です。
安くても数万円、相場は10~十数万円ほどと言われています。
演目に合わせた衣装が必要になるため、毎回オーダーしているとその分費用がかさみます。
また、子どもの場合は成長によってサイズアウトしやすいので、衣装を着られる期間が短くなってしまうこともあります。レンタルとオーダー、どちらを選ぶ?
コンクールには出ず、発表会のみの場合や、頻繁にコンクールに出ない場合などは、レンタル衣装でも良いでしょう。
逆に、コンクールにたくさん出場していたり、コンクールの演目を決めていて同じ衣装を長く着る予定の場合などはオーダーでぴったりの衣装を手に入れるのもいいかもしれません。
どちらも一長一短なので、それぞれのメリットとデメリットを吟味したり、お教室の先生や周りの保護者に相談したりして決めてみてください^^衣装レンタルの注意点

衣装を借りるときは、衣装の破損や紛失など気を付けることがたくさんあります。
ここでは衣装レンタルの注意点についてお話しします。着る前に衣装の状態を確認しておこう
衣装を受け取ったら、着る前に衣装の状態を確認しましょう。
衣装を着た後に汚れや破損があった場合、それが自分が破損してしまったものなのかどうかを確認するためです。
もしももとから汚れや破損があった場合には、写真に撮っておくと安心です。
また、もとから破損があった場合は、一度お教室の先生に伝えておくとさらに安心ですね。丁寧に取り扱おう
当たり前ですが、借り物なので丁寧に扱わなければなりません。
保護者が丁寧に扱うだけでなく、衣装を着る子ども本人にも大切な衣装であることを教えましょう。
小さい子は借り物だなどとはわからないため、衣装を着ているときにしてはいけないことなどを決めると良いでしょう。
お教室ごとに衣装の約束事が決まっていることもありますが、ご家庭でも約束事を決めておくことも大切です。
例えば、「衣装を着ているときはご飯やお菓子を食べない」「衣装を一人で着たり脱いだりしない」「衣装を着たまま床に座らない」など、衣装を汚したり破損しないための約束事を作っておくといいかもしれません。試着をしてサイズを合わせよう
衣装を受け取ったらなるべく早くサイズ調節をしましょう。
レンタルの場合、ぴったりのサイズで着られることはそう多くありません。
発表会やコンクール前はなにかと忙しいので、余裕のある時にあらかじめサイズを合わせておくと安心です。
また、万が一サイズが合わなかった場合、着用日までに交換できる場合もあるので、早めに準備しましょう。レンタル期間や返却方法を確認しておこう
レンタルの場合、返却期限が定められていることがほとんどです。
返却が遅れると先生に迷惑がかかったり、場合によっては延滞料がかかることもあります。
また、どのように返却するかも確認しておきましょう。
教室によっては、発表会後に衣装を返却する日を設けているところもあるようです。
教室からのアナウンスを確認して、遅れずに返却できるようにしましょう。万が一の対応を確認しておこう
万が一、衣装を汚してしまったり破損してしまったりした場合の対応を確認しておきましょう。
本番前に衣装を破損してしまった場合、一度返却してお直しをしてくれる場合もあります。
また、破損や汚れの場合、追加で修繕費やクリーニング代がかかることもあるので、事前にお教室の先生などに確認しておくと安心です。まとめ

いかがでしたか?
今回はレンタル衣装についてお話ししました。
みなさんの不安や疑問が少しでも解消されていればうれしいです♪
すてきな衣装を身にまとって、舞台上でとびきり輝けますように☆ -
7.92025
バレエといえばシニヨン!!ネットからきれいなシニヨンの作り方まで解説!!


バレエを習っていると髪型をシニヨン(お団子)にする機会が多いですよね。
きれいなシニヨンはスッキリ見えて、踊りの見た目にも反映します。
お子さんが小さい場合は保護者の方がシニヨンを作ってあげることが多くなりますね。
今回はきれいなシニヨンの作り方や、シニヨン作りの必需品であるネットについてなどを紹介します!!
バレエのヘアスタイルといえばシニヨン!シニヨンについて知ろう!!

バレエの発表会本番のヘアスタイルはシニヨンなのでリハーサルでも「シニヨンで来てください」と言われることもあります。
バレエを習っているとすることの多いシニヨンスタイルですが、慣れていないときれいに作るのに苦戦する方も多いです。
シニヨンについて、シニヨン作りに必要なもの、作り方を解説していきます。
これからお子さんにシニヨン作りをしてあげる方は参考にしてみてください!
なぜシニヨンスタイルにするのか
シニヨンはフランス語で「 Chignon」で束ねた髪をサイドや後頭部でまとめた髪型のことをさします。
お団子と呼ばれることもありますが、お団子とシニヨンは同じ意味です。
バレエをする際に「なぜシニヨンスタイルにするのか」をまずは解説していきます。
その理由は下記の2つです。
バレエに集中するため
バレエの動きは回ったりジャンプしたりよく動くので、髪がまとまっていないと集中して踊ることができません。
髪の毛に気を取られ集中できないと怪我をしてしまう可能性もあり、汗で髪が顔や首筋に絡みつくことも気持ち悪いですね。
髪を下ろした状態やポニーテールだと無意識に髪を触ってしまう方もいます。
レッスン中や舞台の上では集中力が必要なので、踊ることに専念できるようシニヨンスタイルに整えることが重要なんです。
実はスタイルアップ効果も!
シニヨンスタイルは頭を小さく見せ、首筋を長くきれいに見せる効果があるんです!!
踊りが上手な方はシニヨンもきれいで、よく似合っていることが多いです。
シニヨンに必要なもの
きれいなシニヨンを作るためには、いくつかのアイテムが必要です。
実際にシニヨンを作る際に必要なものを紹介します!
必要なものリストは下記の通りです。
・霧吹き(水)orヘアミスト・ブラシ・20cmぐらいのヘアゴム
・シニヨンネット・Uピン・アメピン
・くし・ヘアジェル・ヘアスプレー・ヘアワックス
シニヨンを作る時のおすすめアイテム
上記で紹介したものはバレエショップで揃っていることも多いですが、全てバレエショップで購入すると割高になってしまうものもあります。
何をどこで購入するのか、おすすめを紹介しますので参考にしてみてくださいね!
シニヨンネット
シニヨンを作る際の必須アイテムであるシニヨンネットはバレエショップで購入がおすすめです。
バレエショップのものはバレエ用なのでシニヨンが美しく見えるよう作られています。
バレエショップにいけない場合はオンラインショップでも購入することができます。
どれを購入していいかわからない場合はシニヨン作りにおすすめのネットをいくつか紹介しますので参考にしてみてください。
※シニヨンの大きさ(髪の量)や髪色など自身に合ったものを選びましょう。
・シニヨンネット<ブラック>Mサイズ3枚組
発表会などに適した目立ちにくい細い糸タイプのシニヨン型ネットです。
サイズはMとLがあり、Mは肩〜セミロングの長さ、Lはセミロング〜ロングの長さがサイズ選びの目安となっています。
・ストレッチヘアーネット(3枚組)【ブラック】
ポニーテールの全体を包み込んで、簡単にお団子の出来上がります。
ネットをかぶせる前の下地のネットです。
髪の毛が細く、猫っ毛のお子様などはこちらのネットを一度使用してからシニヨンを作ると作りやすいです。
発表会などに適した目立ちにくいタイプで、二重にすることで単体でも使用できます。
ロングヘアーの方など、髪とネットを一緒にねじってシニヨンを作りたい方におすすめです。
ヘアジェル・スプレー・ワックス
シニヨン作りに、こんなにヘアスタイリング剤が必要なの!?と驚きますよね。
ヘアスタイリング剤はバレエショップのものでなくても大丈夫。
それぞれ、シニヨン作りにおすすめのものを紹介します。
・ヘアジェル
・ヘアスプレー
・ヘアワックス
ヘアブラシ・くし
シニヨン作りの際に、ヘアブラシとくしは両方必要です。
どのようなものでも使用できますが、髪の艶出しやとかした際に痛くないなどのものを選ぶと良いでしょう。
また、バレエを習っているとシニヨンにする頻度が高いので、丈夫な長く使用できるものがおすすめです。
・ヘアブラシ
・くし
Uピン・アメピン
Uピンとアメピンはシニヨンを留める際に必ず必要となります。
どちらも薬局や100円均一などで購入できるもので大丈夫です。
シニヨン作りにたくさん使うので多めに持っておくと良いでしょう。
きれいなシニヨンの作り方
きれいなシニヨンは頭の形をきれいに見せてくれます。
シニヨンを作る際にはコツが必要となりますので、下記にきれいなシニヨンの作り方を解説していきます!!
- ブラッシング
ブラシで、毛先の絡みがなくなるようによくブラッシングします。
また、生え際からよくブラッシングすることで髪にツヤが出ます。 - 髪の毛全体をまとめる
髪の毛をまとめやすくするために、霧吹きやヘアミストをスプレーします。
※毛先にはつけず、頭の部分にたっぷりとつけていきます。 - 髪の毛を整える
コームを使って一度髪の毛を整えておきます。 - ゴムで仮留めする
次のステップのためにゴムで仮留めをします。
3~4回ゴムを巻き付けて、最後は2回同じところを通して結びます。 - ジェルをつける
ピンポン玉くらいの量のヘアージェルをつけます。
※表面だけではなく、内側の毛にも手ぐしでしっかりつけると、シニヨンが長持ちします。 - コーミング
仮留めしたゴムを外し、コームで表面を整えます。
コーミングしている反対側の毛が緩むので、少し手を引きながら整えましょう。
ある程度まとまってきたらコームでに持ち替え、根元をぎゅっと絞ります。 - ゴムで結ぶ
3~4回ヘアゴムを巻き付け、最後は2回同じところを通して結びます。
※あごと耳の上を通った延長線上にゴムの結び目がくるように結ぶとシニヨンがきれいに見えます。 - 後れ毛をまとめる
もみあげや後れ毛、フェイスラインの細かい毛をワックスでなでつけます。 - ヘアーネットをかぶせる
ポニーテールをヘアネットで包み、結び目に巻きつけるように巻いてシニヨンの形を作ります。
※さらに、ヘアネットを使用するとまとめやすく、毛先がネットからはみ出しにくくなります。 - Uピンで固定する
シニヨン部分をしっかりつぶしながら、上下左右をUピンですくい留めしていきます。
※Uピンを立ててシニヨンの端に当て、地の髪をすくうように倒しながら中心部に向けてうちます。
中心のゴムの結び目に当たる感覚がある場所にうちましょう。 - Uピンで間を固定
Uピンで留めた部分の間をですくい留めしていきます。
※巻いた毛の流れに逆らう向きにピン先が向くように留めます - スプレーをかけて完成!!
スプレーをかけ、最後にもう一度コームのテールでなでつけ、ツヤを出して完成です!
長さやボリュームが難しい!シニヨンのお悩みを解決

お子さまの髪の長さや量によってシニヨンが作りにくい場合も多いですよね。
シニヨン作りの際にありがちなお悩みを解決していきます。
上手くシニヨンが作れない場合は参考にしてみてくださいね!!
シニヨンが作れる髪の長さ
子どものヘアカットしたいけれど、バレエでシニヨンにするのでどのくらいカットしていいかわからないという方も多いでしょう。
シニヨンを作るのに最低限必要な長さは、ボブより少し長めで肩につく程度のロングボブ、胸元にかかる程度のミディアム・セミロングの長さです。
それより短いとシニヨンにするのが難しくなります。
また、髪の毛が長すぎると、シニヨンが大きくなりますのでシニヨンを潰すのが大変かもしれません。
ミディアム・セミロングがシニヨンを作りやすい長さといえるでしょう。
前髪が短い時の対処方法
バレエの舞台で前髪を下すことはほとんどありません。
前髪は全てオールバックにしますが、短い場合はやりにくい、できない時がありますよね。
そんな時は、下記のことを試してみましょう。
コームにジェルをつける
コームでオールバックになるよう流れをつけます。
その後に、コームにジェルをたっぷりと付けて前髪を生え際から頭皮に密着するようにときましょう。
生え際にもしっかりジェルが付くようにコームするのがポイントです。
ピンで前髪を留める
ジェルで固めた後に髪の毛が崩れるのが心配な場合は、前髪が落ちてこないようにヘアピンで固定しましょう。
髪色と同じ色のヘアピンを使用すると目立ちにくいです。
シニヨン用のネットがすぐに破れる
バレエ用のシニヨンネットは、目立ちにくくするためネットの糸が細く繊細です。
そのため、破れやすいのが難点です。
普段のレッスンやリハーサルは強度の高い(本番用より少し目立つ)ネットを使用しても良いでしょう。
バレエ用ではないものだと、薬局や100円均一でも購入することができます。
本番用のシニヨンネットは、当日に破れてしまうこともあるので数個用意しておくと安心です。
下記は練習用の強度の高いシニヨンネットです。
※お教室にもよりますので、先生に確認してみてくださいね。
・ヘアーネットM 【ブラック】
伸縮のある素材のシニヨンネットです。
強度がありレッスン用におすす。
強度がある分、ネットが厚く色が濃いので目立つため本番には適しません。
サイズはMとLがあり、Mは:肩〜セミロングの長さ、Lはセミロング〜ロングの長さが目安となっています。
まとめ

シニヨンは必要なものが多く、作り方の工程も多いですが、バレエを習っているとシニヨンを作る回数も増えるので、だんだんと早く上手くできるようになります。
本番できれいなシニヨンにするためにも、普段のレッスン時から練習しておくのがおすすめ。
練習を重ねると自分なりのやり方も見つかりますので、研究してみてくださいね!
- ブラッシング
-
7.92025
バレエタイツは履く必要がある?ない?バレエレッスンの必需品バレエタイツを徹底解説!!


バレエタイツはバレエの必須アイテムであるイメージがありますが、バレエを始めたばかりの方にとって抵抗がある場合もありますよね。
なぜ膨張色のピンクなのか・・。
いつ履くのがマストなのかもわからないといった方も多いでしょう。
今回はバレエタイツについて、履く理由や色や種類など徹底解説していきます!!
バレエタイツを履いてみたい方や代用品をお探しの方は参考にしてみてくださいね。
バレエの舞台には必須アイテム!!バレエタイツについて知ろう!!

バレエの舞台で必ずといっていいほど見かけるピンクのバレエタイツ。
なぜ、バレエをする際にタイツを履くのか?本番以外のレッスンでも必須なのかについて解説していきます!
バレエタイツを履く理由
クラシックバレエの舞台では必ずバレエタイツを履きます。
バレエダンサーがバレエタイツを履く理由は下記の通りです。
・足のラインや動きがはっきり見える
・美脚に見える
・照明で全身を照らされる舞台で足が綺麗に見える
バレリーナがタイツを履く理由は主に、足を美しく見せる、足の動きをクリアに見せるためなんですね!!
バレエレッスンでバレエタイツは必須なのか
バレエの舞台では必須のバレエタイツですが、練習であるレッスン時には履くのが必須なのでしょうか?
答えは「大人の場合は絶対に履かなければいけない訳ではないが、履いた方が良い」です。
バレエのレッスンではバーレッスン(バーにつかまり行うレッスン)やセンターレッスン(バーから離れてフロアで行うレッスン)を行います。
バレエでは足や手の向きや位置が細かく決まっていますので、レッスン中に確認することが多いです。
その際にバレエタイツを履いていた方が先生も自分自身も足や手の向きや位置を確認しやすいのです。
バレエのタイツはピンク色の膨張色なので足が太く見えるのでは?と気になってしまう方も多いでしょう。
しかし、「足を細くしたい」や「足の形をよくしたい」と思っているならバレエタイツを履いてレッスンした方が、より正確に足の使い方がわかるので脚やせや形の改善、バレエの上達への早道でもあります。
実は奥が深い!?バレエタイツの種類について

バレエのタイツはピンクタイツと呼ばれるほどピンクであることが定着しています。
しかし、一概にピンクといっても実は色んなカラーバリエーションがあるんです。
また、形にも様々な種類があります。
バレエタイツの色や形の種類について解説していきますので、バレエタイツを履いてみたい方は参考にしてみてくださいね。
※発表会など舞台に出られる際は先生から指定があったり、まとめて購入してくださる場合もあります。
一般のタイツとの違い
寒い冬などは普段でもタイツを履くことがありますね。
一般のタイツとバレエタイツとの違いがあるのか気になる方も多いでしょう。
バレエタイツは一般のタイツに比べて伸縮性が高く、動きやすくもあります。
また、足のラインが綺麗に見えるよう作られています。
消耗品ではありますが、一般のものに比べて強度もあります。
バレエタイツの色
実はバレエタイツはカラーバリエーションが豊かです。
バレエ用品の老舗であるチャコットでは下記のような色の展開があります。
・ホワイト・ブラック
・ハニーベージュ・キャメル
・ロイヤルピンク・ヨーロピアンピンク
6色ものカラーバリエーショがあるのも驚きですが、舞台で着用する場合とバレエタイツとして定番なのはロイヤルピンクとヨーロピアンピンクです。
2つとも名前にピンクが入っていますが、ロイヤルピンクはピンク色が濃く、ヨーロピアンピンクはイエローがかったピンクとなっています。
自分の肌色に近い方を選ぶと肌馴染みが良いでしょう。
バレエタイツの形
バレエのタイツにはフーターと呼ばれるもの、穴あきと呼ばれるものの2種類があります。
なぜ、わざわざ穴が空いているのか不思議に思う方も多いですよね。
2つのバレエタイツの形について解説します。
フータータイプ
フータータイプはスタンダードなバレエタイツです。
一般的なタイツと同じようにつま先まですっぽりと隠れるデザインとなっています。
バレエを始めたばかりの方や、どのタイツを購入していいかわからないといった場合には、まずこのフータータイプがおすすめです。
穴あきタイプ
穴あきタイプは足裏の部分に穴があいているデザインのタイツです。
通常のタイツと大きく異なるため、バレエを始めたばかりの方には馴染みがないかもしれませんね。
足裏に穴があいている理由は、トゥシューズを履いての練習は足先にマメや傷ができることがあるので足先のケアをするためです。
足裏に穴があいていることでタイツを全部脱がなくても良いというわけです。
レッスンでバレエタイツを履かない場合は!?バレエタイツの代用品

バレエタイツをレッスンで履いた方がいい理由を解説しましたが、それでもやはりピンク色のタイツを履くのには抵抗があることもありますよね。
バレエのレッスンでタイツを履かない場合の代用品について紹介します。
レギンスを履く
バレエタイツの色はピンクなので、色に抵抗がある方も多いです。
そういった場合は黒のレギンスがおすすめです。
バレエ用のレギンスもありますし、市販のレギンスでも対応可能です。
バレエ用のレギンスの方が足の形が綺麗に見えるよう作られたものが多いのでおすすめです。
太ももやヒップまわりが気になるといった方はレギンスにプラスして巻きスカートやショートパンツを着用すると程よく体型をカバーできますよ。
また、レギンスはバレエ以外のヨガやピラティスといったレッスンでも使えますね
下記はおすすめのレギンスです。
ストレッチパンツを履く
レギンスはタイツの代用品になりますが足のラインがはっきり出ます。
足のラインがはっきりでた方がレッスンには最適なのですが、バレエを始めた頃だと抵抗を感じることもありますよね。
そういった場合には、タイツやレギンスよりはダボっと感はありますがストレッチパンツがおすすめです。
バレエやヨガ、ピラティに使用できるストレッチパンツは伸縮性があって動きやすく、スウェットよりもラインが綺麗に作られているものが多いんです。
下記はバレエのレッスンにおすすめのストレッチパンツです。
バレエタイツが手に入るバレエショップリスト

バレエタイツは一体どこで売っているのでしょうか?
バレエ用なので一般的なタイツのようには売られておらず、バレエ専門ショップで売られています。
最近ではバレエのオンラインショップも増え実店舗に行かなくても購入が可能です。
下記に実店舗のあるバレエショップとバレエのオンラインショップを紹介します。
バレエショップ実店舗
バレエタイツをバレエショップの実店舗で購入する利点は実際に試着できたり、バレエを熟知したスタッフの方にその場で質問や相談をできること。
特に初めての場合は何を買っていいかわからない場合も多いので、実店舗でのお買い物がおすすめです。
また、バレエタイツ以外のものも揃っているので、トータルコーディネートもでき、バレエに必要なものが全て揃うのも魅力です。
チャコット
バレエ用品といえばチャコットという方も多いほど有名なバレエショップ。
1961年に創業した国内随一の老舗バレエメーカーです。
バレエ用品だけでなくジャズダンス・エクササイズ用品、ボールルームダンス用品、コスメ用品を取り扱っています。
また、ダンススタジオを全国10か所に展開し、衣裳レンタルと製作などの事業もあります。初心者の方からプロのダンサーまで幅広くファンの多いブランドです。
実店舗
全国に31店舗(東京・大阪・福岡・名古屋・札幌など)
※店舗によって取り扱い商品が異なります。
オンラインショップURL:https://shop.chacott.co.jp/
シルビア
1967年に創業したバレエシューズブランドのシルビア。
1978年より自社ブランドのトゥシューズやバレエシューズを製造し、国内のバレエショップの中でも老舗で愛用者も多いです。
バレエシューズの他にはバレエウェアやバレエグッズの販売もあり、ホームページからはレオタードをオーダーメイドすることもできます
実店舗
名古屋、横浜、新宿、梅田、福岡、札幌、仙台の全国7店舗を展開
オンラインショップURL:https://www.shop.sylvia.co.jp/
ミルバ
ミルバ最大の特徴は海外メーカーの取り扱いが豊富なことです。
海外のトゥシューズの取り扱いも多いので「今までしっくりくるトゥシューズが見つからなった」という方も様々なメーカーをフィッティングできるので自分にあったものが見つかるかもしれません。スタッフの方にも気軽に相談できますよ。
実店舗
新宿、横浜、大阪、札幌
オンラインショップURL:https://dance.milba.com/
バレエショップオンライン
バレエのオンラインショップでの購入は何といってもどこにいても買い物ができること。
また、実店舗で紹介したお店よりも値段設定が安価なこともあります。
最近ではオンラインでもスタッフの方とメールやチャットなどでやりとりができることもあるので、商品に対する質問や相談も可能です。
ミニヨン
2003年創業のバレエショップ。
スタッフにはバレエ経験者や元バレエ団員の方が常駐しバレエの専門的な視点から商品の仕入れや開発を行なっています。
また海外バイヤーも所属しているのでトレンド感のあるバレエ用品が多く入荷されています。
オンラインショップURL:https://www.mignon-ballet.com
イーバレリーナ
メーカーや工場から直接仕入れを行なっている、イーバレリーナ。
そのためバレエ用品をお手頃価格で購入できます。
バレエ用品についての悩み事はメールで相談することができ、万が一サイズが合わなかった場合でも無料でサイズ交換をしてくれるなどのサポートも。
試しやすい価格と充実のサポートでオンラインショップで購入が初めてという方にもオススメです!
オンラインショップURL:https://www.mignon-ballet.com
まとめ

バレエの教室にもよりますが、大人のバレエレッスンではレッスン着は本人の自由であるところが比較的多いです。
発表会といった舞台で衣装を着る際はバレエタイツは必須なので、舞台に立つことを目標にされている方は慣れておくのも良いでしょう。
レッスン着は気分の上がるものを選ぶのがおすすめ!
お気に入りのスタイルを見つけてバレエを楽しんでくださいね!!
-
7.92025
男性バレエダンサーの必須アイテム!?バレエの男性用タイツを徹底解説!!


男性の方でバレエを習ってみたいけれどタイツを履くのに抵抗があるという方も多いかもしれません。
なぜバレエでは男性がタイツを着用するのかや、男性用バレエタイツを取り扱うバレエショップについて解説します。
これからバレエを始めたい男性の方や、本格的な格好でバレエのレッスンを受けたい方など、参考にしてみてくださいね!!
着用は必須なの?男性用バレエタイツについて

なぜバレエで男性がタイツを履くのか不思議に思っている方も多いでしょう。
まずは男性バレエダンサーがタイツを履く理由を理解しましょう。
また、本番舞台やレッスンでタイツの着用が必須なのかも解説します。
男性バレエダンサーがタイツを履く理由
足にぴったりとフィットし足の形がはっきり見える男性用バレエタイツ。
男性バレエダンサーがタイツを履く理由は、足捌きの美しさ、 トレーニングされた下半身の動きを鮮明に見せるためです。
タイツを履く際に必要なアイテム
タイツの着用の仕方について「どのようになっているのか」を不思議に思う方も多いですよね。
タイツは下半身にぴったりとフィットしているため、下着のラインが見えないように、タイツの下にはサポーターやTバックなどのアンダーウェアを着用しています。
タイツ用のアンダーウェアはバレエショップで取り扱っていることが多いです。
バレエタイツは着用必須!?舞台本番とレッスンでの着用について

男性バレエダンサーといえばタイツ姿が印象的ですが、舞台本番とレッスン中も着用が必須なのでしょうか?
舞台本番とレッスンでのタイツ着用についてチェックしていきましょう!!
バレエの本番舞台
バレエ舞台では男性用の衣装はほとんど短いトップスにタイツを着用します。
また、演目によってはパンツスタイルの衣装もありますが、その場合も下にタイツを着用するのが基本です。
舞台に立つことを目標にしている場合は普段のレッスンからタイツの着用に慣れていると違和感なく舞台に立てるでしょう。
バレエのレッスン
バレエレッスンでタイツの着用は必須ではありません。
しかしながら、足を含めた身体のラインが見えやすいものがおすすめです。
そのため、レッスンからタイツを着用するバレエダンサーも多いです。
レッスンの場合は膝上や丈の短いスパッツを着用する方も。
タイツやスパッツに合わせるトップスはピタッとしたスポーツ用のトップスやバレエ用のTシャツを組み合わせると良いでしょう。
どこで手に入る?男性用バレエタイツを取り扱うバレエショップ

男性用のバレエタイツはどこで手に入るのでしょうか。
男性用のバレエタイツを取り扱う3つの代表的なバレエショップやサイズ・カラー展開などを紹介します!!
チャコット
バレエショップの老舗であるチャコットでは男性用のバレエ用品も豊富に揃っています。
サイズはメンズのSサイズとMサイズがあり、カラーは定番の白と黒があります。
値段は11,550円(税込)と練習用にするには少し高価に感じますが、チャコットの製品は質が良いので長持ちしそうです。
下記はチャコットでおすすめの男性用タイツです。
【チャコット 公式(chacott)】メンズタイツ(フーター・肩ゴム付)
ミニヨン
バレエ専門店のミニヨンはバレエ用品の専門公式通販サイトです。
海外のバレエブランドも取り扱っており、「Sansha(サンシャ)」というブランドのタイツは90cmから10cm刻みで190cmまでサイズ展開があり、カラーは黒で光沢のあり・なしを選べます。
値段も5,060円とバレエ用品にしてはリーズナブルで初めての1着にもおすすめです。
バレエ用品 【サンシャ】 男の子&メンズ用バレエタイツ(発表会に!レッスンに!)
まとめ

初めてタイツを着用するときは抵抗があるという方も多いですが、まずはレッスンで身体にフィットするスパッツといったものから履き始め、タイツにチャレンジしてみるのもいいかもしれません。
バレエの舞台ではタイツの衣装であることがほとんどです。
バレエ舞台でバレエタイツを履きこなせるよう頑張ってみてくださいね!!
-
7.92025
バレエ用品といえばチャコット!チャコットでレオタードを選ぼう!!


バレエ用品店の老舗として有名なチャコット。
お子さまの初めてのレオタードはチャコットで購入したという方も多いです。
そんなチャコットについて、チャコットのレオタードのメリット・デメリット、レオタード以外に取り扱っているものなどを紹介します。
チャコットでレオタードの購入をお考えの方は参考にしてみてくださいね!!
バレエ用品の老舗!チャコットについて知ろう

小さいお子さまからプロのダンサーまで愛用者が多いチャコット。
そもそもチャコットとはどのようなブランドなのでしょうか?
チャコットについて詳しく解説していきます!
チャコットとは
チャコット株式会社は1950年1月に創業者である土屋誠さんが青志社(個人企業)として創業した日本のバレエ・ダンス用品企業です。
チャコットという企業名称は創業者の土屋誠さん(ツチヤマコト)の「マ」を抜いたもの。また、国内の各種バレエ公演で協賛企業としてスポンサー活動も行っており、2012年からは海外の有名なコンクール「ローザンヌ国際バレエコンクール」の協賛企業にもなっています。
チャコットのコンセプト
チャコットは「人生を、芯から美しく」をコンセプトにしています。
バレエやダンス用品の総合メーカーとして、お子さまから一流のアーティストまで幅広い層にサービスや商品を提供することや、芸術分野の強みを活かし、日常生活への価値提供を行うことで、美しくありたいと願うすべての人々をサポートすることを目的としているそう。
お子さまからプロのダンサー、また一般の方(コスメなど)にも愛用者が多い理由がわかりますね!
チャコットのレオタードの何がいいの?メリットとデメリット

「初めての1着」にチャコットのレオタードを選ぶ方は多いです。
その理由が気になりますね。
チャコットのレオタードのメリット・デメリットについて紹介します!!
チャコットレオタードのメリット
チャコットでレオタードを選ぶメリットは下記の通りです!
・バレエ用品の老舗という安心感
・質が高い(日本製で縫製がしっかりしている、生地が強く、毛玉になったり痛むということがほとんどない)
・キッズ・ベビー向けの100cmからサイズがある
・シーズンごとに新作のデザインが出るなどデザインが豊富
やはりバレエ用品の老舗ということで安心して選ぶことができる要素が多いですね。
レオタード以外のバレエ用品もチャコットという方も多いようです。
チャコットレオタードのデメリット
チャコットでレオタードを選ぶデメリットは下記の通りです!
・値段が高価なものが多い
チャコットのレオタードは質が高い分、お値段も高価なものが多いです。
しかし、その分劣化もしにくく長くきれいに着ることができます。
レオタードだけじゃない!チャコットで取り扱っているバレエ用品

チャコットではレオタード以外にもバレエ用品全般が手に入ります。
そのため、バレエ用品に関してあちこち買い回りをする必要がなく大変便利です。
チャコットで手に入るバレエ用品についてチェックしていきましょう!!
バレエシューズ
チャコットではバレエのレッスンに必須アイテムであるバレエシューズも種類も豊富に取り扱っています。
取り扱っているサイズは16m〜28cmまでの取り扱いがあり、素材も前皮(つま先部分が皮になっている)やキャンバス生地、本番用のサテン生地などがあります。
また、足の幅や足裏のソールも好みのものを選ぶことができます。
店舗では知識が豊富なスタッフが試着を手伝ってくれますので、どのバレエシューズがいいかわからない場合は相談してみましょう。
タイツ・アンダーウェア
レオタードと一緒に必要なアイテムといえばタイツとアンダーウェアです。
チャコットのタイツは105cm(95〜115)からあり、カラーもバレエで定番のロイヤルピンクやヨーロピアンピンクが揃っておりレオタードと一緒に購入する方も多いです。
また、バレエ用のアンダーウェアはレオタードを着た際にはみ出したり、目立ったりしないのが特徴。
小さいお子さまの場合は普段のものを使用する方もいますが、バレエ用を揃えておくとバレエの衣装を着る際にも役立ちます。
コスメ
チャコットでは舞台用のコスメが豊富に揃っています。
バレエの舞台の日には教室がコスメを用意してくれることもありますが、コロナウィルスの流行以降はコスメの共有を避けるために自分自身のコスメを用意するよう指定がある場合もあります。
チャコットの舞台用コスメは発色がよく汗をかいても落ちにくいので、教室がチャコットのコスメを使用するよう指定していることも。
舞台用のコスメが豊富に揃っているので、指定のコスメがあってもチャコットに行けば一通り揃うでしょう。
ヘア小物
バレエの定番ヘアスタイルといえばシニヨン(お団子)ですよね。
チャコットではシニヨンにする際に必要なネットやピン類に加えて、ヘアブラシやクシ、ヘアスプレー、ワックスといったシニヨンをより綺麗に作るためのアイテムが揃っています。
特にネットはサイズやカラーなども豊富で小さいお子さまも使用している方が多いです。
まとめ

バレエ用品といえばチャコットという方も多く、今も昔も質の高いバレエ用品を提供しているチャコット。
レオタードはもちろん、その他のバレエ用品も教室で指定があるなど安定のクオリティを保っています。
知識が豊富なスタッフも常駐しているので、バレエ用品でわからないことがあれば気軽に相談してみましょう!
-
7.82025
何を着て踊るの?男性バレエダンサーの衣装を徹底解説!!


初めてバレエの公演を観た方の中には、男性バレエダンサーは舞台でなぜタイツを履くのか?気になった方は多いでしょう。
意外と奥が深い男性バレエダンサーの衣装について紹介していきます!
バレエの公演を観て男性バレエダンサーの衣装が気になっていたという方はチェックしてみてくださいね!!
男性バレエダンサーはどんな衣装を着るの?タイツ着用の理由も解明!

男性のバレエダンサーといえばタイツを履いているイメージが強いですよね。
男性用の舞台衣装はどのようになっているのか、タイツ着用の理由についてチェックしていきましょう!!
男性バレエダンサーの衣装について
女性バレエダンサーの衣装といえばチュチュですが、男性バレエダンサーの場合は短いトップスにタイツが定番の舞台衣装です。
演目や役柄によって舞台衣装は異なり、意外とバリエーションが豊かです。タイツのカラーはトップスとコーディネートされ、トップスに合ったカラーが着用されています。
タイツを着用する理由
男性バレエダンサーといえばタイツですよね。
男性バレエダンサーの衣装にタイツが定着した大きな理由は「動きやすい」ことと「足さばきを美しく魅せられる」ことです。
バレエの生みの親であるルイ14世の時代には、高貴な身分の男性はタイツに短いズボンをはいていました。
また、それ以前のルネッサンス期のイタリアではバレエの王子の衣装のような、短い上着にピタッとしたタイツのようなものをはいていたこともあり、バレエでは短い上着ぎにタイツという舞台衣装のスタイルが定着したとともいわれています。
男性バレエダンサーは何を履いて踊る?

女性バレエダンサーはトゥシューズを履いて踊ることは有名ですが、男性はどうでしょうか?
バレエの舞台で男性バレエダンサーが履いているシューズについて紹介します。
男性バレエダンサーは何を履いて踊るのか
女性のバレエダンサーはトゥシューズを履いて踊りますが、男性バレエダンサーの場合はバレエシューズを履いて踊ります。
基本的に衣装のタイツと同じ色の白や黒といったカラーのバレエシューズで舞台に立つことが多いです。
タイツのカラーによっては舞台用に特別に用意することもあるので、バレエシューズも衣装の中の一つのような役割を果たしています。
男性バレエダンサーがトゥシューズを履いて踊る演目
基本的に男性バレエダンサーは舞台でバレエシューズを履いて踊りますが、中には例外的な演目もあります。
男性バレエダンサーがトゥシューズを履いて踊る演目についてチェックしていきましょう!
『シンデレラ』の義母役
バレエ演目『シンデレラ』では意地悪なシンデレラの義母が登場しますが、男性バレエダンサーがトゥシューズを履いて演じることもあります。
コミカルな演技をして踊るので会場で笑いが起きたり、シンデレラの義母役のシーンを楽しみにしている方も多いです。
『シンデレラ』の見所の一つといっても過言ではないでしょう。
『眠れる森の美女』のカラボス役
『眠れる森の美女』のカラボスはプリンセス オーロラに呪いをかける悪役です。
女性が演じることもありますが、バレエ団や演出によっては男性バレエダンサーが演じることもあります。
カラボス役の方が美人だなと思っていたら男性だったということも、まれにあるようです(笑)
演目・役柄別男性バレエダンサーの衣装の特徴

男性バレエダンサーの衣装は役柄によって異なります。
役柄によってどのような衣装を着用するのか詳しくみていきましょう!!
王子役
バレエの演目で男性バレエダンサーが演じる役で多いのが王子役です。
王子が登場する演目や衣装の特徴について紹介します!
王子が登場する演目
世界三大バレエの『白鳥の湖』、『眠れる森の美女』、『くるみ割り人形』に王子が登場する他、『シンデレラ』にも登場します。
王子役衣装の特徴
王子は貴族であるため、ゴールドの刺繍が入ったものや首元にフリルやリボンがついた豪華なトップスの衣装を着ることが多いです。
また、タイツのカラーも白が定番となっており
※バレエ団や演目によって異なる場合があります。
村人役
王子役の次に多いのが村人役です。
村人が登場する演目や衣装の特徴について紹介します!
村人が登場する演目
村人といっても『ドン・キホーテ』のバジルや『ジゼル』のアルブレヒト(実は貴族)といった主役を演じる村人役もあります。
村人役衣装の特徴
村人役の衣装のトップスはブラウスにベスト、トップスに合ったカラーのタイツであることが多いです。
貴族である王子よりは豪華ではないかもしれませんが、ベストにベロア生地が使用されているなどバレエの舞台らしい上品で華やかです。
『ドン・キホーテ』のバジル役は舞台がスペインなので闘牛士のようなイメージの衣装となっています。
タイツのカラーは茶色や緑といったものが村人役が着用するもので多いです。
海賊役
男性バレエダンサーが多く登場しメインで活躍する演目『海賊』。
海賊が登場する演目や衣装の特徴について紹介します!
海賊が登場する演目
『海賊』はバレエ作品では珍しくオリエンタルな雰囲気をまとっています。
そのため衣装も他の演目とは異なり、短いトップスにタイツ姿とは異なる場合が多いです。
海賊役衣装の特徴
海賊役衣装の最大の特徴はタイツではなく、パンツスタイルであることです。
また、トップスはなしか、素肌にベストといったワイルドな雰囲気であることが多いです。
頭飾りに羽がついているのも海賊役の衣装の特徴です。
まとめ

男性バレエダンサーの衣装といえばタイツというイメージでしたが、多くのバリエーションがあり役柄の特徴を表現していることがわかりますね。
上演するバレエ団や演出によっても個性が出るバレエの舞台衣装。
バレエの舞台を観る際は男性バレエダンサーの衣装にも注目してみてくださいね!!
-
7.82025
バレエの舞台に必須!?男性バレエダンサーについて知ろう!!


今やバレエスタジオはたくさんありますが、やはり男性より女性の方がバレエ人口が多いのが事実です。
そのためバレエを習っていても男の子や男性バレエダンサーが、まわりにいないという方も多いでしょう。
今回は数は少ないですが、バレエの舞台に必須の存在である男性バレエダンサーの気になるレッスンや舞台について紹介します。
女性ダンサーとの違いはある?男性バレエダンサーのレッスンについて

数自体が少ないので謎の多い男性バレエダンサーですが、レッスンにおいて女性との違いはあるのでしょうか?
男性バレエダンサーのレッスン着やレッスン内容について紹介します。
男性バレエダンサーのレッスン着
バレエのレッスンで女性の場合はレオタードにタイツ、バレエシューズが基本ですよね。
男性の場合はどうでしょうか?
男性バレエダンサーのレッスン着について紹介します。
バレエ用のTシャツ
男性の場合は※レオタードは着用しないので、トップスとボトムスが別れているスタイルがほとんどです。
そのため、トップスはバレエ用のTシャツを着ている方が多いようです。
バレエ用のTシャツは普通のTシャツに比べて厚手で、色は白・黒・グレーなどが定番の色になっています。
また、バレエ用ではなくても、身体のラインがわかりやすい野球で着るアンダーシャツをレッスン着にしている方もいます。
※男性がレオタードを着ることはありませんが、レオタードの太もも部分までつながったようなユニタードを着ることはあります。
男性用バレエのタイツ
前述のバレエ用のTシャツにバレエ用タイツを合わせる方が多いです。
男性用のタイツは女性用のものに比べて厚手になっています。
色はTシャツと同様に白・黒・グレーなどがあり、黒いタイツが定番のスタイルとなってます。(海外ではグレーのタイツが指定のバレエ学校などもあります)
また、タイツ以外のボトムスで着用されているのはレギンスです。
長さも、その方の好みにもよりますが膝上や3部丈ほどのものが着用されています。
男性用バレエシューズ
女性の場合はベージュのバレエシューズが定番となっていますが、男性はどうでしょうか?
男性の場合はタイツの色に合わせ、黒いバレエシューズを履く方が多いです。
しかし、女性と同様にベージュで履く方もいます。
履き方もタイツを着用し履く場合と素足で履く場合も。
自身が履き心地が良い、レッスンしやすいものがベターでしょう。
男性バレエダンサーのレッスン内容
舞台上で男性バレエダンサーを見る機会はありますが、なかなかレッスンを見れる機会は少ないですよね。
男性のバレエレッスンは基本的には女性と同じことが多いです。
バレエの基礎は同じなので、バーレッスンをしてセンターレッスンを行います。
異なる点はセンターレッスンで基本的には女性と同じ動きをしますが、ジャンプやターンといった男性特有の動きを取り入れる場合もあります。
普段のレッスンとは別に男性特有の動きに特化したボーイズクラスがあったり、舞台のレッスンではパ・ド・ドゥやヴァリエーションの練習を行うこともあります。
気になる衣装や役柄は!?バレエの舞台でのバレエダンサーについて

女性の場合、バレエの舞台衣装といえばチュチュですよね。
男性の場合はどのような衣装を着るのでしょうか?
また、男性はバレエの舞台においてどんな役柄があるのかについて紹介します。
男性バレエダンサーの衣装
男性のバレエ衣装といえばタイツですよね。
男性がバレエの舞台でタイツを履くのは「動きやすく、足さばきを美しく見せることができる」からというのが大きな理由です。
バレエの生みの親と言われているルイ14の時代には高貴な身分の男性はタイツに短いズボンを履いていました。
また、それ以前のルネッサンス期のイタリアでは男性バレエの衣装のような短い上着にぴったりしたタイツを履いていたので、その名残が男性バレエダンサーが着用する衣装になったといわれています。
男性バレエダンサーの役柄
女性が主役である演目が多く女性メインの役柄が多いバレエですが、バレエの舞台に男性バレエダンサーは欠かせません。
男性バレエダンサーの役柄について紹介します。
役柄①王子様
バレエ演目の主役で多いのがお姫様ですよね。
お姫様には王子様が必須なので、バレエの演目には王子様も多く登場します。
王子様が登場するバレエ演目は下記の通りです。
・『白鳥の湖』ジークフリード王子
・『眠れる森の美女』デジレ王子
・『くるみ割り人形』コクリューシュ王子(金平糖の精と踊ります)
・『シンデレラ』王子
王子様の名前はバレエ団や上演される国によって異なる場合もあります。
そういった演出の違いもバレエ公演を楽しむ楽しみの1つですね。
役柄②村人
王子様の次に多いのは村人の役です。
村人といってもお話の主役であることが多いです。
男性ダンサーが演じる村人は下記の通りです。
・『ドン・キホーテ』バジル
・『ジゼル』ロイス(実は貴族のアルブレヒト)
・『コッペリア』フランツ
・『ラ・シルフィード』ジェームズ
役柄③その他
王子様や村人以外には海賊やおとぎの国のブルーバード、主役の友人役などがあります。
王子様や村人以外のその他の役柄は下記の通りです。
・『海賊』コンラッド(海賊の領主)/ビルバント(コンラッドの友人)/アリ(コンラッドの忠臣)
・『眠れる森の美女』ブルーバード(フロリナ王女と共にパ・ド・ドゥを踊ります)
・『ドン・キホーテ』エスパーダ(闘牛士)
・『白鳥の湖』王子の友人
・『眠れる森の美女』4人の王子候補
有名な男性バレエダンサーはやっぱりあの人!?日本と海外のバレエダンサーを紹介!!

圧倒的に女性の方が多いバレエ人口ですが、有名な男性バレエダンサーも数多くいらっしゃいます!
日本と海外の有名男性バレエダンサーを紹介します!
日本の有名な男性バレエダンサー
日本の有名な男性バレエダンサーをベテランから現在人気があり有名な方まで紹介します。
現役で活躍されている方もいますので、バレエの舞台を観に行く際は注目して観てくださいね!!
※他にも活躍されている男性バレエダンサーは多くいらっしゃいます!
今回は特に人気がある有名な方を紹介しています。
熊川哲也さん
バレエをしていない人でも名前を知っているほど有名なバレエ界のスターといえば熊川哲也さんですよね。
熊川さんは10歳よりバレエを始め、1989年ローザンヌ国際バレエコンクールで日本人初の1位に輝きました。
そして、東洋人として初めて英国ロイヤル・バレエ団に入団を果たすという快挙も。
同バレエ団で1993年からプリンシパルとして活躍し、1998年にバレエ団退団後にKバレエカンパニーを創立しました。
2012年よりBunkamuraオーチャードホール芸術監督も務めています。
山本 雅也さん
バレエ団「K-BALLET TOKYO」でプリシンパルを務めるのが山本雅也さんです。
山本さんは石川県生まれで、4歳よりバレエを始められました。
2010年にオーストラリアン・バレエ・スクールに留学し、2013年にはローザンヌ国際バレエ・コンクール第3位、プロ研修賞を受賞しました。
同年にはロイヤル・バレエの研修生となり、2014年11月にKバレエ カンパニーに入団。
2016年11月にソリスト、2017年に9月ファースト・ソリスト、2018年9月にプリンシパル・ソリスト、2020年1月プリンシパルに昇格を果たしています。
現在も「K-BALLET TOKYO」の数多くの演目で主役を演じ人気がある男性バレエダンサーです。
福岡雄大さん
福岡雄大さんは大阪府出身で「ケイ·バレエスタジオ」で矢上香織さん、久留美さん、恵子さんに師事していました。
2000年NBA全国バレエコンクール·コンテンポラリー部門第1位、03年こうべ全国洋舞コンクール・バレエ男性シニアの部第1位、08年ヴァルナ国際バレエコンクールシニア男性部門第3位、09年ソウル国際舞踊コンクール· クラシック部門シニア男性の部優勝などの輝かしい受賞歴があります。
2003年には文化庁在外研修員としてチューリッヒ·ジュニアバレエ団に入団し、ソリストとして活躍しました。
2009年に新国立劇場バレエ団にソリストとして入団。
『ドン·キホーテ』『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『火の鳥』、バランシン『アポロ』、ビントレー『パゴダの王子』、ウィールドン『不思議の国のアリス』ほか数々の作品で主役を踊り、2012年にプリンシパルに昇格されました。
現在も数々の主役を演じる、日本を代表する男性バレエダンサーです。
海外の有名な男性バレエダンサー
海外の有名な男性バレエダンサーをベテランから現在人気があり有名な方まで紹介します。
海外の方々ですが、来日されることもありますので、ぜひ、注目してみてくださいね!!
※他にも活躍されている男性バレエダンサーは多くいらっしゃいます!
今回は特に人気がある有名な方を紹介しています。
ウラジミール・マラーホフさん
ウクライナ出身のマラーホフさんは4歳でバレエを始め、10歳のときモスクワのボリショイ・バレエ学校に入学しました。
卒業後の1986年にモスクワ・クラシック・バレエ団に入団し、最も若いプリンシパルとなります。
同年にはヴァルナ国際バレエコンクールで金賞、1989年モスクワ国際バレエコンクールで金メダルを受賞しています。
1991年にはロシアを離れ、1992年にウィーン国立歌劇場バレエ団のプリンシパルとなりました。
1994年にはカナダ国立バレエともプリンシパルとして契約し、1995年にはメトロポリタン歌劇場でのアメリカン・バレエ・シアター公演を機に、同バレエ団のプリンシパルに。
2002年、ベルリン国立歌劇場バレエ団の芸術監督に就任。
2004年にはベルリンの3つの歌劇場の統合により新設されたベルリン国立バレエ団の芸術監督に就任しました。
2013-14年シーズンをもって退任し、2014年8月より東京バレエ団のアーティスティックアドバイザーに就任。
振付家としても活躍し、現在も自ら出演することもあるベテランバレエダンサーです。
日本でも踊ることがあるので、観るチャンスがあれば必見のバレエダンサーです!!
ジュリアン・マッケイさん
アメリカのモンタナ州出身で、当時外国人最年少の11歳でボリショイ・バレエ・アカデミーに入学を果たしました。
米国人として初めてフル・ディプロマを取得し卒業。
在学中にはローザンヌ国際バレエコンクールやユース・アメリカ・グランプリ等、5つの国際コンクールで立て続けに入賞しています。
2015年ローザンヌでプロ研修賞を受賞ののち、英国ロイヤル・バレエ団に研修生として入団し、同年ミハイロフロスキー劇場バレエに入団しました。
2020〜2022年にはサンフランシスコ・バレエ団にプリンシパルとして在籍し、2022年9月よりバイエルン国立バレエにてプリンシパルを務めています。
来日することも多く、日本では「K-BALLET TOKYO」の人気作品にゲスト出演することも多いです。
甘いマスクで人気が高く、ファンサービスも親切に対応してくれる親日ダンサーでもあります。
セルゲイ・ポルーニンさん
ポルーニンさんはウクライナ出身のバレエダンサー兼俳優、モデルです。
1989年、ウクライナのヘルソンで生まれ、初めは体操に取り組んでいましたが、8歳でバレエに転向し、キエフ国立バレエ学校で学びました。
2003年に13歳でロイヤル・バレエ学校に入学し、2006年のローザンヌ国際バレエコンクールやユース・アメリカ・グランプリで入賞するなど数々の賞を受賞しています。
2007年にはイギリス人またはイギリスで学ぶ若いダンサーを対象とするヤング・ブリティッシュ・ダンサー・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、2010年に史上最年少の19歳でロイヤル・バレエ団のプリンシパルとなりました。
しかし、2年後にフリーランスとしてのキャリアに注力することを選び、人気絶頂の中でロイヤル・バレエ団を退団しました。
その後は、フリーランスのプリンシパルとして古巣であるロイヤル・バレエ団だけでなく、サドラーズ・ウェルズ劇場、ボリショイ劇場、スタニスラフスキー・ネミロヴィチ=ダンチェンコ劇場、ミラノ・スカラ座、といった数々の有名なバレエ団で活躍しています。
バレエ界の異端児といえばセルゲイ・ポルーニンさんです。
バレエの天才でありながら俳優やモデルなどもこなします。
その生い立ちは映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』でも描かれ注目を浴びました。
男性バレエダンサーの幅広い活躍に勇気をもらえるという人も多そうです。
バレエの公演以外でも映画で姿を観られるのは嬉しいですね。
まとめ

まだまだバレエ人口の中では少ない男性バレエダンサー。
その分、謎も多く「一体どうなっているのだろう」と感じることも多くありますよね。
バレエは女の子の習い事というイメージがありましたが、ジェンダーレスが意識される世の中となったこともありバレエ男子も増えています。
バレエの公演を観る際は男性ダンサーにも注目してみてくださいね!!
-
7.82025
スタイルアップでモチベーションもアップ!?バレエでジュニアにぴったりのレオタードをみつけよう!


バレエでジュニアという時期はトゥシューズを履きだしたり、ヴァリエーションを踊り始めるころですよね。
また、今までのスカート付きのレオタードといった可愛いものから、少し大人っぽいレオタードを着始める子も増えます。
そんなバレエにおけるジュニア時期のレオタードについて、対象年齢やサイズ、おすすめのバレエショップについて紹介します。
ジュニア向けのレオタードをお探しの方は参考にしてみてくださいね!
バレエでジュニアの対象年齢は?サイズはどのくらい?

バレエにおけるジュニアとは何歳なのでしょうか?またジュニアのサイズとはどのくらいか気になる方も多いでしょう。
まずは、バレエにおけるジュニアの対象年齢とサイズについてチェックしていきましょう!
ジュニアとキッズの違い
ジュニアとキッズは、主に年齢層を指す言葉です。
キッズは一般的に幼児から小学生低学年までを指し、ジュニアは小学生高学年から高校生までを指します。
しかし、ブランドや商品により対象年齢が異なる場合も多くあり、実際は正式に定まった年齢はなく大きな枠でくくられています。具体的な対象年齢やサイズについて下記に解説していきますね。
バレエジュニアの対象年齢
一般的にジュニアといえば対象年齢は小学生から高校生(18歳まで)となります。
バレエのジュニアの対象年齢は教室やコンクールによって異なる場合があります。
教室の場合は小学校高学年から中学生までをジュニアクラスにしたり、新国立劇場バレエ研修所では、13〜14歳を対象とした基礎科のジュニアクラスがあるなど様々です。
また、コンクールの場合は10歳くらいから参加する人が多く、ジュニアの部も設けられています。
国際バレエコンクール ジャパングランプリの場合は中学1〜2年生がジュニアBⅠ、中学3年生がジュニアBⅡ、高校生がジュニアAといったようにジュニアの中でも区分分けされています。
バレエジュニアのサイズ
バレエのジュニアサイズは一般的なサイズと同じことが多いです。
一般的に子ども服は大きく2つに分類されます。
子どもの身長(cm)ごとにサイズがあり、50cm〜100cmまでがベビー服、110cm〜160cmがキッズ服とされています。
さらに、キッズ服の中でも140cm〜160cmをジュニア服と呼びます。
サイズと年齢の目安は下記の通りです。
140サイズ:11~12歳、身長135~145cm
150サイズ:13~14歳、身長145~155cm
160サイズ:13~14歳、身長155~165cm
※子どもの発育には個人差があり、平均値がそのまま当てはまる訳ではありません。
あくまでも目安として参考にしてくださいね。ジュニア向けレオタードはどんなものが人気?おすすめのレオタード

ジュニア向けのレオタードはベビーやキッズに比べてグンと大人っぽいデザインのものが増えます。
バレエでジュニアと呼ばれる世代はどのようなレオタードを着ているのでしょうか?
レオタードの種類やカラーについてチェックしましょう。レオタードの種類について
ベビーやキッズには多かったスカート付きのレオタードがない訳ではありませんがデザインは減ります。
そのため、大人と同じようにスカートなしのレオタードが主流となります。
また、半袖や長袖といった袖がある形のレオタードを選ぶ方も増える印象です。
レオタードのカラーについて
ベビーやキッズにはピンクやパープル、淡いブルーといったカラーが人気ですが、ジュニアのレオタードではブラックといったかっこいいカラーのレオタードを着る方もいます。
身体のラインが見えやすいカラーはブラックやホワイトと言われているため、教室によってはレオタードのカラーに決まりがある場合も。
気になる方は先生に確認してみてくださいね!
レオタードの流行りはココでチェック
現在ではジュニア世代の方もSNSを多く利用していますよね。
また、バレエ用品のブランドもSNSを使用し新しいデザインのレオタードを含むレッスン着を紹介している場合も多いです。
インスタグラムやTikTokなどのSNSで「バレエ レッスン着」といったワードを検索してみると、おしゃれなレッスン着や、参考になるバレエダンサーがみつかりますよ!
体型が気になりはじめるお年頃!?ジュニア向けスタイルアップできるレオタード選びのポイント

ジュニアの対象年齢は小学校高学年から高校生までと幅広いですが、思春期とも重なるため体型が気になり始める年頃ともいえます。
そういった時期にはスタイルアップして見えるレオタードがおすすめ。
体型のお悩み別にスタイルアップできるレオタードを紹介します。
体型が全体が気になる
体型全体が気になるという方はレオタードを着ることに抵抗を感じることも多いです・・。
そういった場合にはレオタードのカラー選びがポイント。
明るい色は「膨張色」なのでレオタードのカラーで選んでしまうと体が実際より少し大きく見える効果があります。
一方で、黒やネイビー・ダークグリーンなどの濃いカラーは「収縮色」といって、体が引き締まって見える効果があります。
また、濃いカラーの「収縮色」に合わせて袖が長いタイプのレオタードだと気になる腕周りをカバーでき、腕が長く見える効果も!
色を味方につけてスタイルアップを目指してみましょう。
肩幅が気になる
レオタードを着る際に意外と多いのが肩幅の悩みです。
具体的には、いかり肩(肩幅が広い)と「体がガッチリ見えてしまう」、逆になで肩(肩幅が狭い)場合は「レオタードの肩紐がずり落ちる」といった悩みが多いです。
いかり肩(肩幅が広い)が気になる方はVネックやダイヤモンドネックの袖付きレオタードがおすすめです。
首元を深くすっきりあいたVネックやダイヤモンドネックの袖付きレオタードは、首の長さ(縦のライン)が強調され、肩幅(横の広がり)に目が行きにくくする効果があります。
なで肩(肩幅が狭い)が気になる方は衿元(えりもと)が広がりにくいレオタードがおすすめ。
なで肩の方で多い悩みはストラップが落ちやすいことです。そういった場合は背面でボタンが留められるバックスナップ付きレオタードや、背面の高い位置がつながっているデザインのレオタードを選んでみましょう。
胸元が気になる
キッズのレオタード選びにはなかった悩みといえば胸元が気になるという問題です。
「胸の成長は早くて8歳頃から始まり、20歳前後までに成長が完了する」と言われています。
そのため、「バストのボリュームで太って見える」、「胸元が目立つのでレオタードを着たくない」という悩みも。
胸元が気になる方へおすすめのレオタードはボートネックのものやハイネックのデザインのレオタードです。
ボートネックは前かがみになっても胸元が見えないので安心できます。
さらに背中開きが浅めのレオタードなら、下にブラトップを着用しても見えにくいので◎
ハイネックのレオタードは胸元を完全にカバーしてくれるので、しっかりカバーしたい方におすすめです。
まとめ

バレエを習っているジュニアの場合はヴァリエーションを踊る機会が増えたり、少しレッスンが難しくなることも多いですよね。
また、思春期に差し掛かり体が変化する時期でもあります。
スタイルが気になってレッスンに集中できないということもありますので、自分自身が自信を持ってレッスンできるレオタードを選んでみましょう。
-
7.82025
トゥシューズの魅力に迫る!あこがれのトゥシューズの歴史と文化


トゥシューズは、バレエの象徴ともいえる存在。
美しく繊細なその姿に、多くのバレエファンが魅了されます。
しかし、その裏側には職人の技やダンサーの努力、そして舞台での輝きが詰まっています。
本記事では、トゥシューズの基本から文化的背景、そして楽しみ方まで、バレエファンが知りたい情報をたっぷりお届けします。トゥシューズとは?その美しさの秘密

トゥシューズとは、その名の通り「つま先で立つためにつくられた靴」です。
バレリーナはトゥシューズを履き、つま先立ちで踊ります。
光沢感のある生地で、つま先立ちをしたバレリーナの足元はとても美しいです。
ここではそんなトゥシューズの美しさの秘密に迫ります。なぜトゥシューズはバレエの象徴とされるのか?
トゥシューズは、バレエと聞いて最初に思い浮かぶアイテムのひとつ。
その美しさはバレエそのものを象徴し、エレガンス、軽やかさ、そして努力の結晶として多くの人を魅了します。
トゥシューズの淡いピンクや繊細なリボン、ポワント部分のフォルムなどは、バレエそのものを象徴する気品と美しさを持っています。バレエダンサーにとってトゥシューズは特別!
ダンサーにとってトゥシューズはただの道具ではありません。
トゥシューズは、初心者がすぐに履けるものではなく、何年もの訓練を経て、足や体幹を強化し、ようやくトゥシューズを履いて踊ることができます。
何度も練習を重ね、自分の足と一体化するまでの過程で特別な絆が生まれます。
ダンサーにとってトゥシューズを履くことは努力の証で、特別な意味があるんですよ。トゥシューズの構造
一見するとシンプルに見えるトゥシューズですが、その構造には細かな工夫が詰まっています。
つま先部分を「ボックス」といい、ダンサーがつま先で立てるように硬い構造になっています。
足裏のソールの部分には、アーチをサポートする「シャンク」という板状のものが入っています。
外側は光沢感のあるサテンの生地が使われていて、美しさと高級感が感じられます。ダンサーがトゥシューズを履いて踊る理由
バレリーナが履いているトゥシューズは、18世紀に生まれたといわれています。
それまではなんとヒールでバレエを踊っていたそうです・・・!
妖精のような軽やかで幻想的な踊りを追求して、女性ダンサーがつま先立ちで、床から足が浮き上がって見えるような動きを作るために開発されました。
トゥシューズを履くことで、バレエの踊りの幅が広がり、さまざまな表現が可能になりました。
バレエの芸術にはトゥシューズが必要不可欠なのです。トゥシューズの製作と歴史

トゥシューズは現代のバレエに欠かせないものです。
日頃トゥシューズを履いて踊っている人もトゥシューズがどのようにして作られているかは知らないのではないでしょうか?
ここではトゥシューズの歴史とともにトゥシューズの製作過程を見ていきましょう。トゥシューズができるまで
トゥシューズは、熟練の職人が一足ずつ手作業で仕上げます。
硬いボックス、丈夫なシャンク、柔らかい布など、さまざまな素材を使用してトゥシューズは作られます。
ボックスを形作り、シャンクを用いてソールを作り、そこに布地を貼り付けていきます。
トゥシューズの製作過程を紹介した動画もあるので、興味のある方は見てみてください^^
初めてトゥシューズを履いたバレリーナは?
トゥシューズが登場するまでは、ヒールのある靴でバレエを踊っていました。
18世紀にパリオペラ座のマリー・カマルゴが初めてヒールを取って踊り、これがトゥシューズのもとになりました。
その後、19世紀に入り、アマリア・ブルニョリというダンサーが初めてつま先立ちで踊り、注目を浴びました。
その刺激を受け、マリー・タリオーニというダンサーが最初から最後までつま先立ちで踊る技法を披露しました。時代ごとに進化したトゥシューズのデザイン
アマリア・ブルニョリがつま先立ちで踊った頃、当時のシューズはまだつま先部分が柔らかかったそうです。
つま先が硬くなったのは19世紀の終わりごろ。
イタリアの靴メーカーがシューズの先を硬くして立ちやすくしました。
トゥシューズが今のような形になったのは20世紀初頭ごろのことです。
つま先をさらに硬くし、さらにソール部分に皮を入れ、現在使われているトゥシューズになりました。トゥシューズを楽しむ

バレエダンサーにとって特別なものであるトゥシューズ。
その可憐な見た目にはバレエをやっていない人も魅了されます。
最近では「バレエコア」の流行により、バレエをやっていない人の間でもバレエらしい服装やグッズが注目を浴びているんです。トゥシューズをインテリアに?
バレエを象徴するトゥシューズは履くだけではなくインテリアにもなっちゃうんです!
新品のトゥシューズをそのまま置いてももちろん可愛いですし、トゥシューズのリボンを結んで壁にかけても可愛いです♪
また、トゥシューズの中に造花を入れたり、レースなどでデコレーションして飾っても可愛いですよ。
買ったけど足に合わず履かなかったトゥシューズを飾ったり、観賞用にネットで安めのトゥシューズを買って可愛いインテリアにしてみてはいかがですか?トゥシューズをモチーフにしたグッズ
キーホルダーやチャーム、ハンカチ、トートバッグなど、トゥシューズをモチーフにしたグッズはたくさんありますね!
特に最近の「バレエコア」ブームのおかげでトゥシューズをモチーフにしたグッズはますます増えています。
グッズを持っているとさりげなくバレエ愛を表現できますね。
このようなグッズはバレエをやっている人へのプレゼントとしてもおすすめですよ!トゥシューズをテーマにしたアート作品
バレエをテーマにした写真や絵画にもトゥシューズは描かれています。
例えば、有名なバレエ画家エドガー・ドガの作品には、トゥシューズを履いたバレリーナたちが繊細に描いてあります。
ドガが描くバレリーナはとても美しく、チュチュの舞い方や指先・足先の美しさから躍動感が感じられます。
ドガは19世紀の画家ナノで、現代のトゥシューズや衣装との違いを楽しめるのも面白いですね。
このようなアート作品でもトゥシューズを楽しむことができます。まとめ

いかがでしたか?
今回はトゥシューズについてお話ししました。
トゥシューズには、美しさだけでなく、努力や情熱、そしてバレエ文化そのものが詰まっています。
この小さな靴に込められた物語を知ることで、バレエがもっと特別なものに感じられるはずです。
ぜひみなさんもトゥシューズの世界をのぞいてみてください! -
7.72025
バレエオープンクラスってどんな雰囲気!?オープンクラスについて知ろう!!


バレエのレッスンクラスにはオープンクラスがあるのを知っていますか?
大人の方が通っているイメージが多いかと思いますが、実は年齢やレベルは様々です。
オープンクラスについて、特徴やメリット、デメリットについて紹介します!
オープンクラスが気になっているという方はチェックしてみてくださいね!
レベルや雰囲気は?オープンクラスってどんなクラス?

オープンクラスという言葉を聞いたことがあるものの、どんなクラスなのか知らないという方は多いかもしれません。
オープンクラスについて普通のクラスとの違いや特徴を紹介します!!
オープンクラスと普通のクラスとの違い
普通のクラスの場合は、バレエ教室やスタジオに登録が必要だったり、レッスンの曜日が固定されていたり、毎月お月謝を払って通うことが一般的となっています。
しかし、オープンクラスの場合は「オープン」とあるように、多くの方向けに開かれてたクラスのことで、バレエ教室やスタジオに所属しなくても、気軽に1回限りの参加が可能です。
オープンクラスの特徴
オープンクラスは、バレエ教室やスタジオに所属していても誰でも単発で参加できることが多いです。
大きなバレエスタジオのオープンクラスの場合は、レッスン数や講師の数もバラエティ豊か。
メソッドも講師によって違ったり、レッスンに参加している生徒さんも様々な方がいらっしゃいます。
そのため、プロのダンサーが参加していたりする場合も。
また、バレエ団が開催しているバレエクラスでは現役や元バレエダンサーが講師を務めることもあり、運が良ければプロに教えてもらえます。
毎回生徒さんの顔ぶれは異なるので、人間関係のしがらみはあまりありません。
受講する人数が多いので、講師から全体へのアドバイスはあるものの個人へ向けた指導は少ない、もしくはないのが通常です。
オープンクラスのレベル
オープンクラスを受講するにあたって、クラスのレベルが気になるという方は多いでしょう。
オープンクラスにも初級・中級・上級とレベル分けされているクラスもありますが、1つのクラスに初級から上級といった様々なレベルの方が一緒になってレッスンを受けるというところもあります。
いいことたくさん!?オープンクラスに通うメリットを知ろう!

普通のクラスに通うのか、オープンクラスに通うのがいいのか迷ってしまう方も多いでしょう。
バレエのオープンクラスに通うメリットは実はたくさんあります!!
オープンクラスに通うメリットを紹介していきますので参考にしてみてくださいね!!
スケジュールが自由に決められる
バレエのオープンクラスの一番のメリットは、自分の都合に合わせてレッスンを受けられることです。
例えば仕事や家庭の予定がはっきりしない方や(週によって違う等)、いつものレッスンに加えてレッスンを一時的に増やしたい方等、様々な事情があったとしても気軽に受講できるのがオープンクラスの魅力です。
どこでも受講できる
オープンクラスは多くの場合、会員登録なしにレッスンを受講することができます。
どこの教室やスタジオに所属しなくてもレッスンを受けられる自由さがあります。
また、旅行先や海外などオープンクラスが開かれていれば、どこでも好きな場所でレッスン受講が可能です。
こんなことに気をつけて!オープンクラスに通うデメリットを知ろう!

好きなタイミングでバレエのレッスンを受けられるなど自由度の高いといったメリットがある一方で、気をつけるべきデメリットもあります。
オープンクラスのデメリットについても理解しておきましょう。
レッスン内容が毎回違う場合がある
オープンクラスは毎回レッスンに来る人が違うことも多いので、レッスンに来た人たちに合わせてレッスン内容が異なる場合もあります。
オープンクラスを担当している講師が代行になったり、中には固定でない場合も。
そういった点には、柔軟に対応する必要があるでしょう。
期限付きのチケット制であることが多い
オープンクラスは毎月決まった額を支払う月謝制ではなく、チケット制であることがほとんどです。
チケットには期限がある場合が多いので、期限内にチケットを消費する必要があります。
割高になってしまうこともありますが、期限内に通えなそうな場合は1回券で様子をみるのがいいかもしれません。
個人へ向けた指導が少ないorない
オープンクラスは人数が多く、レベルも様々な方が集まっているため個人へのアドバイスや指導が少ないか、ほとんどありません。
そのため、ある程度バレエの知識を持って受講する必要があります。
オープンクラスの中には、バレエ初心者の方へ向けた、入門や初級といったレベル分けされたクラスもあるので、自分にあったレベルのクラスを受講すると良いでしょう。
オープンクラスはどこで受けられる!?おすすめのオープンクラス

どういったところでオープンクラスが開催されているかわからない場合も多いでしょう。
下記におすすめのオープンクラスを紹介していきますので、オープンクラスの受講を検討している方は参考にしてみてくださいね!
Angel R
バレエスタジオのAngel Rはオープンクラス制でクラスを自由に選んで受講することができます。
レベルや目的が細かく分かれているため、自分にあったクラスが見つけやすいのも◎
週に200を超えるクラスがあり、レベルや目的、ライフスタイルに合わせてお好きなクラスを受講することができますね。
スタジオ所在地
表参道校/渋谷校
チャコット
バレエグッズの専門店として有名なチャコットではバレエを含む様々なダンスのクラスを開講しています。
その中にはバレエのオープンクラスもあります。
オープンクラスの場合は予約も必要ないので、好きな時間に受講することが可能です。
1回券での受講も可能ですが、入会し会員になると会員価格で受講でき回数券もお得に購入することができます
一度、受講してみてクラスが気に入ったなら、入会してみても良いかもしれません。
オープンクラスが開催されているチャコットのスタジオ一覧
東京都
・代官山スタジオ・宮益坂スタジオ・池袋スタジオ・勝どきスタジオ
神奈川県
・たまプラーザスタジオ・横浜スタジオ
愛知県
・名古屋スタジオ
大阪府
西心斎橋スタジオ
兵庫県
神戸スタジオ
有名なダンサーが講師を担当していることも多いのがチャコットのクラスです。
運が良ければ有名ダンサーにバレエを教えてもらえるかも!?
NOAバレエスクール
NOAバレエスクールは様々なレベルのバレエが自由に受けられるオープンクラスのバレエ教室です。
バーレッスンやストレッチに特化したクラスもあるので未経験からも気軽に始められます。
料金はコース制ですが、月2回、月4回、月6回、月8回の全回数コースが、在籍の限り無期限で繰越しが可能です。
コースの回数も変更可能なので、いつでもレッスンを受けたいときに受けたいだけ受講ができるんです。
スタジオ所在地
都立大校、/池袋校/新宿校/秋葉原校/恵比寿校
まとめ

バレエのオープンクラスは「全てのバレエのレッスンを受けたい方のために開かれているクラス」といっても過言ではありません。
そのため、レッスンの受講人数やレベル、内容が異なる様々なオープンクラスがあります。
中にはレベル分けがはっきりされているクラスや、有名講師が教えるクラスも。
自分の都合やレベルに合った、オープンクラスを見つけるとバレエを続けやすい場合も多いです。
バレエのオープンクラスが気になっている方は、自分に合ったオープンクラスをぜひみつけてみてくださいね!!
-
7.72025
まだまだ遅くない!!中学生から始めるバレエの習い方を徹底解説!!


現在、子どもから大人までバレエを習う方は増えています。
そのため、中学生になってからバレエを習いたいという方も多くいらっしゃいます。
今回は中学生からバレエを習いたいという方のために、バレエを習う際のメリット・デメリット、悩みの解決、おすすめの習い方などを紹介いたします。
バレエを習うことを検討している方は参考にしてみてくださいね!!
バレエは中学生からでも始められる!!メリット・デメリットを知ろう

「バレエは早くから始める方が良い」というイメージがありますが、中学生からでも何歳からでも始めることができます!!
「バレエは早くから始める方が良い」と言われている理由や中学生からバレエを習うメリット・デメリットについて紹介します。
バレエを早く始めると良いと言われる理由
一般的に4~5歳くらいでバレエを始める方が多いですが、プロを目指すのであれば小学校の低学年(6歳~8歳)くらいに習い始めるのが理想だとされています。
その理由は、幼少期より柔軟性を高めたり、骨格を整える必要があるからです。
しかしながら、世界的なバレエダンサーである熊川哲也さんがバレエを始めたのは10歳からなんです!!
柔軟性や基礎力が実際にしっかり自分で意識して使っていけるようになるのは、10才から12才くらいだと言われています。
また、中学生から高校生は一番身体能力の高い年齢とされているため、むしろ何かを始めるには適した時期でもあります。
何歳から始めても自身の努力次第で、どこまでもバレエの上達を目指すことができます。
バレエを始めるメリット
子どもから大人まで人気の高い習い事であるバレエにはメリットがたくさんあります。
特に中学生から大人がバレエを習うと良いことを紹介します!!
美脚を目指せる
中学生は体型が気になるお年頃ですよね。
しかしながら、無理なダイエットは体を壊してしまうのでよくありません。
では、「何をしたらいいの?」と悩む方も多いでしょう。
そういった方に、体型が整い、美脚を目指せるバレエのレッスンがおすすめです。
表面上の筋肉を闇雲に鍛えてしまうと筋肉が大きく見えて太って見えてしまう場合もありますが、バレエで使う筋肉はインナーマッスルを使うので体の奥深くにある筋肉を鍛えることができます。
そのため、ほっそりとしていながらも必要な筋肉のついた美脚を目指せるんです!
一般的にバレエに向いている足の形は真っ直ぐか、X脚だといわれており、生まれつきの部分も大きいですが、正しいレッスンを行うことでバレエ向きの足に近づくことができます。
姿勢が美しくなる
中学生の姿勢が悪くなる原因には、筋力低下や生活環境の変化、生活リズムの乱れ、悪い座り方がクセになっていること、 長時間のスマホやタブレットの使用が挙げられています。
姿勢の悪さが気になるという方にもバレエのレッスンはおすすめです。
バレエを踊っている間は優雅に見えるよう、姿勢を美しく保つ必要があります。
そのため、普段のレッスンから姿勢が美しく見えるよう、背筋を伸ばし、肩甲骨を寄せ、首や顎を引くこと等を意識しレッスンを行なっています。
レッスンから意識しているので普段の生活にも影響し姿勢が良くなります。
柔軟性を高め怪我の防止になる
バレエでは全身の筋肉を伸ばしたり動かすので柔軟性を高めることができます。
また、バレエには柔軟性が必要なのでストレッチは必須。
体の柔軟性を高めることで筋肉や腱、関節への負担を軽減できるので怪我の防止に繋がります。
怪我を防げるということは今後の人生においてもプラスになりますね。
バレエを始めるデメリット
バレエを習うことで発生するデメリットはそれほど多くありません。
圧倒的にメリットの方が多いですが、参考にしてみてください。
怪我のリスク
柔軟性を高めることで怪我の防止になる一方で、正しいレッスンを行わないと怪我に繋がってしまう場合もあります。
怪我をしてしまうと日常生活に支障が出てしまう他にも体育の授業に参加できなくなるといったことも起こり得ます。
バレエのレッスンをたくさん受けたい気持ちが大きく体を酷使すると疲労骨折にも繋がってしまうので、適切なレッスン時間、回数を守ることが大切です。
習得に時間と忍耐力が必要
バレエを習得するにはかなりの時間がかかります。
バレエの基礎を子どもが習得する場合は5年程度必要とされています。
基礎から正しく習うことが上達の早道です。
続けていれば必ず上達できますが、レッスンを続けるための忍耐力も必要です。
しかしながら、中高生といった学生には、大人よりも使える時間がたくさんあるので学生のうちからバレエを始めるのはとても良いことです!!
心配しなくても大丈夫!中学生からバレエを始める時のお悩み解決!

中学生からバレエを始める際に、悩み事や心配に思っていることはありませんか?
中学生ならではの悩みを抱えている方も多いようですので、バレエに心配なく通えるよう、中学生にありがちなお悩みを解決していきます!!
レッスンのレベル
初めてバレエを習う際には「レッスンについていけるか」ということを心配する方が多いかもしれません。
自分のレベルがわからない場合は、どのクラスを受講すべきかをバレエの先生に相談してみましょう。
大体のバレエクラスは入門や初級などレベルによってクラス分けされています。
バレエを初めて習う時は、入門クラスや初級クラスで一から丁寧に基礎を学ぶことが上達への早道です。
バレエ経験者の中学生向けのレッスンに混ざることもできますが、「レッスンが難しい」、「ついていけない」と感じた場合は躊躇せずにクラスのレベルを変更しましょう。
勉強との両立は可能か
中学生という学生の場合は勉強も大事ですね。
そのため、学校のスケジュールと合わせて通えるバレエレッスンを探す必要があります。
多くのバレエレッスンは平日の場合、夕方以降に開催され学校と被らない時間になっていることが多いです。
また、大人のクラスには仕事や家庭の都合などから土日に開催されているクラスも。
長く続けるためにも、自分の都合にあった時間帯に開催されているクラスを選びましょう。
バレエはお金がかかる?
バレエはお金がかかるイメージのある習い事ですよね。
中学生の場合は、保護者の方にレッスン費を払ってもらう場合が多いので、「お金がかかる」ことを心配・悩みになっている方も多いです。
バレエを習うのにお金がかかる原因は発表会やコンクール、留学費用などが挙げられます。
そのため、これらに関わらない場合は他の習い事とさほど費用は変わりません。
レッスン費用は週に何回通うかによっても変わりますので、保護者の方ともよく相談してみてくださいね。
中学生からのバレエはここで習うのがおすすめ!中学生がバレエを習える場所

どこでバレエを習うかわからないという方も多いでしょう。
中学生からバレエを習うのにおすすめの場所を紹介します。
バレエを習うのを検討している方は参考にしてみてくださいね!!
おすすめのバレエ教室
バレエを習うならやはり、本格的なバレエレッスンを行なっているバレエ教室がおすすめです。
前述の通り、「レッスンについていけるかわからない」といった場合には大人の初級に通ってみましょう。
Gravisバレエスタジオ
日本最大級のダンススクールが運営するバレエスクールです。
中学生からバレエを始める初心者向けのレッスンも開催されていますので、安心して通うことができますよ。
NOAバレエスクール
NOAバレエスクールでバレエレッスンの基礎であるバーレッスンを専門としたクラスもありバレエ初心者がバレエを始めやすい環境が揃っています。
バレエのための体作りを基礎から丁寧に教えてくれるため初心者も通いやすいです。
おすすめのダンススタジオ
様々なジャンルのダンスレッスンを開催するダンススクールでは、バレエのレッスンも開催されていることが多いです。
ダンススクールの場合は他のダンスの基礎を学ぶためにバレエのレッスンに参加しているという方もいます。
そのため、他のダンスのスキルは高くてもバレエは初心者という場合も。
バレエ初心者というスタートは同じなので、中学生からでも気軽に通うことができそうです
セーラーズスタジオ
自由が丘のバレエ・ダンス教室 セーラーズスタジオはバレエに力を入れているダンススタジオです。
そのため、質の高いバレエレッスンを受けることができます。
中高生の生徒さんの多くが大人クラスに通っているそうで、中学生からバレエを始める際も気負うことなく通えそうです。
BROADWAY DANCE CENTER(ブロードウェイダンスセンター)
初心者からプロまで幅広いレベルの方が通っているダンススタジオです。
様々なジャンルのダンスレッスンが開催されており、バレエのクラスもあります。
チケット制で予約不要、月会費なしのため気軽にバレエを始められます。
まとめ

バレエは何歳からでも始められます!
中学生から高校生は一番身体能力の高い年齢ということもありバレエを始めるのに適しています。
そのため、正しいレッスンを受ければ上達も早いはず!
自分のレベルやスケジュールに合ったバレエレッスンをみつけて、ぜひバレエに挑戦してみてくださいね!!
バレエKnow 記事一覧
- バレエをもっと楽しく!バレエ整体って?どんな効果があるの?
- 気軽にバレエを始めよう!美しい身体を手に入れるためのバレエエクササイズ
- バレエと音楽の魅力とは?名曲が生み出す感動の世界
- バレエを通じて楽しく英語!小さいお子様にピッタリなバレエ英語レッスンの魅力とは?
- リノリウムってなに!?お稽古場や舞台の床について知ろう!!
- 国内トップレベル!?国際バレエコンクール【ジャパングランプリ】を徹底解説!!
- バレエのティアラは作れる!?バレエティアラを作ってみよう!!
- バレエの衣装はサイズ調整できる!?ムシの作り方を徹底解説!!
- お家でもバーレッスン!?自主練用のバーはどんなものがいいのか徹底検証!!
- エレガントさがアップする!?自分にぴったりのティアラをみつけよう!!
- 【初心者向け】これからバレエを始める方必見!バレリーナの足を知ろう!バレエレッスンのための基礎知識
- バレエをやっていたら一度は読みたい!?人気バレエ漫画TOP 5
- 【高校生以上編】新国立劇場バレエ団の団員になるには?オーディションを徹底解説!
- バレエグッズを手軽に買おう!バレエ用品専門通販サイト4選!
- どんなものが最適?もらって嬉しいバレエ発表会のプレゼント
- 【中級者向け】バレリーナのような足を目指そう!美しい筋肉の付け方を徹底解説!
- 花のワルツってどんな曲?バレエの有名な曲について知ろう!!
- 【小中学生編】新国立劇場バレエ団付属のバレエ研修所について徹底解説!!
- 人気のヴァリエーション!キュートなキューピットについて知ろう!!
- 信じていれば夢は叶う!!夢と魔法がつまったバレエ作品『シンデレラ』の全幕を徹底解説!
- ロマンティク・バレエの代表作!「ジゼル」の全幕を徹底解説!
- バレエを描いた映画やドラマ・アニメはある?おすすめ作品紹介!
- 舞台が魔法に包まれる!?バレエ版『アラジン』を徹底解説!!
- バレエの人気作品!「コッペリア」の全幕を徹底解説!
- 実はあらすじがある!?バレエ『ボレロ』を徹底解説!!
- バレエ作品『エスメラルダ』のあらすじ・どこで観れる?を徹底解説!
- 体が硬くても大丈夫!小学生の柔軟性を高めるバレエストレッチ
- 子どものバレエスタジオ選びで後悔しないために!親が知っておくべき4つのポイント
- 初心者でも簡単!美しいバレエポーズの基本とコツ
- 華やかさと大人な雰囲気が魅力『パキータ』のあらすじとヴァリエーションを徹底解説!!
- ダイナミックで勇ましいバレエ作品『海賊』の全幕を徹底解説!
- 3大バレエの1つ!『くるみ割り人形』の全幕を徹底解説!
- コミカルで華やか!!『ドン・キホーテ』の全幕を徹底解説!
- 3大バレエの1つ!『白鳥の湖』の全幕を徹底解説!
- 3大バレエの1つ!『眠れる森の美女』の全幕を徹底解説!
- 発表会の必需品!!衣装バッグはどんなものが最適?衣装バッグを徹底解説
- 自分にぴったりのチュチュを探そう!バレエの衣装チュチュについて徹底解説!!
- バレエキッズはなにを履けばいいの?キッズにおすすめのバレエタイツ
- 寒さ対策&着痩せ効果にバッチリ!おしゃれなバレエトップスをみつけよう!!
- 【バレエ衣装】レンタルの流れって?レンタルとオーダーはどっちがいいの?
- バレエといえばシニヨン!!ネットからきれいなシニヨンの作り方まで解説!!
- バレエタイツは履く必要がある?ない?バレエレッスンの必需品バレエタイツを徹底解説!!
- 男性バレエダンサーの必須アイテム!?バレエの男性用タイツを徹底解説!!
- バレエ用品といえばチャコット!チャコットでレオタードを選ぼう!!
- 何を着て踊るの?男性バレエダンサーの衣装を徹底解説!!
- バレエの舞台に必須!?男性バレエダンサーについて知ろう!!
- スタイルアップでモチベーションもアップ!?バレエでジュニアにぴったりのレオタードをみつけよう!
- トゥシューズの魅力に迫る!あこがれのトゥシューズの歴史と文化
- バレエオープンクラスってどんな雰囲気!?オープンクラスについて知ろう!!
- バレエ舞踊歴70年以上!!伝説のプリマ森下洋子さんを知ろう!!
カテゴリ一覧
- イベント報告・体験談 (35)
- クラス内容予告 (186)
- バレエKnow (79)
- バレエ上達コラム (121)
- フェスティバル等 (44)
- メディア紹介 (42)
- レッスン体験談 (319)
- ワークショップ (176)
- ワークショップ(MT) (5)
- 通常のお知らせ (825)
- 重要なお知らせ (346)
- 重要なお知らせPickUp (11)












![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42d3c8b6.63f29962.42d3c8b7.bc59e7fd/?me_id=1397120&item_id=10000531&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzenlo%2Fcabinet%2F10783400%2F1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10099496&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2F041120-0015-35.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42d34234.4f5536d4.42d34235.3aedd820/?me_id=1221746&item_id=10065354&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmile88%2Fcabinet%2Fmaster%2F1st%2Fa14334.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10100497&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fgift%2F270402-0309-41.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10100979&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fgift43%2F270402-0908-43.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/35d7128d.2ceaf6db.35d7128e.33a92714/?me_id=1203237&item_id=10004557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmignon%2Fcabinet%2Fbag-t115-0005.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10098067&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2F013130-0032-28.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f78be55.c77cd084.3f78be56.0988848a/?me_id=1272374&item_id=10002274&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fballetarabesque%2Fcabinet%2Fsylvia%2Fsy-foot-c.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/35d7128d.2ceaf6db.35d7128e.33a92714/?me_id=1203237&item_id=10000666&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmignon%2Fcabinet%2Fcross202411%2Fting1115.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/35d727c0.913227ae.35d727c1.5882eb44/?me_id=1224778&item_id=10000767&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Feballerina%2Fcabinet%2Fitem4%2F0100056-main5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10100901&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fseason43%2F050200-0929-43.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10101531&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fseason51%2F050210-0435-51.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4268cc01.e7f62d45.4268cc02.c24757e4/?me_id=1235977&item_id=10007749&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstyle-depot%2Fcabinet%2Fchacott%2F4009656617es.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10100230&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fseason34%2F050253-1203-34.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10091729&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fcosme%2F503643-0368-88.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10097289&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fcosme%2F503644-0900-18.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a20281a.f631cbf4.4a20281b.c5c5be16/?me_id=1312651&item_id=10072020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbotanic-garden%2Fcabinet%2Fbrand01%2F132%2F132-098-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f3e00cc.5f3b2940.2f3e00cd.f1d2faaf/?me_id=1227200&item_id=10090046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcosmecomonline%2Fcabinet%2Fitem-img2009%2Fitem_1000107376_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10101527&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fcosme%2F502640-0983-58.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10071986&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fcosme%2F502670-0203-58.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42a90a92.3dc1a3b0.42a90a93.67a52acd/?me_id=1428264&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimii%2Fcabinet%2F001%2Fimgrc0138146867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10072218&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2Fcosme%2F503643-0383-58.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10098066&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2F013130-0031-28.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10098068&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2F013130-0033-28.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10101456&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fchacott%2Fcabinet%2Fseason55%2F256331-7210-55_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4268cc01.e7f62d45.4268cc02.c24757e4/?me_id=1235977&item_id=10007079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstyle-depot%2Fcabinet%2Fchacott%2F4009658017bq.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3097817c.7751753e.3097817d.56729b98/?me_id=1240170&item_id=10099516&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchacott%2Fcabinet%2F055937-6403-35.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/35d7128d.2ceaf6db.35d7128e.33a92714/?me_id=1203237&item_id=10000574&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmignon%2Fcabinet%2Fcross202111%2F2021111603.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)